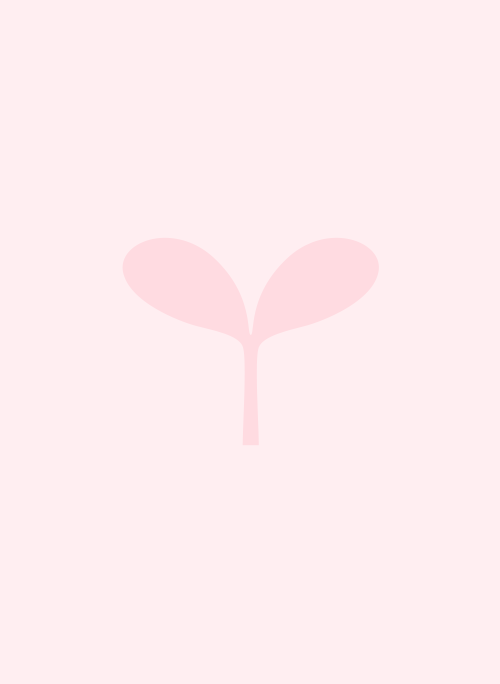1
朝、リビングに顔を出すと、いつものように朝食が並んでいた。
食事はガクが作る。朝昼晩と三食。味もなかなかいける。さすがはオカマと言ったところだ。僕がこの鬼畜を追い出さないでいるのは、あるいはこの食事のせいと言えるかも知れない。
「おはよう」
キッチンからガクが顔を出した。長い髪を束ね、エプロンを着けている。この光景にもさすがに慣れた。
もっとも、ガクが美青年でなければ、ぶん殴ってでも止めさせただろうが。
僕は黙ってテーブルについた。
鼻歌が聞こえた。今日はとりわけ機嫌がいいらしい。
それもそうだろう。何せ、昨夜は一晩中レイの体を弄び、陵辱の限りを繰り返したのだから。
「……女は?」
「ゴミ屑のように眠ってるわ」
「だろうな」
僕は寝覚めのコーヒーをすすり、テーブルの横の窓に目を向けた。青々としたブナ林に朝日が差し込み、朝露に濡れる林道を暖かく包んでいた。
朝、リビングに顔を出すと、いつものように朝食が並んでいた。
食事はガクが作る。朝昼晩と三食。味もなかなかいける。さすがはオカマと言ったところだ。僕がこの鬼畜を追い出さないでいるのは、あるいはこの食事のせいと言えるかも知れない。
「おはよう」
キッチンからガクが顔を出した。長い髪を束ね、エプロンを着けている。この光景にもさすがに慣れた。
もっとも、ガクが美青年でなければ、ぶん殴ってでも止めさせただろうが。
僕は黙ってテーブルについた。
鼻歌が聞こえた。今日はとりわけ機嫌がいいらしい。
それもそうだろう。何せ、昨夜は一晩中レイの体を弄び、陵辱の限りを繰り返したのだから。
「……女は?」
「ゴミ屑のように眠ってるわ」
「だろうな」
僕は寝覚めのコーヒーをすすり、テーブルの横の窓に目を向けた。青々としたブナ林に朝日が差し込み、朝露に濡れる林道を暖かく包んでいた。