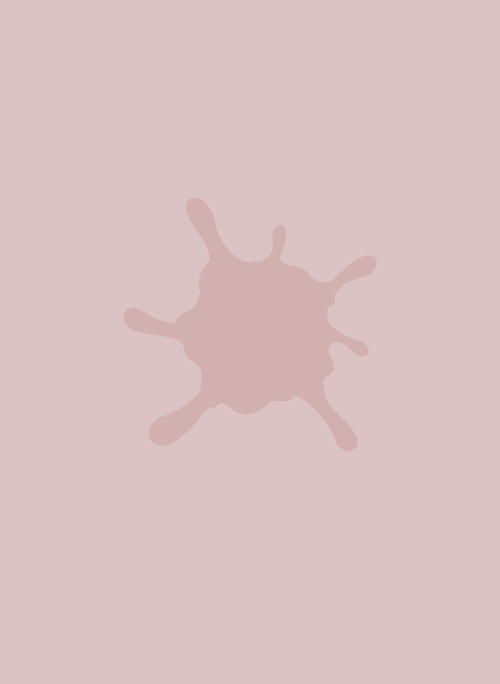彼は彼女を、公園のベンチに座らせた。
人もまばらな、午後九時。
彼らに目をとめる者もなかった。
「サキチャン、やっと二人だね。君の事、ずっと気になっていたんだ。」
彼は、彼女の背中に手をまわす。彼女は微笑みながら、彼を見つめていた。
「サキチャン、僕の事、どう思ってる?」
彼女は笑顔をたたえたまま。
微笑しながらその問いをはぐらかしているようでさえある。
「今日も、かわいい服だね。このブラウス、すごく似合う。」
彼はうっとりと、襟元から頬に触れた。
彼女はただ、大人しくそれを受け入れる。
笑顔のまま、まばたきもせずに。
彼は、切々とその思いを彼女に打ち明けた。
彼女は静かに、彼の話を頷くのも忘れ聞いている。
「サキチャン!もう!なんとか言ってくれよ!!」
彼は、とうとうじれったくなり、彼女の胸元に触れた。
……しかし、抵抗する様子もなく、彼女はされるがまま。
彼はついに、そっと彼女に口づける。
彼女の唇は、冷たい。
ツヤのあるその唇に、彼は自分の温もりを伝えるように、彼女を優しく抱きしめた。
「サキチャン……。」
彼女の衣服の乱れを、気にしてあげる余裕もなく、彼は夢中になって彼女の名前をよぶ。
風はもう冷たい。
そして、彼女の身体もまた、冷えていた。
彼は彼女の手を優しくひいた。
「うち、行こうね……。」
しかし、彼女は立ち上がらなかった。身をかたくし、座りこんだまま。
「サ、サキチャン、どうして?どういう事?僕の気持ち、わかってくれたよね?」
彼女は答えない。ただ、彼に微笑みながら。
「僕…、オレ…、こ、こんな屈辱初めてだよ。な、なんだよ……、ただずっと笑いやがって。オレの事、馬鹿にしてるのか!!」
彼が彼女の手を強くひくと、彼女は宙に浮いた。
「オ、オマエなんて……コウシテヤル!」
彼は身体を強く遊具にたたき付けた。
あまりに突然の事で、彼女は声もでなかった。
ただ、公園には、身体が割れる、バリッという音のみ響き続けた。
−−−翌日。
公園には、バラバラになった微笑むマネキンと。
近くのデパートから引取にきた警備員が。
木陰でひっそりと口づけを交わしていた。
人もまばらな、午後九時。
彼らに目をとめる者もなかった。
「サキチャン、やっと二人だね。君の事、ずっと気になっていたんだ。」
彼は、彼女の背中に手をまわす。彼女は微笑みながら、彼を見つめていた。
「サキチャン、僕の事、どう思ってる?」
彼女は笑顔をたたえたまま。
微笑しながらその問いをはぐらかしているようでさえある。
「今日も、かわいい服だね。このブラウス、すごく似合う。」
彼はうっとりと、襟元から頬に触れた。
彼女はただ、大人しくそれを受け入れる。
笑顔のまま、まばたきもせずに。
彼は、切々とその思いを彼女に打ち明けた。
彼女は静かに、彼の話を頷くのも忘れ聞いている。
「サキチャン!もう!なんとか言ってくれよ!!」
彼は、とうとうじれったくなり、彼女の胸元に触れた。
……しかし、抵抗する様子もなく、彼女はされるがまま。
彼はついに、そっと彼女に口づける。
彼女の唇は、冷たい。
ツヤのあるその唇に、彼は自分の温もりを伝えるように、彼女を優しく抱きしめた。
「サキチャン……。」
彼女の衣服の乱れを、気にしてあげる余裕もなく、彼は夢中になって彼女の名前をよぶ。
風はもう冷たい。
そして、彼女の身体もまた、冷えていた。
彼は彼女の手を優しくひいた。
「うち、行こうね……。」
しかし、彼女は立ち上がらなかった。身をかたくし、座りこんだまま。
「サ、サキチャン、どうして?どういう事?僕の気持ち、わかってくれたよね?」
彼女は答えない。ただ、彼に微笑みながら。
「僕…、オレ…、こ、こんな屈辱初めてだよ。な、なんだよ……、ただずっと笑いやがって。オレの事、馬鹿にしてるのか!!」
彼が彼女の手を強くひくと、彼女は宙に浮いた。
「オ、オマエなんて……コウシテヤル!」
彼は身体を強く遊具にたたき付けた。
あまりに突然の事で、彼女は声もでなかった。
ただ、公園には、身体が割れる、バリッという音のみ響き続けた。
−−−翌日。
公園には、バラバラになった微笑むマネキンと。
近くのデパートから引取にきた警備員が。
木陰でひっそりと口づけを交わしていた。