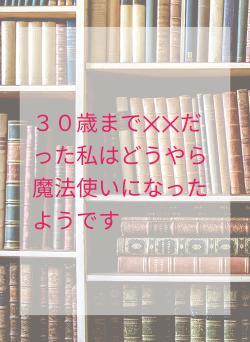朝日が眩しくて光平は目を細めた。
室内はムッとした血の匂いが充満していて、床は血の海と化していた。
目玉を繰り抜かれ、内臓も繰り抜かれた二人分の死体が転がっている中、光平は朝日の心地よさを全身で感じていた。
朝がくることがこれほど気持ちがいいと感じたことは久しぶりの経験だった。
朝になればあいつらにイジメられる。
朝になれば叔父と叔母に暴力を振るわれる。
朝なんて来なければいいのに。
そんな毎日を送っていた光平にとって、朝は強敵ともいえるものだった。
「気持ちがいい」
光平はガラスの入っていない窓へと近づいて呟く。
朝日をもっと全身に浴びたいと思い、仮面に手をかけた。
そして仮面をはがそうとしたその瞬間、ズキンッとひどい痛みが顔を襲っていた。
「っ!?」
光平は顔をしかめ、仮面から手を離す。
今のはなんだ?
いぶかしげな表情を浮かべ、再び仮面に手をかける。
ズキンッ!
まただ。
仮面をぬごうとすると痛みが走る。
それはまるで自分の本来の顔を引き剥がそうとする痛みなのだ。
室内はムッとした血の匂いが充満していて、床は血の海と化していた。
目玉を繰り抜かれ、内臓も繰り抜かれた二人分の死体が転がっている中、光平は朝日の心地よさを全身で感じていた。
朝がくることがこれほど気持ちがいいと感じたことは久しぶりの経験だった。
朝になればあいつらにイジメられる。
朝になれば叔父と叔母に暴力を振るわれる。
朝なんて来なければいいのに。
そんな毎日を送っていた光平にとって、朝は強敵ともいえるものだった。
「気持ちがいい」
光平はガラスの入っていない窓へと近づいて呟く。
朝日をもっと全身に浴びたいと思い、仮面に手をかけた。
そして仮面をはがそうとしたその瞬間、ズキンッとひどい痛みが顔を襲っていた。
「っ!?」
光平は顔をしかめ、仮面から手を離す。
今のはなんだ?
いぶかしげな表情を浮かべ、再び仮面に手をかける。
ズキンッ!
まただ。
仮面をぬごうとすると痛みが走る。
それはまるで自分の本来の顔を引き剥がそうとする痛みなのだ。