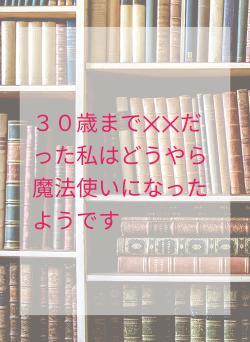その家は更に10分ほど歩いた場所にあった。
二階建ての一軒やで小さな庭もある。
しかし庭は草木が生え放題で手入れがされていない。
その上なんだか妙なにおいがその家から漂ってきていた。
鼻のきく猫田さんは険しい表情を浮かべて家を睨みつけている。
「ここですけど、どうしましょう」
蔦の絡まった玄関先に立ち尽くす怜美。
ここは今までの家とは全く違った雰囲気で、人間を寄せ付けない感じがする。
怜美はいますぐにでも立ち去ってしまいたい気持ちにおそわれた。
「行ってもらえませんか? なんだか嫌な予感がします」
猫田さんにそういわれたらここで立ち去るわけにはいかなくなってしまう。
怜美は勇気を出して玄関チャイムを押した。
中からチャイムの音が聞こえてくる。
しかし、いつまで待ってみても人が出てくる気配はなかった。
留守なのかもしれない。
もう一度チャイムを鳴らしてみたとき、中から犬のほえる声が聞こえてきた。
猫田さんが緊張した様子を見せる。
次に聞こえてきたのは猫がなにかを威嚇しているような声だった。
二階建ての一軒やで小さな庭もある。
しかし庭は草木が生え放題で手入れがされていない。
その上なんだか妙なにおいがその家から漂ってきていた。
鼻のきく猫田さんは険しい表情を浮かべて家を睨みつけている。
「ここですけど、どうしましょう」
蔦の絡まった玄関先に立ち尽くす怜美。
ここは今までの家とは全く違った雰囲気で、人間を寄せ付けない感じがする。
怜美はいますぐにでも立ち去ってしまいたい気持ちにおそわれた。
「行ってもらえませんか? なんだか嫌な予感がします」
猫田さんにそういわれたらここで立ち去るわけにはいかなくなってしまう。
怜美は勇気を出して玄関チャイムを押した。
中からチャイムの音が聞こえてくる。
しかし、いつまで待ってみても人が出てくる気配はなかった。
留守なのかもしれない。
もう一度チャイムを鳴らしてみたとき、中から犬のほえる声が聞こえてきた。
猫田さんが緊張した様子を見せる。
次に聞こえてきたのは猫がなにかを威嚇しているような声だった。