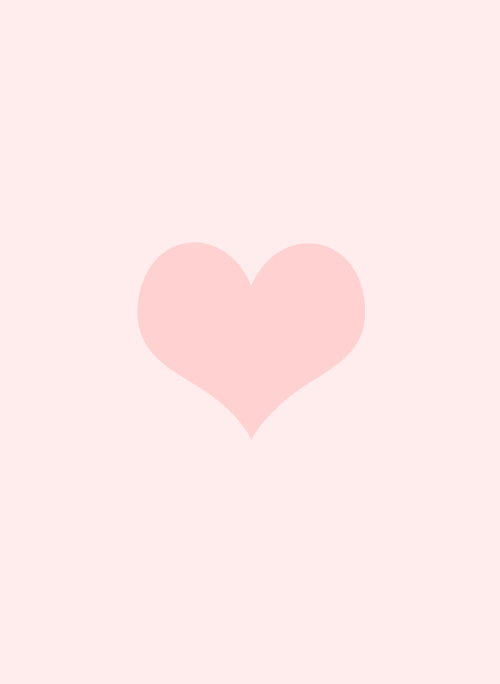*
突き抜けるような青空の下で男達の怒号が響き渡っていた。
ここが本当に三年前まで自分が暮らしていた、元フィールド辺境伯領とは思えない。
ここが戦場になるなんて……。
戦場に響く怒号に混じり悲鳴やうめき声、それにすすり泣く声が聞こえてくる。沢山の人々の感情が渦を巻き目眩を起こしそうだ。セリカは重症度の重い者を運び入れているテントの中で聖女の力を使っていた。
オウガの指示で負傷者全員を治していくのではなく、傷のひどい重症の者のみを治すこととなった。それはセリカの体を気遣ってのことだったが、回りも特に口出しをすることはなかった。
聖女の力を使わない代わりにセリカは積極的に、軽傷から中傷度の怪我人の手当を進んで行った。服が汚れるのを垣間見ず、血の付いた包帯やガーゼを交換する聖女の姿に騎士達は涙した。
「聖女様ありがとうございます」
「聖女様……何とお優しい」
騎士達がセリカに向かって感謝の気持ちを述べるが、セリカはそれを微笑むだけで返した。
「おい、誰だよ。聖女は傲慢でワガママで男を侍らせる最低女だとか言ってたやつ」
優しく微笑む聖女に皆の気持ちが一つに纏まっていく。
この戦、絶対に勝つと。
それから二週間が過ぎた。毎日の様に繰り返される戦。戦場も、テント内も血の匂いが充満しているが、鼻が慣れてしまったのか気にならなくなっていた。
慣れって怖いわね。
騎士の腕に巻かれた包帯を交換しながら、そんなことを思う。
日が落ち前線で戦っていた騎士達が帰ってきた。その中にオウガの姿もあった。
セリカはオウガに向かって走り出し、彼が生きていることを確認するため強く強く抱きしめる。始めこそ、強く抱き合う二人に騎士たちは驚き、冷やかしたりもしていたが、それは毎日の光景となっていた。
今ではこの光景を見ないことには体が休まらないと、騎士たちは思っていた。夕日に輝く二人は、戦場にいるというのに、一つの絵画のように美しい。騎士達は思った。この二人を守るためにも負けられない。二人には幸せになってもらいたいと。