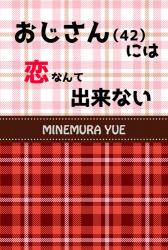それからミラルカは屋敷の仕事をしながらなるべく少女について面倒を見た。
少女は最初こそミラルカを信用していないようかったが、話すうちに少しずつ打ち解けるようになっていった。
怯える癖は抜けないものの、それでもなんとか仲良くなろうと努力する姿勢が窺える。元々優しい少女なのだろう。
肺炎も治り怪我も大分良くなった頃、ミラルカは少女の部屋に一輪のバラを持って来た。屋敷の庭で育てた赤い薔薇だ。
「綺麗でしょう? 今お庭で咲いているんです」
少女はバラを見たことがないのか。物珍しそうに見つめた。
バラは希少な花だ。育てているのは貴族ぐらいではないだろうか。そう考えると、少女が目にしたことがなくても不思議ではない。
「バラをご存知ないのですか?」
少女は頷いた。
「それなら、一度お庭に出てみますか? 今が一番綺麗な時ですから」
少女はまた頷いた。どうやらバラに興味を持ってくれたようだ。
ミラルカは少女に元気を取り戻してもらおうとあれこれ考えていた。庭に連れ出すのも作戦のうちの一つだ。
だが、庭に行くにあたって少女にある説明をしなけければならなかった。庭には屋敷に仕えている庭師がいる。
少女が庭に行くなら庭師を隠しておけばいいのだが、少女が人に対して失ってしまったもの────信頼を取り戻させるためには、やはりもう一度人と関わる必要があるだろうと考えた。
時期尚早かもしれないが、ミラルカは庭師の話をすることにした。
「庭師に、私と同じ村の出身のファビオという男の子がいるんです。歳は……あなたと同じくらいです」
突然庭師の話を始めたミラルカに少女はきょとんとした表情を向けた。
ここでファビオがどういう人物かをじっくり話してはおかなければならない。ファビオは悪い人間ではないし、会って話せばきっと仲良くなれると思った。
だが少女の人間不信は相当なものだろう。今でこそこうしてまともに顔を向けてくれるようになったが、屋敷に来た最初の頃は怯えて逃げ回る有様だった。
少女と喋ったことがあるのは現時点ではミラルカだけだ。屋敷の従者達はほぼ男で、少女を怖がらせてしまうかもしれない。いかにファビオがいい子であろうと、初対面の人間をそう簡単に信用はしてくれないだろう。
「植物が好きな子なんです。このバラも、ファビオが育てたんですよ」
ミラルカがそう言うと少女は興味ありげに頷いた。
「ファビオなら、あなたとも仲良くなれると思います。どうでしょう、会ってみませんか?」
そう誘うと、少女の表情に途端暗い影が差す。やはり今は無理なのだろうか。
「ファビオと会わなくてもバラは見れますからご安心ください。でも今のままでしたら私以外の人と話せないままでしょう? ずっとこのままでいいのですか?」
少女は俯いた。悩んでいるようだった。
「無理には勧めません。ただ、ファビオは優しい子ですから、安心して会えると思ったんです。ごめんなさいね」
『すこしだけなら』
少女が紙にペンを走らせた。グネグネした文字を見て、ミラルカはつい嬉しくなった。
「いいのですか?」
『ミラルカさんもいてくれますか?』
「もちろんです。よかった! あなたもきっと気に入ると思います。早速ファビオに伝えましょう」
少女は最初こそミラルカを信用していないようかったが、話すうちに少しずつ打ち解けるようになっていった。
怯える癖は抜けないものの、それでもなんとか仲良くなろうと努力する姿勢が窺える。元々優しい少女なのだろう。
肺炎も治り怪我も大分良くなった頃、ミラルカは少女の部屋に一輪のバラを持って来た。屋敷の庭で育てた赤い薔薇だ。
「綺麗でしょう? 今お庭で咲いているんです」
少女はバラを見たことがないのか。物珍しそうに見つめた。
バラは希少な花だ。育てているのは貴族ぐらいではないだろうか。そう考えると、少女が目にしたことがなくても不思議ではない。
「バラをご存知ないのですか?」
少女は頷いた。
「それなら、一度お庭に出てみますか? 今が一番綺麗な時ですから」
少女はまた頷いた。どうやらバラに興味を持ってくれたようだ。
ミラルカは少女に元気を取り戻してもらおうとあれこれ考えていた。庭に連れ出すのも作戦のうちの一つだ。
だが、庭に行くにあたって少女にある説明をしなけければならなかった。庭には屋敷に仕えている庭師がいる。
少女が庭に行くなら庭師を隠しておけばいいのだが、少女が人に対して失ってしまったもの────信頼を取り戻させるためには、やはりもう一度人と関わる必要があるだろうと考えた。
時期尚早かもしれないが、ミラルカは庭師の話をすることにした。
「庭師に、私と同じ村の出身のファビオという男の子がいるんです。歳は……あなたと同じくらいです」
突然庭師の話を始めたミラルカに少女はきょとんとした表情を向けた。
ここでファビオがどういう人物かをじっくり話してはおかなければならない。ファビオは悪い人間ではないし、会って話せばきっと仲良くなれると思った。
だが少女の人間不信は相当なものだろう。今でこそこうしてまともに顔を向けてくれるようになったが、屋敷に来た最初の頃は怯えて逃げ回る有様だった。
少女と喋ったことがあるのは現時点ではミラルカだけだ。屋敷の従者達はほぼ男で、少女を怖がらせてしまうかもしれない。いかにファビオがいい子であろうと、初対面の人間をそう簡単に信用はしてくれないだろう。
「植物が好きな子なんです。このバラも、ファビオが育てたんですよ」
ミラルカがそう言うと少女は興味ありげに頷いた。
「ファビオなら、あなたとも仲良くなれると思います。どうでしょう、会ってみませんか?」
そう誘うと、少女の表情に途端暗い影が差す。やはり今は無理なのだろうか。
「ファビオと会わなくてもバラは見れますからご安心ください。でも今のままでしたら私以外の人と話せないままでしょう? ずっとこのままでいいのですか?」
少女は俯いた。悩んでいるようだった。
「無理には勧めません。ただ、ファビオは優しい子ですから、安心して会えると思ったんです。ごめんなさいね」
『すこしだけなら』
少女が紙にペンを走らせた。グネグネした文字を見て、ミラルカはつい嬉しくなった。
「いいのですか?」
『ミラルカさんもいてくれますか?』
「もちろんです。よかった! あなたもきっと気に入ると思います。早速ファビオに伝えましょう」