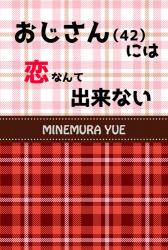ここ最近、エルは一日のほとんどをミラルカと過ごすようになった。それだけエルはミラルカに心を開いていた。
いつものように筆談をしながら、エルはバラ園をくれたネリウスのことを尋ねてみることにした
『ごしゅじんさまはなにをしているひとなのですか』
「ネリウス様は侯爵なんですよ」
エルは首を傾げた。
「貴族は分かりますか?」
エルはまた首を横に振った。
監禁生活から抜け出したとはいえ、エルは世情に疎い。部屋から一歩も出ていないし新聞もまともに見ていないので、ミラルカが言う「侯爵」がなんなのか理解できなかった。
「偉い人の身分のことをそう呼ぶのです。まぁ、うちのご主人様は呑気なものだから家でゴロゴロしてますけどね」
『どうしてわたしをここにおいておくのですか? もうけがはなおりました』
「行くあてはあるの?」
そう返されて、エルはどう答えたらいいか分からず俯いた。
好意を申し訳なく思いながらも、いざ放り出されればどうすればいいかわからない。行くあてなどなかった。
「ないならいていいのですよ。いくらでも。お金も何もいりませんから」
『めいわくじゃないですか?』
「ここを出て行きたいですか?」
そんな気持ちはひとつもなかった。ここにいれば安全だ。あの男に見つかることはない。衣食住が保証されていて、皆優しい。
だけど迷惑をかける訳にもいかない。いつまでもこの生活が続くとは思えなかった。
「出来れば……エル様にはここに留まって欲しいのです」
ミラルカは逆に申し訳なさそうに言った。
「このお屋敷は広いですが、住んでいるのはネリウス様と私達従者だけです。ネリウス様は人付き合いが苦手で、あまり外に出たがらなくて……。エル様が来てくれたおかげで、屋敷が明るくなりました。だから出来れば、このままいて欲しいと思っています」
有難い申し出だ。だが、ほとんど部屋に引きこもってミラルカとファビオ以外に会ったこともない自分が屋敷を明るくしていることには同意しかねた。
屋敷の中はほとんど歩いたことがないが、庭を見たときに外観を見た。ベッカー侯爵邸はとても大きい。だがミラルカ曰く、この屋敷で働く従者は少ないのだという。
それは現当主、ネリウスが人付き合いが悪い無口な性格をしていることが理由らしいが、静かな屋敷だ。人が一人増えたぐらいで賑やかになるだろうか。
「エル様は綺麗な緑色の瞳をしてらっしゃるのですね。前から思っていたのですが、大奥様によく似ていらっしゃいます」
大奥様というのは、ネリウス侯爵の母親のことだろうか。
『わたしがですか?』、とエルは自分を指差した。
「ええ。大奥様も緑色の瞳をしていたのです。とてもお綺麗な方で、気品があって────エル様ももっと綺麗な格好をすればきっと似合うと思います。そうだわ、ドレスを着てみませんか?」
『わたしにはにあいません』
「あら、そんなことございませんよ。今度ルーシーを呼びましょう」
エルが首を傾げると、ミラルカが説明してくれた。
「街で仕立て屋をしている女性です。お喋りが上手で素敵な洋服を作るのですよ。きっとエル様とも仲良くなれます」
『でもわたししゃべれません』
「大丈夫ですよ。そんなこと気にする人じゃありませんから。私エル様に会わせたい人が沢山いるのです。一度には無理だけど、一人ずつ、ね?」
ミラルカは嬉々として喋った。ルーシーやネリウスの話、過去にあったこと。まるで自分のことのように語った。
ミラルカは二人と仲良くしてほしいと思っているのだろう。エルはそう思った。
いつものように筆談をしながら、エルはバラ園をくれたネリウスのことを尋ねてみることにした
『ごしゅじんさまはなにをしているひとなのですか』
「ネリウス様は侯爵なんですよ」
エルは首を傾げた。
「貴族は分かりますか?」
エルはまた首を横に振った。
監禁生活から抜け出したとはいえ、エルは世情に疎い。部屋から一歩も出ていないし新聞もまともに見ていないので、ミラルカが言う「侯爵」がなんなのか理解できなかった。
「偉い人の身分のことをそう呼ぶのです。まぁ、うちのご主人様は呑気なものだから家でゴロゴロしてますけどね」
『どうしてわたしをここにおいておくのですか? もうけがはなおりました』
「行くあてはあるの?」
そう返されて、エルはどう答えたらいいか分からず俯いた。
好意を申し訳なく思いながらも、いざ放り出されればどうすればいいかわからない。行くあてなどなかった。
「ないならいていいのですよ。いくらでも。お金も何もいりませんから」
『めいわくじゃないですか?』
「ここを出て行きたいですか?」
そんな気持ちはひとつもなかった。ここにいれば安全だ。あの男に見つかることはない。衣食住が保証されていて、皆優しい。
だけど迷惑をかける訳にもいかない。いつまでもこの生活が続くとは思えなかった。
「出来れば……エル様にはここに留まって欲しいのです」
ミラルカは逆に申し訳なさそうに言った。
「このお屋敷は広いですが、住んでいるのはネリウス様と私達従者だけです。ネリウス様は人付き合いが苦手で、あまり外に出たがらなくて……。エル様が来てくれたおかげで、屋敷が明るくなりました。だから出来れば、このままいて欲しいと思っています」
有難い申し出だ。だが、ほとんど部屋に引きこもってミラルカとファビオ以外に会ったこともない自分が屋敷を明るくしていることには同意しかねた。
屋敷の中はほとんど歩いたことがないが、庭を見たときに外観を見た。ベッカー侯爵邸はとても大きい。だがミラルカ曰く、この屋敷で働く従者は少ないのだという。
それは現当主、ネリウスが人付き合いが悪い無口な性格をしていることが理由らしいが、静かな屋敷だ。人が一人増えたぐらいで賑やかになるだろうか。
「エル様は綺麗な緑色の瞳をしてらっしゃるのですね。前から思っていたのですが、大奥様によく似ていらっしゃいます」
大奥様というのは、ネリウス侯爵の母親のことだろうか。
『わたしがですか?』、とエルは自分を指差した。
「ええ。大奥様も緑色の瞳をしていたのです。とてもお綺麗な方で、気品があって────エル様ももっと綺麗な格好をすればきっと似合うと思います。そうだわ、ドレスを着てみませんか?」
『わたしにはにあいません』
「あら、そんなことございませんよ。今度ルーシーを呼びましょう」
エルが首を傾げると、ミラルカが説明してくれた。
「街で仕立て屋をしている女性です。お喋りが上手で素敵な洋服を作るのですよ。きっとエル様とも仲良くなれます」
『でもわたししゃべれません』
「大丈夫ですよ。そんなこと気にする人じゃありませんから。私エル様に会わせたい人が沢山いるのです。一度には無理だけど、一人ずつ、ね?」
ミラルカは嬉々として喋った。ルーシーやネリウスの話、過去にあったこと。まるで自分のことのように語った。
ミラルカは二人と仲良くしてほしいと思っているのだろう。エルはそう思った。