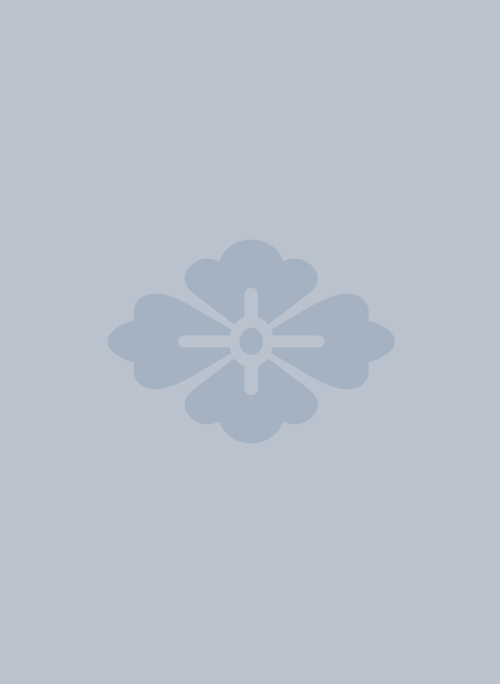Keith
青色が眩しい。
雲の隙間から日差しが漏れ、そこだけキラキラと輝いていた。
ほんの一筋だけだ。
たったそれだけなのに、キースは目を細めた。
これ以上光を受けないように――否、これはもう癖なのだろう。
太陽でも、空でも――ひとでも。
あまりの輝きは、未だ慣れないでいる。
例えばロイ、例えばジェイダ。
彼らのような明るすぎる光は苛々するし、皆も承知の通り不快だった。
ほの暗さが心地いいのだ。
明かりに恵まれなくても、守りたいものは守ってきた。それの何が悪いというのか。
あの兄弟、特にアルバートは父である先王を毛嫌いしていた。
確かに、人情味に溢れた王様だったとは言えないかもしれない。
それでもトスティータがここまで攻められもせず、どこかを攻めずにいられたのは王の力が強かったからだ。
厳しい状態が続く中、内紛も反乱もなかった。
(憐れなひとだ、貴方も)
アルバートの事情もあれば、親子喧嘩に興味もない。
それでも、不憫だったと思うのだ。
それは同情だろうか。
仲が良かった訳でも、優しくされた記憶があるのでもないが。
あのひとと長くいたのは、息子よりも補佐官である自分だったのだ。