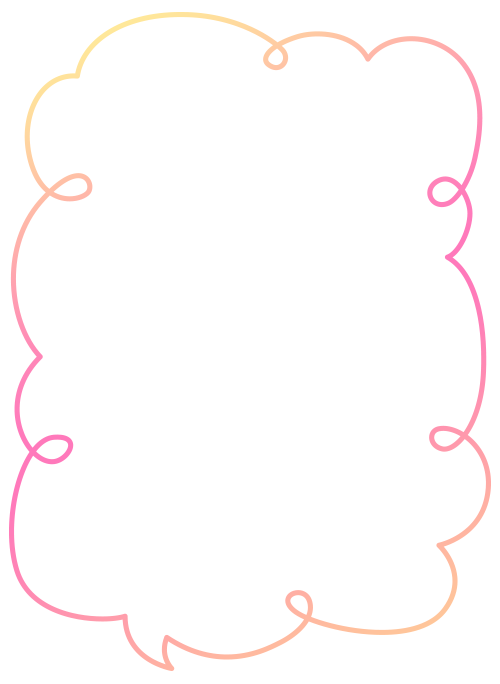それは、ダンスパーティ本番の一週間前。
金持ちの考えは未だよくわからないが、恋人のいる男性はパーティのたびにドレスを贈る風習があるらしい。
それなのに、私の婚約者は言った。
「ねぇ、ねぇ、リイナ! 僕はどんな服を着たらいいの?」
「……はい?」
「どんな格好したら、リイナをより綺麗に引き立ててあげられるかな? 僕じゃあよくわからないから、一緒に選んでもらえないかな?」
半裸の王子は、日に日に目に毒となっていた。まだ多少脇腹に肉が乗っているものの、肩幅も広く、服を着た状態ではよくわからなかったが、胸板も暑い。お風呂上がりのいい匂いがする状態で保湿クリームを塗ってあげている最中、ズイッと両手を握られ懇願されては、
「あ、はい」
と、頷く以外の選択肢などなく――――
そして衣装を選びに、てっきり衣装部屋に行くものかと思いきや、
「王子、こちらの布ですが――――」
通された部屋は、応接間だった。そこにはこれでもかと巻かれた布が置かれており、スケッチブック片手に行商人ぽい人が説明や質問を重ねていた。
その話を優雅にお茶を飲みながら聞くエドの袖を私はそっと引っ張る。
「エ、エド……衣装を選ぶんじゃないんですか?」
「うん? だから選んでるじゃない」
さも当然とばかりに私に笑みを向けてから、行商人に「その隣の生地を見せて」と指示を出すエド。
「さすがはエドワード王子、お目が高い。こちらの生地は希少価値の高い――――」
「まぁ、そういうのはいいんだけどさ。少しリイナに当ててみてもらってもいいかな?」
「も、もちろんでございます!」
そして、なぜだか私に充てがわれたのは、濃紺の布だった。一見地味な色かと思いきや、よく見るとキラキラと細かい刺繍が入っており、素人目からしても高そうなのが一目瞭然。
それを見たエドが「うん」と顎を撫でる。
「すごく似合っているよ、リイナ。すごく大人っぽく見える。今回は晩餐会も兼ねているし、肩を出したドレスをこれで作ったら、きっと僕は昇天しちゃうんじゃないかな」