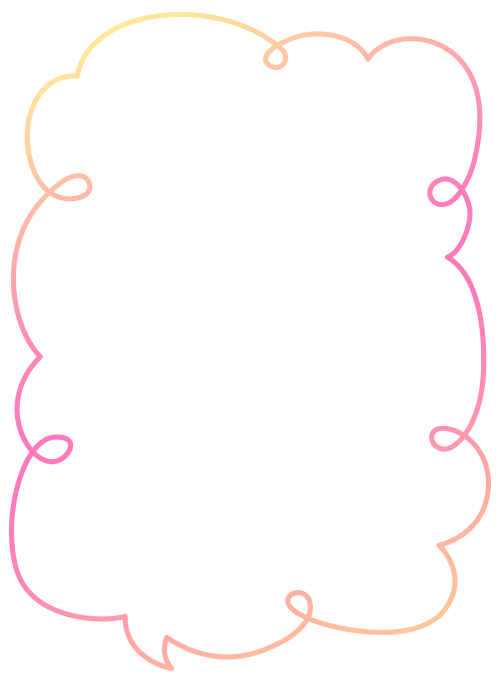◆ ◆ ◆
俺の添い寝役が、椅子に座って舟を漕いでいる。
そんなに首をかくんかくんさせて、辛くはないんだろうか……。思わずそんな心配をしてしまうほど、見事な爆睡ぶりだ。
まだ一日の付き合いだが、どうも仕事のやる気はあるらしい。そもそも添い寝役なんて馬鹿みたいな仕事にやる気を見出してどうするんだか……。
「馬鹿みたいは、失礼か……」
飴をガリッと噛み締める。
正直『添い寝役』なんて仕事を、こんなウブな女がどうして生真面目に引き受けたのか。あのクソ陛下になんて唆されたのか。
色々不思議で、色々ぶん殴りたくて仕方ない。
それでも陛下に『主命』と言い渡されてしまえば。
俺に、拒否権なんてあるわけがない。
そんな自分に対する感情を処理することなんて、もう慣れてしまった。
とりあえず、自分の添い寝役に風邪でも引かれたら面倒だ。
ベッドに運んでやろうと、近付いた時だった。
「う……」
谷間が見えた。
お、俺は悪くない。椅子に座っている彼女に近付こうとすれば、上から見下ろす形になるのが必然。ただでさえ、彼女はなぜか露出度の高いネグリジェを着ているのだ。どうせアルベール陛下の差し金だろうが……クソ。あいつのニヤけている顔が目に浮かぶ。
というか、この服装からしておかしいだろうが。断れ。拒否しろ。そして自分を大切にしろ。そんな格好しているから、こっちも最初『そういうつもり』なのかとカマかけたんだろうが。その気がないなら、もっと隠せ。自衛しろ。
手足はちゃんと食べているのか心配になるくらい細いくせに、胸だけふくよかなのは実にけしからん。もっと栄養を回すべき場所があるだろうが。
「はあ……」
気を取り直すため、俺は一度机へと戻る。そして飴の入った瓶から、まとめて取り出した。それを煽るように口に放り込む。
ガリガリガリ。ガリガリガリ。
「ふんっ」
口の中に広がる圧倒的な甘さに心を落ち着かせて。
俺は今一度、挑む。
見るな。余計な場所を見るな見るな見るな見るな。
カミュ=バルバートン。二十四歳。アルベール騎士団所属第七班小隊長。
胸元がなんだ。レースに透けている白い太ももがなんだ。半開きの口元がなんだ。
俺は彼女が膝に抱えた猫ごと、彼女を横抱きに持ち上げた。
クソ。やっぱり軽い。それにあたたかさはなんだ。特に右手。膝裏を支えている方。こんな細いのに、こんな柔らかいとはどういうことだ⁉
……こんなことなら、少しでも陛下の女遊びに付き合っておくんだった。
「クソッ」
俺はとうとう実際に舌打ちした時だ。
彼女の腹の上で器用に丸くなっていた猫の金色の目が、俺を見ていた。
ジーッと。ジーッと。
もふもふしている黒猫の瞳が、まっすぐ俺を見据えている。
「……なんだ。何か文句あるのか?」
彼女を起こさないよう、小声で尋ねる。すると猫は何も言わず、すんっと目を閉じてしまった。
……狸寝入りだよな。猫のくせに、生意気な。
せっかくこれからは少し高いミルクに切り替えようと思っていたのに、やめだ。やめ。
俺はガリガリと飴を奥歯ですり潰し、飲み込んだ。そしてベッドに、彼女を下ろす。
去年の俺の誕生日に『友達からの祝い』とアルベール陛下が無理やり贈ってきたベッド。品質は一級。シーツは定期的に取り替えているが、俺は一度もこのベッドに横たわったことがない――昨日までは。
まぁ、ほぼ新品同様だ。女性に使わせたところで問題ないだろう。
彼女には他の部屋を使うように言ったが、他のベッドはそれこそ十年前から新調していない。寝心地はこのベッドが一番のはずだ。それに掃除だって追いついて――
「あー……確か、余計なことをしてくれたんだったな」
思い返すのは、荒れ果てた屋敷の姿。
使用人なしで一人で暮らしている以上、どうしても手の行き届かない所がある。だが、それでも両親の忘れ形見と、俺なりに手入れを心がけていたのだが。
……まぁ、添い寝役という訳わからん仕事の代わりに、彼女にメイド仕事を頼むわけにはいかないらしい。
「しかしまぁ、どうして陛下もこんな子を俺に寄越したんだが……」
俺がこの姉弟について聞いたのは『過労が祟って倒れられては困る』『だから俺から最適の人物を送ってやる』『そしていい加減まともに寝ろ』それだけ。
「寝ろと言われてもな……」
俺はもう十年近く、ベッドで寝たことがない。
寝ようとすると、嫌でも思い出してしまうから。
あの悪夢を見るくらいなら、たまに机でうたた寝するくらいで十分だ。
現に、もう時刻はかなり遅くなっているが、まるで眠くはない。
ただ少しだけ、頭がぼんやりするくらいだ。
「掃除でもしてくるか」
一人暮らしが長いと、自然と独り言が増えてしまった。
書類仕事も一段落したし、今のうちに屋敷を掃除しようとドアノブに手をかけると「みゃあ」と猫が鳴く。
「なんだ?」
俺が振り返った時には、彼女が連れている猫がベッドから飛び降りて、俺の足元に擦り寄っていた。
「腹でも減ったのか?」
「みゃ!」
「……安いミルクしかやらんぞ」
俺が告げると、猫は媚びるように俺の靴をペロペロと舐めてきて。
「汚いからやめろ」
俺はそっと足を退け、嘆息を吐く。
明日から、もう一段階だけ高いミルクを買うようにしよう。
そのことを頼むのは、やはりあの弟の方がいいだろう。
俺の気苦労も知らないで、敵意むき出しの目で見てきた弟。
明日から俺の母校に通うということだが、やはり勉強など俺も見てやるべきなのだろうか。実技は……あんな殺気ある目が出来るやつだ。少なくとも素人ではないはずだ。
しかし、問題はすやすや寝ている彼女だ。放っておいたら、また屋敷を荒らされてしまうのだろうか。
この屋敷の惨状も、様子を見るからに掃除で失敗したという所か。どう失敗したらこんなことになるのかわからないが。
だけど、やる気はあるらしい。やる気だけはあるらしい。
「まったく……面倒なやつらを寄越しやがって」
陛下の権限で寄越された人材を勝手に追い出すわけにもいかないだろ。
俺は猫も部屋を出たのを確認してから、そっと扉を閉める。
月明かりに照らされた彼女は、気持ち良さそうにすやすや眠っていた。