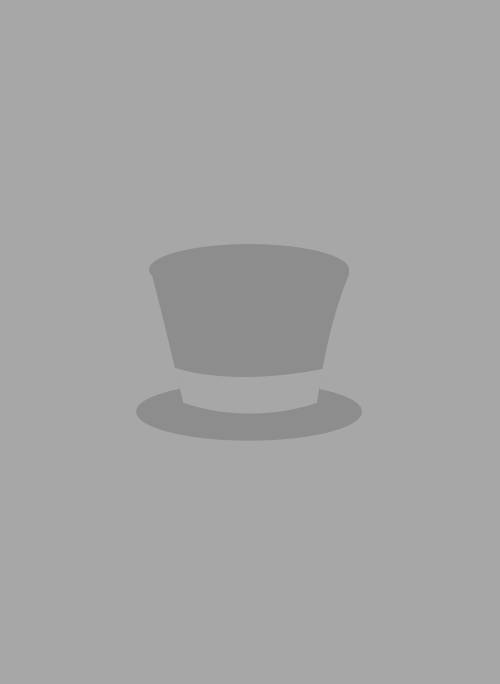赤錆に覆われたアパートの外階段に足音が響く。
(此処に来てくれたら嬉しいな)
俺は呑気なことを考えていた。
叔父が経営する、イワキ探偵事務所に最近客足が遠退いているからだった。
(迷子の子猫ちゃん捜しでもいいから……)
そう思いつつドアを見つめた。
――ガラガラドッシャーン!!
突然大きな音がした。
(しまった。バケツを出しっぱなしだった!)
俺は慌ててイワキ探偵事務所から飛び出した。
上熊谷駅の横の道路から国道へ向かう途中に、それまで覆い隠された川がいきなり現れる。
其処が熊谷空襲で被害が甚大だった星川だ。
焼夷弾などによる空爆で多くの建物が延焼する中、暑さ凌ぎに小さな川に大勢詰めかけた。
其処で百名近くの命が奪われたのだ。
終戦直前の悲劇として語り継がれている史実だ。
ゆったりと流れる川は今では憩いの通りとなっている。
まるであの日が嘘のように……
その通りを熊谷駅方面に向かう途中を曲がり、一本中に入った道。
古い木造アパートの二階。
東側の窓に手作り看板。
イワキ探偵事務所はあった。
間取りは六畳と四畳半、一坪キッチンとトイレ付きバスユニット。
出来た当初はきっと斬新だったんだろう。
でも今は修繕もされないまままま放っておかれている。
目立たない場所だからかなと、俺は密かに思っていた。
通路側に開くドア。
靴置き場のみある玄関。
その横に広がる、洋間が事務所だ。
其処で探偵としての仕事を請け負っていた。
俺は中学生の頃から、学校が早目に終わった日は良く叔父の探偵事務所に遊びに来ていた。
両親は共働きて鍵っ子だったからだ。
だから見よう見まねで迷子の子猫捜しなどを手伝っていたのだ。
給料なんて貰ったためしはないけど、俺はアルバイトだと思っていた。
勿論誰にも言っていない。だって、子供を雇っているとか噂を立てられたくなかったんだ。
弟に子供を預かってもらっている。きっと母はそう思っているに違いないからだ。
でも本当の理由は弟が心配だったからだ。
叔父は新婚時代に奥さんを殺されていたのだ。
叔父は警視庁に勤めていた。
だけど住む家が見つからずに、仮住まいしていたのだった。
何れは社宅に住みつもりだったからだ。
まさか其処にずっと住むことになろうなんて思いもしなかったはずなのだ。
俺はアパートの奥に住んでいると聞いた、水村麗子(みずむられいこ)さんのドアを叩いた。
きっとあの足音を確かめるようとしたのだろう。
俺がドアを開けるまで目を瞑っていた気がした。
でも其処にいたのは、渡部和也(わたなべかずや)さんではなかった……
階段から聞こえたのは和也さんの足音のだったからか、水村さんは一瞬怯んだ。
そしてその後身構えた。
「スイマセン。イワキ探偵事務所の者ですが」
俺は不審者でも見るような水村さんの態度を見抜き、不安を払拭するように言った。
初対面だったからだ。
和也さんはイワキ探偵事務所に居た。
俺が無造作に階段の横に置いたバケツ。
それに和也さんが足を突っ込んでしまったからだった。
履いていた革靴とスーツを汚れてしまったので、着替えを頼まれたのだった。
「すいません。スエットの下有りますか? それとスニーカー……」
申し訳なさそうな俺に対して水村さんは微笑んだ。
ドキンとした。
(まさか!? 恋じゃないよね? だったら辞めておけ、俺にはみずほがいるのだから……)
女好きと言う訳ではないけど、俺はドキドキしながらスエットなどを受け取った。
(下着!? そうかやはり恋人同士か?)
俺は少しがっかりしながらイワキ探偵事務所に戻った。
俺からそれらを受け取った和也さんは直ぐに着替えて水村さんの部屋へと向かった。
その時、写真が落ちた。
でも気付かずに和也さんは部屋に入って行った。
それを見て驚いた俺は慌てて隠した。
「瑞穂(みずほ)。今何を隠した?」
叔父の言葉にドキンとして、仕方なくそれを見せることにした。
「これは!?」
叔父も相当たまげたようで声が裏がえっていた。
其処に写っていたのが男女の営みだったからだ。
「女性は水村さんのようだな?」
叔父の言葉に頷いた。
「でも男性はさっきの人とは違うようだ」
「そうだよね。だって、これを誰が写したかってことだから」
「何れにしても、何故これを持っているかってことだ」
「水村さんが可哀想だ」
俺はさっき、和也さんを待っていた姿を思い出して胸を痛めた。
「瑞穂悪いけどドアの下の隙間から入れてきてくれないか?」
叔父の言葉を受けて、俺は慎重に対処することにした。
本当はそんなことはしたくない。
水村さんに災いが降りかかることが判っていたからだ。
だってきっと和也は水村さんにとって大切な人のはずだからだ。
『その子の事はコイツと良く相談するんだな』
写真を拾ったらしい和也さんはそう冷たく言い放っていた。
俺は探偵の癖で聞き耳を立てていたのだ。
何故そんな写真を和也さんが持っているのか?
それは恋人と別れるために和也さんが企てた陰謀かも知れない。
叔父の推測だけど、きっと上司か何かの娘と婚約がまとまったから邪魔になった麗子さんと別れる策略をしたようだ。
叔父の勘は良く当たるのだ。
三月前。
和也さんは泥酔した水村さんと帰って来た。
叔父はその姿を見て心配したそうだ。
でもそれだけは終わらなかった。
待たせていたタクシーにはもう一人いて、和也さんはその男性をアパートに運び込んだのだ。
『この後ろ姿はその時の男性に似ている。もしかしたら二人を……』
麗子さんの部屋に送り込まれたのは酩酊状態の男性だった。
どうやらその時に男女の関係を持たされてしまったらしい。
でも麗子さんは、全く知らなかったのだ。
だから……
和之さんの子供だと思い込んでいたのかも知れない。
だから待っていたんだ。
和也さんの足音があの階段から聞こえる日を……
その後、上村治樹(うえむらはるき)さんがイワキ探偵事務所を訪れた。
その上村さんこそ和也さんが持っていた、水村さんと写っていた男性だったのだ。
「何時麗子さんの部屋を訪れたのか解りませんが、どうやらその時に関係を持ってしまったらしいのです。でも麗子さんも私も、全く知らなかったのです」
「隠謀だな。これは」
俺はつい口を滑らせていた。
「だと思います。噂で、この辺りに刑事経験のある凄腕探偵がいると聞いたことがあります。もしかしたら?」
「あ、そうですよ」
俺は又口を滑らせた。
「あの日麗子さんは和也と飲んでいました。だから……和之の子供だと思い込んでいたのだと思います。さっき言われた隠謀かも知れません。調べていただけないでしょうか?」
「でも二人共かなり酔っていましたから……」
「もしかしたら見ていたのですか?」
「三ヶ月ほど前でした。泥酔した水村さんが和也さんにあの部屋に運ばれたのは事実です。その後で貴方も……。本当に覚えがないのですか?」
叔父の言葉に上村さんは頷いた。
「だとしたら、和也の言ったように私の子供なのかも知れない」
上村さんは頭を抱えた。
「上村さんでしたね。失礼ですが、貴方と和也さんの関係は?」
「同期入社で、良きライバルと言ったところです。もしかしたら私を蹴落とすつもりだったのかも知れません。上司のお嬢様との婚約が整いましたから……」
「汚ない人だな。水村さんが哀想だ。其処までして別れなくても……」
俺は又口を滑らせた。
「あっ、婚約が整ったのは私です。実はその写真は上司の家のポストの中にあったそうです」
「えっ!? 結婚が決まったのは上村さんでしたか?」
「だったら何の意味があるんだろ?」
高校生になったばかりの俺には、男女の問題なんて判るはずもなかったのだ。
みずほと言う恋人はいるにはいるけど、未だにキス止まりだった。
でもまだ高校生だからそれで充分だと思っていたのだ。
水村さんは確かに妊娠していた。
でもそれは間違い無く和也さんの子のはずだった。
「『あれは俺のじゃない。お前覚えてきないのか?』って和也は意外なことを言ったんです。上司に送られてきたあの写真を見せて確めた時に……」
「解りました。コイツが言ったように隠謀だったら許されない。出来るだけ調べてみます。で、その上司のお嬢様とは?」
「勿論破談です。きっとそれが狙いだったのでしょう」
「やはりそうなりましたか? コイツと二人であれこれ推察していました」
「ところで、この人は? まだ未成年のように見受けられますが?」
「あ、アルバイトですよ。こんなちっぽけな探偵事務所では給料なんて出せませんが……」
「そうでしたか。何か解りましたら又報告してみます。此方でも調べてみますのでよろしくお願い致します」
「はい。解りました。でもくれぐれも無理はなさらないでくださいね」
叔父は上村さんの依頼を引き受けた。
「叔父さんさっき『あ、アルバイトですよ。こんなちっぽけな探偵事務所では給料なんて出せませんが……』って言ってたけど」
「何だ瑞穂、給料が欲しいのか?」
「違うよ、そうじゃなくて……」
そう言ってはみたものの、俺は言葉に詰まって黙ってしまった。
「悪いな。何時か小遣いやるからな」
叔父はバツが悪そうに言った。
叔父の経営している探偵事務所があまり流行っていないことは解っていた。
それでも丁寧な仕事を評価してくれる人は大勢いる。
だから口コミが頼りだったのだ。
「そう言えば、もうすぐ蛍まつりだったな」
場の雰囲気を変えようとしたのか、叔父が突然口を開いた。
「うん、そうだよ。水質管理のために皆で頑張った甲斐があって、今年は多く飛ぶみたいだよ」
叔父に話を合わせるようにあれこれと考える内に、雑草取りや蛍の餌になるカワニナの育成などて頑張っていた子供の頃を思い出した。
だから毎年、この時期がくるとウキウキしてくるのだ。
今年もみずほと出掛けるつもりだ。
本当は男女関係の縺れなどの依頼より、動物捜しの方が嬉しかったりするのだ。
仕事の選り好みは出来ないと解ったはいるけど……
「なあ、瑞穂。アルバイトじゃなくて社員にならないか?」
「又その話? 仕事が忙しくなりそうだから?」
俺の問いに叔父は頷いた。
その手の話は叔父は良く言っていたから先手を打ったのだ。
「なあんだ。さっきの言葉はアルバイトじゃ物足りないってことじゃなかったのか?」
「えっ、そっちの話? 俺はてっきり……」
「高校辞めて手伝えってか?」
叔父は笑い出した。
「瑞穂の答えは決まっていたな」
「だって叔父さん『サッカーなんか辞めてずっと手伝ってくれ』って言うからだよ。俺はサッカー命なんだから」
そう、俺は中学時代はサッカー部のエースだった。
まだ高校の部活は始まったばかりだったけど、みずほのためにも頑張っていたのだ。
みずほは俺と同じ高校を選んでくれた。
本当はもっとレベルの高い学校に行ける実力があったのに……
だから俺は得意なサッカーでせめてもの恩返しをしようと思っていたのだ。
(此処に来てくれたら嬉しいな)
俺は呑気なことを考えていた。
叔父が経営する、イワキ探偵事務所に最近客足が遠退いているからだった。
(迷子の子猫ちゃん捜しでもいいから……)
そう思いつつドアを見つめた。
――ガラガラドッシャーン!!
突然大きな音がした。
(しまった。バケツを出しっぱなしだった!)
俺は慌ててイワキ探偵事務所から飛び出した。
上熊谷駅の横の道路から国道へ向かう途中に、それまで覆い隠された川がいきなり現れる。
其処が熊谷空襲で被害が甚大だった星川だ。
焼夷弾などによる空爆で多くの建物が延焼する中、暑さ凌ぎに小さな川に大勢詰めかけた。
其処で百名近くの命が奪われたのだ。
終戦直前の悲劇として語り継がれている史実だ。
ゆったりと流れる川は今では憩いの通りとなっている。
まるであの日が嘘のように……
その通りを熊谷駅方面に向かう途中を曲がり、一本中に入った道。
古い木造アパートの二階。
東側の窓に手作り看板。
イワキ探偵事務所はあった。
間取りは六畳と四畳半、一坪キッチンとトイレ付きバスユニット。
出来た当初はきっと斬新だったんだろう。
でも今は修繕もされないまままま放っておかれている。
目立たない場所だからかなと、俺は密かに思っていた。
通路側に開くドア。
靴置き場のみある玄関。
その横に広がる、洋間が事務所だ。
其処で探偵としての仕事を請け負っていた。
俺は中学生の頃から、学校が早目に終わった日は良く叔父の探偵事務所に遊びに来ていた。
両親は共働きて鍵っ子だったからだ。
だから見よう見まねで迷子の子猫捜しなどを手伝っていたのだ。
給料なんて貰ったためしはないけど、俺はアルバイトだと思っていた。
勿論誰にも言っていない。だって、子供を雇っているとか噂を立てられたくなかったんだ。
弟に子供を預かってもらっている。きっと母はそう思っているに違いないからだ。
でも本当の理由は弟が心配だったからだ。
叔父は新婚時代に奥さんを殺されていたのだ。
叔父は警視庁に勤めていた。
だけど住む家が見つからずに、仮住まいしていたのだった。
何れは社宅に住みつもりだったからだ。
まさか其処にずっと住むことになろうなんて思いもしなかったはずなのだ。
俺はアパートの奥に住んでいると聞いた、水村麗子(みずむられいこ)さんのドアを叩いた。
きっとあの足音を確かめるようとしたのだろう。
俺がドアを開けるまで目を瞑っていた気がした。
でも其処にいたのは、渡部和也(わたなべかずや)さんではなかった……
階段から聞こえたのは和也さんの足音のだったからか、水村さんは一瞬怯んだ。
そしてその後身構えた。
「スイマセン。イワキ探偵事務所の者ですが」
俺は不審者でも見るような水村さんの態度を見抜き、不安を払拭するように言った。
初対面だったからだ。
和也さんはイワキ探偵事務所に居た。
俺が無造作に階段の横に置いたバケツ。
それに和也さんが足を突っ込んでしまったからだった。
履いていた革靴とスーツを汚れてしまったので、着替えを頼まれたのだった。
「すいません。スエットの下有りますか? それとスニーカー……」
申し訳なさそうな俺に対して水村さんは微笑んだ。
ドキンとした。
(まさか!? 恋じゃないよね? だったら辞めておけ、俺にはみずほがいるのだから……)
女好きと言う訳ではないけど、俺はドキドキしながらスエットなどを受け取った。
(下着!? そうかやはり恋人同士か?)
俺は少しがっかりしながらイワキ探偵事務所に戻った。
俺からそれらを受け取った和也さんは直ぐに着替えて水村さんの部屋へと向かった。
その時、写真が落ちた。
でも気付かずに和也さんは部屋に入って行った。
それを見て驚いた俺は慌てて隠した。
「瑞穂(みずほ)。今何を隠した?」
叔父の言葉にドキンとして、仕方なくそれを見せることにした。
「これは!?」
叔父も相当たまげたようで声が裏がえっていた。
其処に写っていたのが男女の営みだったからだ。
「女性は水村さんのようだな?」
叔父の言葉に頷いた。
「でも男性はさっきの人とは違うようだ」
「そうだよね。だって、これを誰が写したかってことだから」
「何れにしても、何故これを持っているかってことだ」
「水村さんが可哀想だ」
俺はさっき、和也さんを待っていた姿を思い出して胸を痛めた。
「瑞穂悪いけどドアの下の隙間から入れてきてくれないか?」
叔父の言葉を受けて、俺は慎重に対処することにした。
本当はそんなことはしたくない。
水村さんに災いが降りかかることが判っていたからだ。
だってきっと和也は水村さんにとって大切な人のはずだからだ。
『その子の事はコイツと良く相談するんだな』
写真を拾ったらしい和也さんはそう冷たく言い放っていた。
俺は探偵の癖で聞き耳を立てていたのだ。
何故そんな写真を和也さんが持っているのか?
それは恋人と別れるために和也さんが企てた陰謀かも知れない。
叔父の推測だけど、きっと上司か何かの娘と婚約がまとまったから邪魔になった麗子さんと別れる策略をしたようだ。
叔父の勘は良く当たるのだ。
三月前。
和也さんは泥酔した水村さんと帰って来た。
叔父はその姿を見て心配したそうだ。
でもそれだけは終わらなかった。
待たせていたタクシーにはもう一人いて、和也さんはその男性をアパートに運び込んだのだ。
『この後ろ姿はその時の男性に似ている。もしかしたら二人を……』
麗子さんの部屋に送り込まれたのは酩酊状態の男性だった。
どうやらその時に男女の関係を持たされてしまったらしい。
でも麗子さんは、全く知らなかったのだ。
だから……
和之さんの子供だと思い込んでいたのかも知れない。
だから待っていたんだ。
和也さんの足音があの階段から聞こえる日を……
その後、上村治樹(うえむらはるき)さんがイワキ探偵事務所を訪れた。
その上村さんこそ和也さんが持っていた、水村さんと写っていた男性だったのだ。
「何時麗子さんの部屋を訪れたのか解りませんが、どうやらその時に関係を持ってしまったらしいのです。でも麗子さんも私も、全く知らなかったのです」
「隠謀だな。これは」
俺はつい口を滑らせていた。
「だと思います。噂で、この辺りに刑事経験のある凄腕探偵がいると聞いたことがあります。もしかしたら?」
「あ、そうですよ」
俺は又口を滑らせた。
「あの日麗子さんは和也と飲んでいました。だから……和之の子供だと思い込んでいたのだと思います。さっき言われた隠謀かも知れません。調べていただけないでしょうか?」
「でも二人共かなり酔っていましたから……」
「もしかしたら見ていたのですか?」
「三ヶ月ほど前でした。泥酔した水村さんが和也さんにあの部屋に運ばれたのは事実です。その後で貴方も……。本当に覚えがないのですか?」
叔父の言葉に上村さんは頷いた。
「だとしたら、和也の言ったように私の子供なのかも知れない」
上村さんは頭を抱えた。
「上村さんでしたね。失礼ですが、貴方と和也さんの関係は?」
「同期入社で、良きライバルと言ったところです。もしかしたら私を蹴落とすつもりだったのかも知れません。上司のお嬢様との婚約が整いましたから……」
「汚ない人だな。水村さんが哀想だ。其処までして別れなくても……」
俺は又口を滑らせた。
「あっ、婚約が整ったのは私です。実はその写真は上司の家のポストの中にあったそうです」
「えっ!? 結婚が決まったのは上村さんでしたか?」
「だったら何の意味があるんだろ?」
高校生になったばかりの俺には、男女の問題なんて判るはずもなかったのだ。
みずほと言う恋人はいるにはいるけど、未だにキス止まりだった。
でもまだ高校生だからそれで充分だと思っていたのだ。
水村さんは確かに妊娠していた。
でもそれは間違い無く和也さんの子のはずだった。
「『あれは俺のじゃない。お前覚えてきないのか?』って和也は意外なことを言ったんです。上司に送られてきたあの写真を見せて確めた時に……」
「解りました。コイツが言ったように隠謀だったら許されない。出来るだけ調べてみます。で、その上司のお嬢様とは?」
「勿論破談です。きっとそれが狙いだったのでしょう」
「やはりそうなりましたか? コイツと二人であれこれ推察していました」
「ところで、この人は? まだ未成年のように見受けられますが?」
「あ、アルバイトですよ。こんなちっぽけな探偵事務所では給料なんて出せませんが……」
「そうでしたか。何か解りましたら又報告してみます。此方でも調べてみますのでよろしくお願い致します」
「はい。解りました。でもくれぐれも無理はなさらないでくださいね」
叔父は上村さんの依頼を引き受けた。
「叔父さんさっき『あ、アルバイトですよ。こんなちっぽけな探偵事務所では給料なんて出せませんが……』って言ってたけど」
「何だ瑞穂、給料が欲しいのか?」
「違うよ、そうじゃなくて……」
そう言ってはみたものの、俺は言葉に詰まって黙ってしまった。
「悪いな。何時か小遣いやるからな」
叔父はバツが悪そうに言った。
叔父の経営している探偵事務所があまり流行っていないことは解っていた。
それでも丁寧な仕事を評価してくれる人は大勢いる。
だから口コミが頼りだったのだ。
「そう言えば、もうすぐ蛍まつりだったな」
場の雰囲気を変えようとしたのか、叔父が突然口を開いた。
「うん、そうだよ。水質管理のために皆で頑張った甲斐があって、今年は多く飛ぶみたいだよ」
叔父に話を合わせるようにあれこれと考える内に、雑草取りや蛍の餌になるカワニナの育成などて頑張っていた子供の頃を思い出した。
だから毎年、この時期がくるとウキウキしてくるのだ。
今年もみずほと出掛けるつもりだ。
本当は男女関係の縺れなどの依頼より、動物捜しの方が嬉しかったりするのだ。
仕事の選り好みは出来ないと解ったはいるけど……
「なあ、瑞穂。アルバイトじゃなくて社員にならないか?」
「又その話? 仕事が忙しくなりそうだから?」
俺の問いに叔父は頷いた。
その手の話は叔父は良く言っていたから先手を打ったのだ。
「なあんだ。さっきの言葉はアルバイトじゃ物足りないってことじゃなかったのか?」
「えっ、そっちの話? 俺はてっきり……」
「高校辞めて手伝えってか?」
叔父は笑い出した。
「瑞穂の答えは決まっていたな」
「だって叔父さん『サッカーなんか辞めてずっと手伝ってくれ』って言うからだよ。俺はサッカー命なんだから」
そう、俺は中学時代はサッカー部のエースだった。
まだ高校の部活は始まったばかりだったけど、みずほのためにも頑張っていたのだ。
みずほは俺と同じ高校を選んでくれた。
本当はもっとレベルの高い学校に行ける実力があったのに……
だから俺は得意なサッカーでせめてもの恩返しをしようと思っていたのだ。