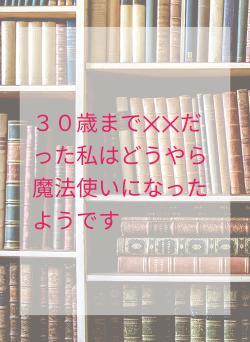それから梓と厚彦は学校へ戻ってきていた。
すぐに家に帰ってもよかったのだけれど、まだ日が高いし、他にやれることがないか探しに来たのだ。
「まだいるの?」
梓はまた大きなマスクをつけて、厚彦へそう聞いた。
厚彦は屋上へ視線を向けて頷いた。
「いる」
女性の顔を思い出すと、また胸が痛んだ。
カナさんはまだ苦しみ続けている。
そんなこと、女性には言えるわけがなかった。
「もう少し話が聞けないか、行ってみよう」
「そうだね」
グラウンドではまだ部活にいそしんでいる生徒たちが沢山いた。
そんな中、梓は立ち止まる。
すぐに家に帰ってもよかったのだけれど、まだ日が高いし、他にやれることがないか探しに来たのだ。
「まだいるの?」
梓はまた大きなマスクをつけて、厚彦へそう聞いた。
厚彦は屋上へ視線を向けて頷いた。
「いる」
女性の顔を思い出すと、また胸が痛んだ。
カナさんはまだ苦しみ続けている。
そんなこと、女性には言えるわけがなかった。
「もう少し話が聞けないか、行ってみよう」
「そうだね」
グラウンドではまだ部活にいそしんでいる生徒たちが沢山いた。
そんな中、梓は立ち止まる。