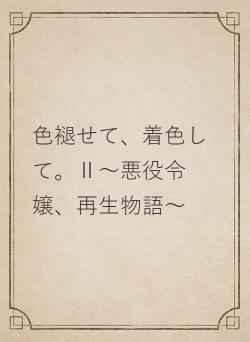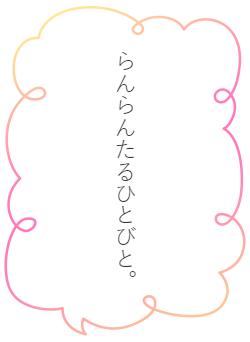蘭の元に嫁いで一ヵ月が経とうとしている。
少しずつだけど、ここでの生活に慣れてきたのか。
緊張感がゆるゆると解放されつつある。
相変わらず、蘭は忙しそうで。
たまに顔を見合わせても「おぅ」とか「俺は忙しいんだ」とだけ言って去ってしまう。
普段、アイツがどんな仕事をしているのかわからない。
貴族の仕事って何だろう?
まぁ、蘭と毎日顔を見合わせても息が詰まるだけだろうから。
アイツのことなんかどうだっていい。
むしろ会えなくてラッキーと思うようになった。
この頃、渚くんと仲良くなり始めた。
渚くんは、この屋敷の中で一番口が堅くないほうだと知った。
他の人達は「それは、秘密」だの「答えられない」っていうけど。
渚くんは、ギリギリまで答えてくれる。
でも、やっぱり答えられない内容に関しては、
「ごめん。答えられないんだ」と申し訳なさそうに言う。
私の兄がアズマだという話になった時。
私は思わず「渚くんは兄弟いるの?」と訊いてしまった。
渚くんは物凄く驚いた表情をして。
「ごめん、答えられないんだ」とさみしそうに言った。
この屋敷で働く人達はすべてが謎に包まれている。
「サクラさん、今日も手紙って届いてない?」
朝、食堂でパンケーキを小さく刻んで口に入れながら。
後ろに立っているサクラさんに尋ねてみた。
フェイスベールをつけながらの食事は、見る人がビックリするけど。
私は慣れっこなので、違和感などない。
とにかく、小さくナイフで刻んで口にほおりこんで。モグモグ。
初めの頃はサクラさんに「食べにくいんじゃない!?」と突っ込まれたけど。
今は何も言ってこない。
「手紙? 届いてないわよ。届いていたら、ちゃんと渡すわよ」
「…そうですよね」
私は小さくため息をついた。
流石に、オカシイなと思い始めた。
私のご両親。
昔から、私のことなんか構ってもくれなかったけど。
没落した今。大丈夫なのかと心配になる。
蘭は幾らかお金を渡しているはずだけど。
あの人達のことだから、すぐに使い果たしているのではないかと思う。
だから、そろそろお金の催促でもしに来るのではないかと考えたのだ。
あの人達が昔から豪遊して。
家の財産を使い果たして。
生活費を稼ぐために、お兄様は恥を忍んで蘭の護衛係となった。
と、言っても。お兄様が働けども、そのお金は両親が使い果たしてしまう…。
悪循環だった。
お兄様が行方不明になったのは、一年前だった。
蘭を助けようとした際、大怪我を追って死にかけて。
それから、病院で治療を受けていたけど。
ある日、病院から抜け出したのだ。
それっきりだ。
私はお兄様に会っていない。
「カレンさん、考え事? ずっと上の空だけど」
ライト先生に指摘されて。
私は「あ、すいません」とペンを置いた。
授業内容がちっとも身に入らない。
お昼ご飯を食べ終えた後の心地よい眠気が響いて。
更に心配事は時間が経つにつれて、どんどんと膨張していく。
「あの、ライト先生」
「うん?」
先生は教科書に目を通している。
「うちの…実家のほうへ最近行くことはありませんでしたか?」
「実家?」
ライト先生の眉毛がピクッと吊り上がった。
「いえ…。両親と連絡が取れないんです」
嫁いでから4通ほど手紙を出してみたけど。
一切、返事はない。
「どうして、僕に訊くの?」
怒った表情をするので。
私は「ひえー」と心の中で絶叫をする。
ライト先生にとっては、余計な話だったらしい。
でも、訊くとしたら、ライト先生しかいないのだ。
「いえ…知らないなら、大丈夫です。ごめんなさい」
目をそらして、ノートに単語をガリガリと書く。
そんな私を黙ってライト先生が見つめている。
「カレンさんの実家は町外れにあるだろ? 僕はそっちのほうには、あまり行かないから」
(私の家って町外れにあるんですか?)
そもそも、私は実家がどの位置にあるのか、知らない。
そうか、町外れなのかとライト先生の言葉に初めて納得する。
「ま、でも。カレンさんの実家あたりって確か先週…」
そこまで言いかけてライト先生は口をつぐんだ。
「先週…なんです?」
急に恐ろしくなってライト先生を見る。
「いや。何でもないよ」
先生は静かに笑った。
その時、どうしようもないくらい。
嫌な予感がした。
これは、本当に予感っていう感覚なんだけど。
「あれ、カレンさん。実家に帰ればいいだけの話じゃないの?」
一言。
ライト先生の言葉は。
私を硬直させた。
先生はわかって言っているのだろうか。
「蘭くんにお願いしてさ、たまには実家に帰ってみたら? アズマくんのことだって気になってるんだろ?」
「…お兄様の情報があるんですか?」
この一年、お兄様の目撃情報はゼロだった。
何か含みを持つライト先生の言葉に、心臓がドキドキする。
「いや。僕は知らないけどさ。もしかしたら、情報が来ているかもしれないんじゃないのかなって」
「……たとえ」
少し意地悪そうに言うライト先生をまっすぐと見る。
「たとえ、蘭に相談したとしても。私は両親に会いにいけるかわからないので。もう、嫁いだ身ですから」
はっきりと言うしかなかった。
私は、此処から出ることなんぞ許されない。
ライト先生は黙り込んだ。
私が言い返さないとでも思っていたのだろうか。
先生はどこか、そういうところがある。
たまに意地悪なことを言う。
「じゃあさ、あの男の子に訊いてみれば?」
先生は頬杖をついて私を見た。
「あの運転手の男の子。クリスって言ったっけ?」
「へ? クリスさん?」
意外な人物の名に驚く。
「彼、何度か町で見かけたことあるよ。買い出しでも行ってるんじゃないのかな。もしかしたら、知ってるかもよ」
「…クリスさんが」
確かに運転手の仕事もしているから。
知っているのかもしれない。
少しずつだけど、ここでの生活に慣れてきたのか。
緊張感がゆるゆると解放されつつある。
相変わらず、蘭は忙しそうで。
たまに顔を見合わせても「おぅ」とか「俺は忙しいんだ」とだけ言って去ってしまう。
普段、アイツがどんな仕事をしているのかわからない。
貴族の仕事って何だろう?
まぁ、蘭と毎日顔を見合わせても息が詰まるだけだろうから。
アイツのことなんかどうだっていい。
むしろ会えなくてラッキーと思うようになった。
この頃、渚くんと仲良くなり始めた。
渚くんは、この屋敷の中で一番口が堅くないほうだと知った。
他の人達は「それは、秘密」だの「答えられない」っていうけど。
渚くんは、ギリギリまで答えてくれる。
でも、やっぱり答えられない内容に関しては、
「ごめん。答えられないんだ」と申し訳なさそうに言う。
私の兄がアズマだという話になった時。
私は思わず「渚くんは兄弟いるの?」と訊いてしまった。
渚くんは物凄く驚いた表情をして。
「ごめん、答えられないんだ」とさみしそうに言った。
この屋敷で働く人達はすべてが謎に包まれている。
「サクラさん、今日も手紙って届いてない?」
朝、食堂でパンケーキを小さく刻んで口に入れながら。
後ろに立っているサクラさんに尋ねてみた。
フェイスベールをつけながらの食事は、見る人がビックリするけど。
私は慣れっこなので、違和感などない。
とにかく、小さくナイフで刻んで口にほおりこんで。モグモグ。
初めの頃はサクラさんに「食べにくいんじゃない!?」と突っ込まれたけど。
今は何も言ってこない。
「手紙? 届いてないわよ。届いていたら、ちゃんと渡すわよ」
「…そうですよね」
私は小さくため息をついた。
流石に、オカシイなと思い始めた。
私のご両親。
昔から、私のことなんか構ってもくれなかったけど。
没落した今。大丈夫なのかと心配になる。
蘭は幾らかお金を渡しているはずだけど。
あの人達のことだから、すぐに使い果たしているのではないかと思う。
だから、そろそろお金の催促でもしに来るのではないかと考えたのだ。
あの人達が昔から豪遊して。
家の財産を使い果たして。
生活費を稼ぐために、お兄様は恥を忍んで蘭の護衛係となった。
と、言っても。お兄様が働けども、そのお金は両親が使い果たしてしまう…。
悪循環だった。
お兄様が行方不明になったのは、一年前だった。
蘭を助けようとした際、大怪我を追って死にかけて。
それから、病院で治療を受けていたけど。
ある日、病院から抜け出したのだ。
それっきりだ。
私はお兄様に会っていない。
「カレンさん、考え事? ずっと上の空だけど」
ライト先生に指摘されて。
私は「あ、すいません」とペンを置いた。
授業内容がちっとも身に入らない。
お昼ご飯を食べ終えた後の心地よい眠気が響いて。
更に心配事は時間が経つにつれて、どんどんと膨張していく。
「あの、ライト先生」
「うん?」
先生は教科書に目を通している。
「うちの…実家のほうへ最近行くことはありませんでしたか?」
「実家?」
ライト先生の眉毛がピクッと吊り上がった。
「いえ…。両親と連絡が取れないんです」
嫁いでから4通ほど手紙を出してみたけど。
一切、返事はない。
「どうして、僕に訊くの?」
怒った表情をするので。
私は「ひえー」と心の中で絶叫をする。
ライト先生にとっては、余計な話だったらしい。
でも、訊くとしたら、ライト先生しかいないのだ。
「いえ…知らないなら、大丈夫です。ごめんなさい」
目をそらして、ノートに単語をガリガリと書く。
そんな私を黙ってライト先生が見つめている。
「カレンさんの実家は町外れにあるだろ? 僕はそっちのほうには、あまり行かないから」
(私の家って町外れにあるんですか?)
そもそも、私は実家がどの位置にあるのか、知らない。
そうか、町外れなのかとライト先生の言葉に初めて納得する。
「ま、でも。カレンさんの実家あたりって確か先週…」
そこまで言いかけてライト先生は口をつぐんだ。
「先週…なんです?」
急に恐ろしくなってライト先生を見る。
「いや。何でもないよ」
先生は静かに笑った。
その時、どうしようもないくらい。
嫌な予感がした。
これは、本当に予感っていう感覚なんだけど。
「あれ、カレンさん。実家に帰ればいいだけの話じゃないの?」
一言。
ライト先生の言葉は。
私を硬直させた。
先生はわかって言っているのだろうか。
「蘭くんにお願いしてさ、たまには実家に帰ってみたら? アズマくんのことだって気になってるんだろ?」
「…お兄様の情報があるんですか?」
この一年、お兄様の目撃情報はゼロだった。
何か含みを持つライト先生の言葉に、心臓がドキドキする。
「いや。僕は知らないけどさ。もしかしたら、情報が来ているかもしれないんじゃないのかなって」
「……たとえ」
少し意地悪そうに言うライト先生をまっすぐと見る。
「たとえ、蘭に相談したとしても。私は両親に会いにいけるかわからないので。もう、嫁いだ身ですから」
はっきりと言うしかなかった。
私は、此処から出ることなんぞ許されない。
ライト先生は黙り込んだ。
私が言い返さないとでも思っていたのだろうか。
先生はどこか、そういうところがある。
たまに意地悪なことを言う。
「じゃあさ、あの男の子に訊いてみれば?」
先生は頬杖をついて私を見た。
「あの運転手の男の子。クリスって言ったっけ?」
「へ? クリスさん?」
意外な人物の名に驚く。
「彼、何度か町で見かけたことあるよ。買い出しでも行ってるんじゃないのかな。もしかしたら、知ってるかもよ」
「…クリスさんが」
確かに運転手の仕事もしているから。
知っているのかもしれない。