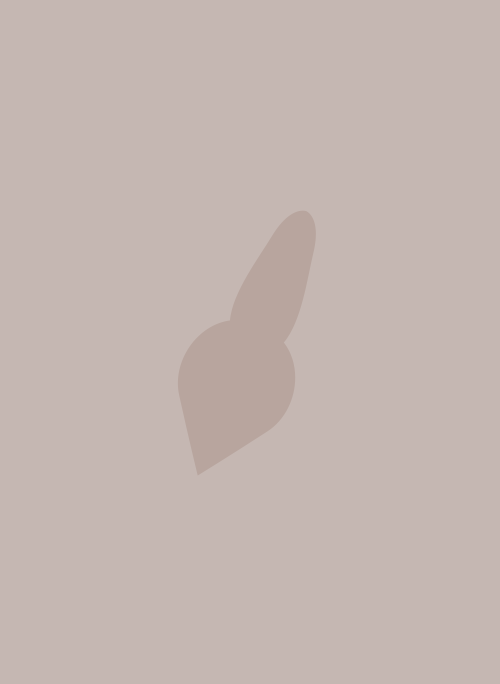「五十一」
5日前から、毎晩、老人の幽霊があらわれて、わたしの右目を指でほじくる。
幽霊だから、感触は無いのだが、あまり気持ちのいいものではない。
7日目。
目玉が少し動いた。
「五十二」
夜中に自動販売機でジュースを買ったとき、後ろから、
「みーつけた」
と声をかけられた。
ふりむくと、顔を真っ白に塗りつぶした女が、大きなホッチキスを手に持って笑っていた。
「五十三」
夕方の公園のベンチで、顔を真っ白に塗りつぶした女が、スクラップブックをめくっているのを見た。
それには、小さくて平べったい、やけにリアルな人形が、1ページごとに、ホッチキスで両手両足を止められていた。
「五十四」
家の前にあるマンホールの蓋が開いていて、そこから何かが這いずりながら進んだ黒い跡が、家のほうまでのびていた。
十年前に、赤ちゃんを捨てたマンホールから・・・。
「五十五」
捨てた女から、スマホに留守電が入っていた。
「会いたい」「会いたい」「会って」「会えよ」
無視して電源を切ろうとしたとき、
いきなり液晶にヒビがはいって、
画面いっぱいにあの女の目が
「五十六」
「死体が生き返る呪文」
というものを、スマフォのネット検索で見つけた。
試しに小声で唱えてみたが、ここは昼間のにぎやかなファミレスだ。何も起きやしない。
そのとき、おなかの中で何かが動いた。
・・・・・・さっき食べたハンバーグの肉も、死体になるのだろうか?
「五十七」
「ねえ、手をにぎって」
夜中、恋人から、そんな電話があった。
おれは青ざめた。
恋人は、飛行機の墜落事故で死んだはずだった。
「ねえ、手をにぎってよお」
ふと窓を見ると、黒焦げのちぎれた手首が、窓ガラスをギイギイとひっかいていた。
「五十八」
夕方、息子が小さな箱を持って帰ってきた。
箱の中には、きれいな女の顔を持つ、コオロギのようなものが一匹、いた。
「これ飼うから。絶対に飼うから」
顔を赤らめながら、息子は強く言った。
「五十九」
夜中、宿題をしている途中にふと振り向くと、
壁に黒い涙を流して泣き叫ぶ女の絵があった。
・・・・・・こんなもの、飾った覚えがない。
「六十」
校門のところにある桜の木の幹から、男の首が生えている。恋人を長い間、待っているうちに、桜とひとつになってしまったらしい。先生が子どもの頃から、その首はあったという。
「六十一」
わたしの部屋の天井に、首吊り用のヒモがつけられた。
両親に抗議したが、父も母も、
「あなたのためなんだから」
と言って聞かない。
意味が、わからない。
「六十二」
「明日から、赤くなってください」
ホームルームで、先生が、意味のわからないことを言った。
翌日、クラスメイトのみんなの皮膚が赤色になっていた。
ひとりだけ肌色なわたしを、全員が無言でにらんできた。
「六十三」
今日、
「お姉ちゃん狂ってるよ」
って弟に言われた。
ムカツクーッ!(●`ε´●)
怒ったらおなかがすいたので、わたしは電池を食べた。
「六十四」
「痛いの痛いのとんできたあ」
すれちがった顔を真っ白に塗りつぶした女が、そうつぶやいた瞬間、
おれの舌が突然ぶちんとちぎれて落ちた。
女は、うずくまったおれを笑って見下ろし、
「ね?あ、またとんできたあ」
「六十五」
「痛いの痛いの飛んでいけ」
そう言って、顔を真っ黒に塗りつぶした男のひとが、
舌を噛みちぎって自殺した恋人を生き返らせてくれました。
とても感謝しています。
「六十六」
朝、弟の両目がなくなっていた。初めから何も無かったかのように。
ふと窓の外を見ると、全身にたくさんの目をつけた何かが、こっちを見て笑っていた。
「六十七」
卒業アルバムの集合写真に首のない生徒が三人いた。
「六十八」
昼間、街で買い物をしてる途中、セールスマン風の男に声をかけられた。
「あのう、噛んでいいっすか?」
「・・・・・・え?」
「噛んでいいっすか?」
すごい力で腕をつかまれた。
「六十九」
iPodで音楽を聴いているとき、突然イヤフォンから笑い声が聞こえてきた。
「あははははは死ねた死ねた死ねた死ねた死ねた死ねた死ねたもう死ねたいじめられなく死ねた死ねたあははははは」
声がやんだ。
ここは学校の屋上だった。
「七十」
引っ越したばかりのアパートで、夜3時くらいになると、突然、人を殴る音が聞こえてくる。
誰もいないし、何もない。
なのに、ただ人を殴る音だけが聞こえてくる。
「七十一」
最近、爪がのびるのが早い。毎日切っても、すぐのびてくる。
ある日の夜、激痛を感じて目覚めると、
長くのびた爪が、狙ったかのように、わたしの喉に刺さっていた。
「七十二」
好きなアーティストのCDを聴いていたら、歌の中に、「ちぎった」という知らない声がまじっていた。
聴きなおすと、声がどんどん増えていて
「ちぎった」「ちぎりとってやったよ」「耳を」「耳も」「唇も」「これから」「おまえのも」
「七十三」
昔、捨てた女が、自殺したと聞いた。
なんとなく、彼女にもらった恋文を読み返してみた。
文面の、「愛してる」という文字が、手紙から飛び出してきて、おれの両目を切り裂いた。
「七十四」
幼い頃から、顔がブサイクという理由でいじめられていた。
なので、わたしは「顔削ぎ屋」へ行った。
顔の肉を、削いでもらった。
次の日から、わたしは「かわいそうな子」として扱われるようになり、誰にもいじめられなくなった。
顔削ぎ屋さん、ありがとう。
「七十五」
アパートのドアに、「助けて」という文字が彫られていた。
次の日、部屋の壁に、「助けてよ」という文字が彫られていた。
その日の夜、わたしの舌に「助けろよ」という文字が彫られて液が
「七十六」
深夜、コンビニに寄った帰り、突然後ろから肩をつかまれ、無理やり振り向かされた。
顎が地面につくくらい、顔の長い女が、おれの肩をつかんだまま、
「愛されるのと、潰されるの、どっちがいい?」
と聞きながら、目を見つめてきた。
「七十七」
友人が公園で、口のまわりを血まみれにしながら泣いているのを見た。
どうしたの?と聞くと、友人はしゃべれないらしく、スマフォに文字を打ちこんで、わたしに見せた。
「知らないひとに連れてかれて歯をぜんぶ釘ととりかえられた」
どぷっと友人の口から血の塊があふれて地面に落ちた。
「七十八」
正月、おばあちゃん家の和室で、
人間の唇に虫の足が生えた形のものが、もぞもぞと動くのを見た。
おばあちゃんに聞くと、あれは何もしなければ無害だからと言って笑った。
わたしはあれにゴミをぶつけていた。
「七十九」
コインランドリーの忘れ物置き場に、
ちぎれた赤ん坊の足首が置かれていた。
顔を真っ黒に塗りつぶした男が入ってきて、無言でそれを持ち帰った。
「八十」
深夜ふと目覚めると金縛り天井に何か黒いものがぶらさがっていて体が動かない黒いものは何かぎざぎざしたものをこちらにのばしてきて
「八十一」
授業中、前の席の男子の机の中に、老人の顔をしたトカゲのようなものがいるのが見えた。
あまり仲の良くない男子生徒だったので、わたしは何も話さなかった。
3日後、その男子が、何かに鼻を喰いちぎられたという噂を聞いた。
「八十二」
母親を紹介すると言われ、わたしは緊張しながら彼の家に行った。
彼に案内されて、わたしは広い部屋に通された。
そこには、三メートルくらいの身長の、乾いた血で汚れた裸の老婆がいた。
彼が言った。
「母さん、エサを連れてきたよ」
「八十三」
朝、学校へ行く途中、道路に這いつくばって、ひいひいひいと笑うおじさんを見た。
怖くなって、遠回りした。
夕方、帰宅途中、同じ場所でそのおじさんを見た。
車に踏まれたのか、ふとももがタイヤの跡の形に潰れていた。
ひいひいひいと笑っていた。
「八十四」
知らない町を歩いていると、深夜なのにあいている床屋があった。中をのぞくと、薄暗い照明の下で、床に落ちた髪の毛を食べるおじいさんがいた。
「八十五」
三年前に、わたしがストーカー行為をして、殺して埋めたはずのアイドルの死体が、ネットで売られていた。
「八十六」
変な虫に噛まれた。
最初は、少し腫れたくらいですんだのだけど、3日たってから、目玉がどんどんふくらんできて・・・・・・
「八十七」
夜、カラオケの帰りに、暗い道路を歩いているとき、友達が何気なく言った。
「わたし、暗いところって結構好きだな。静かで、なんか落ち着くし」
するとその友達は暗闇にひきずりこまれた。
「八十八」
町中で、出版社に勤めている友人に出会った。手に包丁を持っていた。
何やってるのと聞くと、友人は真顔で答えた。
「営業よ。作家が死ねば、追悼フェアとかで、本が売れるの」
目が血走っていた。
「八十九」
日曜日の昼、街中で、泣きじゃくる5歳くらいの男の子が、母親に引きずられながら歩いていくのを見た。
歯医者に連れて行くところかな、なんて思っていたら、男の子が、
「ギロチンはいやだ」
とかすれた声でつぶやくのが聞こえた。
「九十」
朝、登校すると、靴箱の中に、ひよこの首が入っていた。
動いていた。
気味が悪くなって、あわててゴミ箱に捨てた。
翌朝、登校して、靴箱を開けると、中からニワトリの首が飛び出してきて、クチバシでわたしの目をえぐった。
「九十一」
朝起きるとなんだか体が重い。
外に出る。すれちがうひとが目を丸くする。
ふと自分の影を見る。
人間の影じゃない。
「九十二」
居間のテレビに、男が猫の首をねじ切る映像が映っていた。
気持ち悪い番組だな、と思い、テレビを消そうとして電源ボタンを押した。
・・・・・・消えない。
男がこっちを見た。
「九十三」
深夜、強いかゆみを感じて目を覚ました。
全身にびっしりと黒い毛を生やした何かがベッドのそばにいて、ぼくの体をなでまわしていた。
「・・・・・・ぼうや」
十年前に出ていった、母の声がした。
「九十四」
学校の帰り、友達と親の悪口を話して盛りあがっているとき、
「消そうか?」
と後ろから声をかけられた。
異様に背の高い、細くて色白の男が、私達を見下ろしていた。
「消そう」
と言って、男は去っていった。
「九十五」
夜中に彼と電話で話していたときのこと。
「ねえ、誕生日プレゼント、何がほしい?」
と聞くと、
「生爪」
という返事が聞こえてきた。
思わず絶句していると、また、
「生爪」
と聞こえた。
「ちょっとふざけないでよ」
「生爪」
「・・・・・・・・・・・・」
彼の声じゃない。
「九十六」
この前、遊びで友達の耳をちぎったらさ、なんかすごく怒られてさ、びっくりしたよ。おれ、子供の頃から母ちゃんと一緒にひとの耳をちぎって遊んでたからさ。てっきり普通のことだと思ってたんだけど。そうやってちぎった耳を、母ちゃんにホッチキスで背中にくっつけてもらったなあ。
ほら。
「九十七」
今年、15歳になる友人が、過労死した。
彼女はいつも、
「追いかけてくる、追いかけてくる」
と何かに怯えながら、朝も夜も町中をずっと走り回っていた。
葬式の帰り、足音が聞こえて、ふりむいた。
わたしは走り出した。
彼女が、追いかけてきた。
「九十八」
よる、あたらしいおかあさんが、おとうさんのめだまをりょうほう、すいとってのみこんでいるのをみた。
「九十九」
友達の部屋で、うごめく肉片を見た。
すぐにこの世のものではないとわかったが、怖がらせるのも悪いと思ったので、黙っていた。
翌日、友達が肉片になった。
「百」
「ここどこ?ねえ、ここどこなのよお?」
夕方、ギャル風のファッションに身を包んだ女子高生が、泣きそうな声をあげながら、うろうろとさまよっていた。
その少女の両目玉が、ありえない動きでぐるぐると激しく回っていた。
「よく見えないよお。ここどこお?」
古い墓場だった。