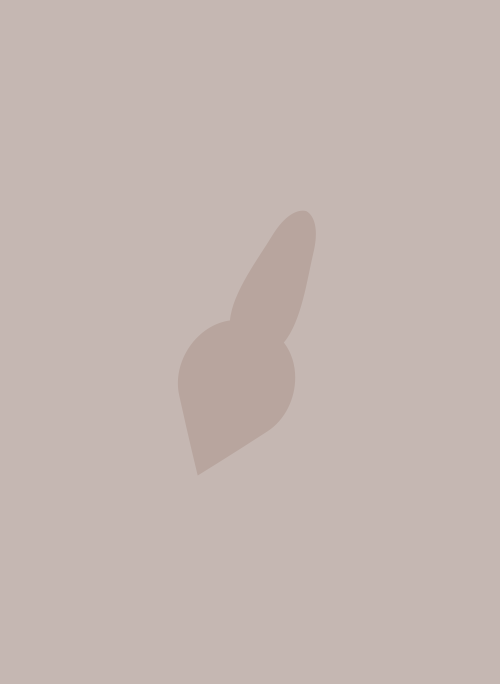「一」
まだ暗い朝4時に、ゴミを出しに行った。
ゴミ捨て場には、半透明のゴミ袋がひとつ置かれていた。
中に詰められていた、お婆さんと目があった。
「二」
次の授業は国語だ。
教科書とノートを取り出すために、少年は机の中に手を入れた。
机の中で、何かが手をつかんだ。
「三」
足を切られている途中だった。
顔を真っ黒に塗りつぶした男が、ノコギリでぼくの足を切っている。
ぼくはもう死んでいるのに何すんだよ。
「四」
夜の山道をわたしは歩いていた。
すぐ後ろに、いる、とわかっていた。
振り向いてはいけない、ともわかっていた。
振り向いてしまった彼の、ちぎれた手首が、わたしの指を握りしめていた。
「五」
「ぼく、百足(ムカデ)になっちゃうよう」
と夜中、急に息子が泣きだした。
息子の足が、一本増えていた
「六」
夜中の神社で、必死に祈っている男のひとを見た。
「もう、ゴキブリは殺しません。もう、ゴキブリは殺しません。だから、・・・・・・もどして
そのひとの両腕は、ゴキブリの足になっていた。
「七」
街でデートをしている途中、彼が突然その場に土下座して叫んだ。
「がびぜろ様!申し訳ございません!がびぜろ様!申し訳ございません!」
すると、空から、指が七本ある手がすう、と降りてきて、
彼の頭をわしづかみにして
「八」
恋人が行方不明になって以来、娘が部屋にひきこもって出てこない。
何を聞いても、
「がびぜろ様、ごめんなさい。がびぜろ様ごめんなさい」
と繰り返しつぶやくばかりだ。
ある日、家の外の壁に、指が七本ある手形のシミをたくさん見つけて
「九」
「だーれだ?」
急に目をおおわれた。
驚いて、後ろに手をのばしてみたが、何も触れない。
誰もいない。
なのに、何かが、目をふさいでいる。
「だーれだ?」
「十」
何かどろどろしたものを、顔に押しつけられて、ぼくは目を覚ました。
「母を喰え」
顔を真っ黒に塗りつぶした男が、そう叫びながら、髪の毛のまじった、何かどろどろとしたものをぼくの口にねじ込んだ。
「母を喰え」
「十一」
最近なぜか、目をつぶると、まぶたの裏の闇の中に、
目玉がはみ出た赤ん坊の顔が浮かびあがる。
眠れない。
怖くて目をつぶれない。
「十二」
「明日の晩、おんめの皮ば剥ぎにいくえ」
と留守電にしゃがれた老人の声が入っていた。
玄関の呼び鈴が鳴った。
「十三」
突然、腹の上に重みを感じて、夜中、ふと目を覚ました。
暗闇の中、布団の上を、上半身だけの姿をした裸の老婆が這い回っていた。
「十四」
「ただいま」
と、玄関の方から、お父さんの声が聞こえた。
・・・・・・・・・・・・え?
じゃあ、いま、私の目の前でご飯を食べているお父さんは、いったい何?
「十五」
朝、学校へ向かう途中に、後ろから誰かが肩を強く叩いてきた。
驚いて振り返ると、顔中にたくさんの画鋲を刺した男が、
「ねえ!ぼくの仲間になってよ!」
と叫びながら、私の手を握りしめてきた。
「十六」
視界の端に、ちらちらと人影が見える。
しかし、まわりを見回しても、誰もいない。
それなのに、前に向きなおると、視界の端にまた人影が見える。
そいつは包丁を持っているような気がする。
「十七」
おかあさんとかいものにいったとき、でんちゅうをなめているおじさんをみた。「おかあさん、あのひとへんだよ」といってゆびさしたら、そのおじさんがとんできて、ぼくのゆびにかじりついた。
「十八」
学校の廊下の端に、「入れ」という看板のついたドアがあった。
気になって中に入ってみたけど、そこは窓も何もない、真っ白な部屋だった。
戻ろうと思ってふりむくと、ドアが無くなっていた。
・・・・・・出られなくなった。
「十九」
おばあちゃんの部屋の机に、豆がいっぱい入ったお椀が置かれていた。
よく見ると、それは豆ではなく、人の足の小指だった。
糸切りバサミを持ったおばあちゃんが、部屋にもどってきた。
「二十」
「ねじ切ろねじ切ろねじ切ろねじ切ろ」
という声が聞こえて、目を覚ました。
牛くらいに大きな手がふたつ、わたしの足と頭をわしづかみにして持ち上げると
「二十一」
「あの、これ、食べてください!」
後輩の女子が、顔を赤らめながら、おれにタッパーをさしだした。
中には、何か赤黒い肉のようなものがつまっていた。
ふと、彼女の足にたくさんの包帯が巻かれていることに気がついた。
「食えよ」
彼女の声色が変わった。
「二十二」
夜、テレビでバラエティー番組を見ていると、画面の隅にぽつんと、血走った目が映っていた。
どれだけチャンネルを変えても、その血走った目はずっと映っていた。
「二十三」
「部屋の電気をつけっぱなしにして寝たら、だめだよう」
目覚めると、全然知らないおじさんがベッドに寝るわたしを見下ろしていた。
おじさんは、「だめだよう」と言いながら、手に持っていた野菜の皮むき器をわたしの額に押し当てた。
「二十四」
「ずっとダベに見られてたんだおしまいだ」
おれのケータイに、友達から意味不明なメールがきていた。
その友達は、おととい死んだ。何者かに、体を縦に引き裂かれたらしい。
そのメールを見て以来、町のあちこちで、身長が3メートルくらいの女が、遠くからおれを見るようになった。
「二十五」
臨死体験をした。
どんなことがあったのかは、よく覚えていない。ただ一度死んで、また生き返ったのは確かだ。
それ以来、ぼくに触れたひとは、なぜかみんな腐って死ぬようになっていた。
ぼくは殺されて、また死んだ。
「二十六」
彼女の部屋で、中学時代の卒業アルバムを見た。
すべての俺の写真の目に、押しピンが刺されていた。
「ずっとこうしたかったの」
手に何かをたくさん握った彼女が、部屋の鍵をゆっくりと閉めた。
「二十七」
6歳の弟が、庭の隅で、
「痛いか?痛いか?」
と笑いながら、棒で何かをつついていた。
虫でもいじめているのかと思って見ると、
5センチくらいの小さな老人が、血まみれになって痙攣していた。
「二十八」
夜中、隣の布団で寝ている6歳の弟が、
「痛い!痛い!」
と泣き叫んだ。
5センチくらいの小さな老人が10人、弟の腹をむさぼり喰っていた。
「二十九」
夜、宿題をやろうとして、机の上でノートを開いた。
誰かの悪戯だろうか。
ノートのページに、頭を割られた女のひとの顔が描かれていた。
どのページにも。
どのページにも。
どのページにもだ。
「三十」
「おなかが裂けるよ」
という声が聞こえて目を覚ました。
肌の白い男の子が、にっこりと笑みを浮かべながら、わたしの腹を見つめていた。
「ほら、もうすぐおなかが裂けるよ」
「三十一」
日曜日の昼間、公園のベンチで、アルミホイルに包んだ何かを食べている、作業着姿のおじさんを見た。
おじさんの口から、髪の毛がはみだしていた。
「三十二」
玄関からガリガリガリガリという音がして、夜中に目を覚ました。
ドアの魚眼レンズから外をのぞくと、
サラリーマン風の男のひとが、歯で私の家のドアを削っていた。
目があった。
「三十三」
深夜、酔っ払いながら路地裏を歩いていると、後ろから、
「動いたら肉ちぎるど」
という老婆の声がした。
硬直したおれの背中や尻を、シワだらけの手の感触が十個、ぺたぺたと這い回った。
「三十四」
「目に入れても痛くないくらい可愛いって、本当よね」
そう言った母親の、右目の眼球が横にずれて、中から血まみれになった赤ん坊の手が出てきた。
「三十五」
花火大会のあとの帰り道、人気のない田んぼ道を家族で歩いていると、父が突然、
「見るな!」
と叫んで私の目をふさいだ。母の息を呑む音がした。
濃い血の臭いが、ゆっくりと近づいてきた。
「三十六」
夕方頃、道路に落書きをしている男の子を見た。
その子は、切り落とした手首の切断面を道路に強くこすりつけて、泣きながら血で絵を描いていた。
「三十七」
「かじらせて」
という手紙が、最近毎日ポストに入れられていた。
毎日毎日毎日毎日・・・・・・。
そして四十四日目、
「今夜かじりにいくから」
という手紙がポストにねじこまれていた。
「三十八」
台所の隅に、いつの間にか深い深い穴が開いていた。
ある日、父がその穴にあやまって落ちた。
その瞬間、私たち家族はみんな父の存在を忘れてしまった。父はいないことになった。
その穴は、いまもまだ台所の隅にある。
「三十九」
ベッドの掛け布団に、ボールくらいのふくらみがあり、動いていた。
ペットの猫かと思って布団をとると、
男の生首に、昆虫の足をつけたような何かが、カサカサと動いていた。
「四十」
友達の部屋の本棚に、何かどろどろした液体を入れたガラスの瓶が置かれていた。
「ねえ、あれ何?」
とわたしが聞くと、友達は、こう答えた。
「お姉ちゃん」
「・・・・・・え?」
「お姉ちゃん」
「四十一」
「あしあげるからうでくれよ」
そう書かれた手紙といっしょに、太ももの付け根から千切りとられた、血まみれの人間の両足が、 アパートの私の部屋のベランダに転がっていた。
手紙の終わりには、
「こんやうでくれよ」
と書かれていた。
もう夜だ。
「四十二」
朝、寝ぼけ眼でスーツに着替え、妻からカバンを受け取り、いってきますと言って家を出た。
会社に向かうバスに乗って席に座ったとき、
昨晩、妻を殺して庭に埋めたことを思い出した。
「四十三」
朝、登校中に、電柱に頭をゴツゴツとぶつけている男を見た。
「30、31、32、33、34・・・・・・・」
とつぶやき、頭をぶつける回数を数えているようだった。
夕方、下校中に、その男がまだ電柱に頭をぶつけているのを見た。
「156789、156790、156791、156792・・・・・・」
男の顔の鼻から上が、ぐちゃぐちゃに潰れていた。
「四十四」
深夜、アパートに帰ると、わたしの部屋の真ん中に、頭部が異様にでこぼこした女が立っていた。
「わたしは神だよ」
と女は言った。
「信じるか?」
と聞いて、女はこちらに歩み寄ってきた。
「信じろよ」
と言って、女は目の前まで来た。
「四十五」
深夜、トイレへ行く途中、廊下で何かを踏み潰した。
暗くて何を踏んだのかはわからなかったが、足元から、かすかにうめき声がした。
翌日、わたしの足は動かなくなった。
「四十六」
「落ちてくるぞおまえの頭の上に落ちてくるぞ」
という差出人不明のメールがケータイに届いていた。
5日後、わたしは、落ちてきたものに頭を溶かされて死んだ。
生者じゃなくなったわたしは、友達のケータイにメールを送信した。
「落ちてくるよあんたの頭の上に落ちてくるよ」
「四十七」
友達が、肉を売りだした。
ブランドバッグが欲しくて、小遣い稼ぎのために、人肉買いに自分の肉を売っているのだ。
友達の体は、いま、あちこちがえぐれている。頬の肉もえぐれて、奥歯が剥き出しになっている。
「いーじゃない。誰にも迷惑かけてないから」
と友達は言う。
「四十八」
オレオレ詐欺をしてみた。適当な番号に電話をかける。
「もしもし?」
「あ、おばあちゃん?オレオレ」
「・・・・・サトシかい?」
「そう、オレ、サトシ」
「サトシ、ちゃんと、お母さんを殺したかい?」
「・・・・・・え?」
「おばあちゃんの指示通りに、死体をすり潰して、トイレに流せたかい?」
「・・・・・・・・・・・・」
「サトシ、サトシ!・・・・・・・・・・・・・・・・・・あんた誰だね?」
「四十九」
夜、仕事から帰ると、アパートの前に、赤ん坊を乗せた乳母車が一台、ぽつんと置かれていた。
赤ん坊の顔が、えぐりとられていた。
ふと視線を感じて上を見ると、えぐりとられた赤ん坊の顔の部分が、宙に浮かんでわたしを見下ろして、きゃっきゃっと笑っていた。
「五十」
目覚めると、暗い倉庫のような場所にいた。
左半身がびりびり痛む。胸のあたりが、妙にすーすーする。
「今日からあなたは人体模型」
どこからか声がした。
まだ暗い朝4時に、ゴミを出しに行った。
ゴミ捨て場には、半透明のゴミ袋がひとつ置かれていた。
中に詰められていた、お婆さんと目があった。
「二」
次の授業は国語だ。
教科書とノートを取り出すために、少年は机の中に手を入れた。
机の中で、何かが手をつかんだ。
「三」
足を切られている途中だった。
顔を真っ黒に塗りつぶした男が、ノコギリでぼくの足を切っている。
ぼくはもう死んでいるのに何すんだよ。
「四」
夜の山道をわたしは歩いていた。
すぐ後ろに、いる、とわかっていた。
振り向いてはいけない、ともわかっていた。
振り向いてしまった彼の、ちぎれた手首が、わたしの指を握りしめていた。
「五」
「ぼく、百足(ムカデ)になっちゃうよう」
と夜中、急に息子が泣きだした。
息子の足が、一本増えていた
「六」
夜中の神社で、必死に祈っている男のひとを見た。
「もう、ゴキブリは殺しません。もう、ゴキブリは殺しません。だから、・・・・・・もどして
そのひとの両腕は、ゴキブリの足になっていた。
「七」
街でデートをしている途中、彼が突然その場に土下座して叫んだ。
「がびぜろ様!申し訳ございません!がびぜろ様!申し訳ございません!」
すると、空から、指が七本ある手がすう、と降りてきて、
彼の頭をわしづかみにして
「八」
恋人が行方不明になって以来、娘が部屋にひきこもって出てこない。
何を聞いても、
「がびぜろ様、ごめんなさい。がびぜろ様ごめんなさい」
と繰り返しつぶやくばかりだ。
ある日、家の外の壁に、指が七本ある手形のシミをたくさん見つけて
「九」
「だーれだ?」
急に目をおおわれた。
驚いて、後ろに手をのばしてみたが、何も触れない。
誰もいない。
なのに、何かが、目をふさいでいる。
「だーれだ?」
「十」
何かどろどろしたものを、顔に押しつけられて、ぼくは目を覚ました。
「母を喰え」
顔を真っ黒に塗りつぶした男が、そう叫びながら、髪の毛のまじった、何かどろどろとしたものをぼくの口にねじ込んだ。
「母を喰え」
「十一」
最近なぜか、目をつぶると、まぶたの裏の闇の中に、
目玉がはみ出た赤ん坊の顔が浮かびあがる。
眠れない。
怖くて目をつぶれない。
「十二」
「明日の晩、おんめの皮ば剥ぎにいくえ」
と留守電にしゃがれた老人の声が入っていた。
玄関の呼び鈴が鳴った。
「十三」
突然、腹の上に重みを感じて、夜中、ふと目を覚ました。
暗闇の中、布団の上を、上半身だけの姿をした裸の老婆が這い回っていた。
「十四」
「ただいま」
と、玄関の方から、お父さんの声が聞こえた。
・・・・・・・・・・・・え?
じゃあ、いま、私の目の前でご飯を食べているお父さんは、いったい何?
「十五」
朝、学校へ向かう途中に、後ろから誰かが肩を強く叩いてきた。
驚いて振り返ると、顔中にたくさんの画鋲を刺した男が、
「ねえ!ぼくの仲間になってよ!」
と叫びながら、私の手を握りしめてきた。
「十六」
視界の端に、ちらちらと人影が見える。
しかし、まわりを見回しても、誰もいない。
それなのに、前に向きなおると、視界の端にまた人影が見える。
そいつは包丁を持っているような気がする。
「十七」
おかあさんとかいものにいったとき、でんちゅうをなめているおじさんをみた。「おかあさん、あのひとへんだよ」といってゆびさしたら、そのおじさんがとんできて、ぼくのゆびにかじりついた。
「十八」
学校の廊下の端に、「入れ」という看板のついたドアがあった。
気になって中に入ってみたけど、そこは窓も何もない、真っ白な部屋だった。
戻ろうと思ってふりむくと、ドアが無くなっていた。
・・・・・・出られなくなった。
「十九」
おばあちゃんの部屋の机に、豆がいっぱい入ったお椀が置かれていた。
よく見ると、それは豆ではなく、人の足の小指だった。
糸切りバサミを持ったおばあちゃんが、部屋にもどってきた。
「二十」
「ねじ切ろねじ切ろねじ切ろねじ切ろ」
という声が聞こえて、目を覚ました。
牛くらいに大きな手がふたつ、わたしの足と頭をわしづかみにして持ち上げると
「二十一」
「あの、これ、食べてください!」
後輩の女子が、顔を赤らめながら、おれにタッパーをさしだした。
中には、何か赤黒い肉のようなものがつまっていた。
ふと、彼女の足にたくさんの包帯が巻かれていることに気がついた。
「食えよ」
彼女の声色が変わった。
「二十二」
夜、テレビでバラエティー番組を見ていると、画面の隅にぽつんと、血走った目が映っていた。
どれだけチャンネルを変えても、その血走った目はずっと映っていた。
「二十三」
「部屋の電気をつけっぱなしにして寝たら、だめだよう」
目覚めると、全然知らないおじさんがベッドに寝るわたしを見下ろしていた。
おじさんは、「だめだよう」と言いながら、手に持っていた野菜の皮むき器をわたしの額に押し当てた。
「二十四」
「ずっとダベに見られてたんだおしまいだ」
おれのケータイに、友達から意味不明なメールがきていた。
その友達は、おととい死んだ。何者かに、体を縦に引き裂かれたらしい。
そのメールを見て以来、町のあちこちで、身長が3メートルくらいの女が、遠くからおれを見るようになった。
「二十五」
臨死体験をした。
どんなことがあったのかは、よく覚えていない。ただ一度死んで、また生き返ったのは確かだ。
それ以来、ぼくに触れたひとは、なぜかみんな腐って死ぬようになっていた。
ぼくは殺されて、また死んだ。
「二十六」
彼女の部屋で、中学時代の卒業アルバムを見た。
すべての俺の写真の目に、押しピンが刺されていた。
「ずっとこうしたかったの」
手に何かをたくさん握った彼女が、部屋の鍵をゆっくりと閉めた。
「二十七」
6歳の弟が、庭の隅で、
「痛いか?痛いか?」
と笑いながら、棒で何かをつついていた。
虫でもいじめているのかと思って見ると、
5センチくらいの小さな老人が、血まみれになって痙攣していた。
「二十八」
夜中、隣の布団で寝ている6歳の弟が、
「痛い!痛い!」
と泣き叫んだ。
5センチくらいの小さな老人が10人、弟の腹をむさぼり喰っていた。
「二十九」
夜、宿題をやろうとして、机の上でノートを開いた。
誰かの悪戯だろうか。
ノートのページに、頭を割られた女のひとの顔が描かれていた。
どのページにも。
どのページにも。
どのページにもだ。
「三十」
「おなかが裂けるよ」
という声が聞こえて目を覚ました。
肌の白い男の子が、にっこりと笑みを浮かべながら、わたしの腹を見つめていた。
「ほら、もうすぐおなかが裂けるよ」
「三十一」
日曜日の昼間、公園のベンチで、アルミホイルに包んだ何かを食べている、作業着姿のおじさんを見た。
おじさんの口から、髪の毛がはみだしていた。
「三十二」
玄関からガリガリガリガリという音がして、夜中に目を覚ました。
ドアの魚眼レンズから外をのぞくと、
サラリーマン風の男のひとが、歯で私の家のドアを削っていた。
目があった。
「三十三」
深夜、酔っ払いながら路地裏を歩いていると、後ろから、
「動いたら肉ちぎるど」
という老婆の声がした。
硬直したおれの背中や尻を、シワだらけの手の感触が十個、ぺたぺたと這い回った。
「三十四」
「目に入れても痛くないくらい可愛いって、本当よね」
そう言った母親の、右目の眼球が横にずれて、中から血まみれになった赤ん坊の手が出てきた。
「三十五」
花火大会のあとの帰り道、人気のない田んぼ道を家族で歩いていると、父が突然、
「見るな!」
と叫んで私の目をふさいだ。母の息を呑む音がした。
濃い血の臭いが、ゆっくりと近づいてきた。
「三十六」
夕方頃、道路に落書きをしている男の子を見た。
その子は、切り落とした手首の切断面を道路に強くこすりつけて、泣きながら血で絵を描いていた。
「三十七」
「かじらせて」
という手紙が、最近毎日ポストに入れられていた。
毎日毎日毎日毎日・・・・・・。
そして四十四日目、
「今夜かじりにいくから」
という手紙がポストにねじこまれていた。
「三十八」
台所の隅に、いつの間にか深い深い穴が開いていた。
ある日、父がその穴にあやまって落ちた。
その瞬間、私たち家族はみんな父の存在を忘れてしまった。父はいないことになった。
その穴は、いまもまだ台所の隅にある。
「三十九」
ベッドの掛け布団に、ボールくらいのふくらみがあり、動いていた。
ペットの猫かと思って布団をとると、
男の生首に、昆虫の足をつけたような何かが、カサカサと動いていた。
「四十」
友達の部屋の本棚に、何かどろどろした液体を入れたガラスの瓶が置かれていた。
「ねえ、あれ何?」
とわたしが聞くと、友達は、こう答えた。
「お姉ちゃん」
「・・・・・・え?」
「お姉ちゃん」
「四十一」
「あしあげるからうでくれよ」
そう書かれた手紙といっしょに、太ももの付け根から千切りとられた、血まみれの人間の両足が、 アパートの私の部屋のベランダに転がっていた。
手紙の終わりには、
「こんやうでくれよ」
と書かれていた。
もう夜だ。
「四十二」
朝、寝ぼけ眼でスーツに着替え、妻からカバンを受け取り、いってきますと言って家を出た。
会社に向かうバスに乗って席に座ったとき、
昨晩、妻を殺して庭に埋めたことを思い出した。
「四十三」
朝、登校中に、電柱に頭をゴツゴツとぶつけている男を見た。
「30、31、32、33、34・・・・・・・」
とつぶやき、頭をぶつける回数を数えているようだった。
夕方、下校中に、その男がまだ電柱に頭をぶつけているのを見た。
「156789、156790、156791、156792・・・・・・」
男の顔の鼻から上が、ぐちゃぐちゃに潰れていた。
「四十四」
深夜、アパートに帰ると、わたしの部屋の真ん中に、頭部が異様にでこぼこした女が立っていた。
「わたしは神だよ」
と女は言った。
「信じるか?」
と聞いて、女はこちらに歩み寄ってきた。
「信じろよ」
と言って、女は目の前まで来た。
「四十五」
深夜、トイレへ行く途中、廊下で何かを踏み潰した。
暗くて何を踏んだのかはわからなかったが、足元から、かすかにうめき声がした。
翌日、わたしの足は動かなくなった。
「四十六」
「落ちてくるぞおまえの頭の上に落ちてくるぞ」
という差出人不明のメールがケータイに届いていた。
5日後、わたしは、落ちてきたものに頭を溶かされて死んだ。
生者じゃなくなったわたしは、友達のケータイにメールを送信した。
「落ちてくるよあんたの頭の上に落ちてくるよ」
「四十七」
友達が、肉を売りだした。
ブランドバッグが欲しくて、小遣い稼ぎのために、人肉買いに自分の肉を売っているのだ。
友達の体は、いま、あちこちがえぐれている。頬の肉もえぐれて、奥歯が剥き出しになっている。
「いーじゃない。誰にも迷惑かけてないから」
と友達は言う。
「四十八」
オレオレ詐欺をしてみた。適当な番号に電話をかける。
「もしもし?」
「あ、おばあちゃん?オレオレ」
「・・・・・サトシかい?」
「そう、オレ、サトシ」
「サトシ、ちゃんと、お母さんを殺したかい?」
「・・・・・・え?」
「おばあちゃんの指示通りに、死体をすり潰して、トイレに流せたかい?」
「・・・・・・・・・・・・」
「サトシ、サトシ!・・・・・・・・・・・・・・・・・・あんた誰だね?」
「四十九」
夜、仕事から帰ると、アパートの前に、赤ん坊を乗せた乳母車が一台、ぽつんと置かれていた。
赤ん坊の顔が、えぐりとられていた。
ふと視線を感じて上を見ると、えぐりとられた赤ん坊の顔の部分が、宙に浮かんでわたしを見下ろして、きゃっきゃっと笑っていた。
「五十」
目覚めると、暗い倉庫のような場所にいた。
左半身がびりびり痛む。胸のあたりが、妙にすーすーする。
「今日からあなたは人体模型」
どこからか声がした。