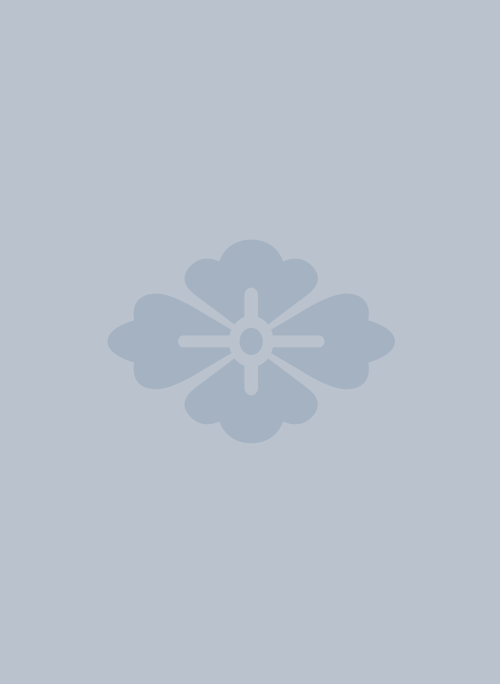「ん……」
翌朝、わたしはやけに頭が重たいことを無意識に感じながら目を覚ました。
ぼやけた意識の中、血の甘い匂いが鼻をかすめた気がして。
わたしは一気に飛び起きた。
「わたし……?」
昨夜、ヴァンパイアに血を吸われた記憶がまざまざと甦ってくる。
銀髪で腰まで伸びていた長髪。
わたしに刻印を刻んでいったヴァンパイアの銀髪はうなじの部分が少し長かったくらいで、長髪ではなかったと訝しげに首をかしげた。
そこではっとして昨夜噛まれた首の部分に触れる。
なんのキズも、ない……?
わたしは慌てて姿見の前に立つとパジャマを脱ぎ捨て裸の上半身をまじまじと見つめた。
仮面舞踏会でつけられたキスマークはまだ美しい形を残していたけれど、首にはキズ一つ、血液の一滴もついてはいなかった。
パジャマを引きちぎられたことも思い出し、パジャマの裂け目も裏表じっくり探すが破られた形跡は微塵もない。
「……どういうこと?」
翌朝、わたしはやけに頭が重たいことを無意識に感じながら目を覚ました。
ぼやけた意識の中、血の甘い匂いが鼻をかすめた気がして。
わたしは一気に飛び起きた。
「わたし……?」
昨夜、ヴァンパイアに血を吸われた記憶がまざまざと甦ってくる。
銀髪で腰まで伸びていた長髪。
わたしに刻印を刻んでいったヴァンパイアの銀髪はうなじの部分が少し長かったくらいで、長髪ではなかったと訝しげに首をかしげた。
そこではっとして昨夜噛まれた首の部分に触れる。
なんのキズも、ない……?
わたしは慌てて姿見の前に立つとパジャマを脱ぎ捨て裸の上半身をまじまじと見つめた。
仮面舞踏会でつけられたキスマークはまだ美しい形を残していたけれど、首にはキズ一つ、血液の一滴もついてはいなかった。
パジャマを引きちぎられたことも思い出し、パジャマの裂け目も裏表じっくり探すが破られた形跡は微塵もない。
「……どういうこと?」