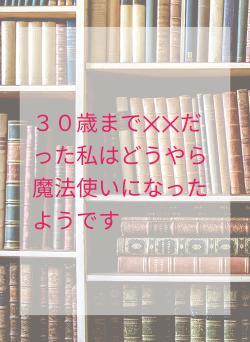「あたしも、行くね」
和馬が出て行ってすぐ梨央がそう言って立ち上がった。
「梨央、本当に?」
あたしは慌てて立ち上がり、梨央の手を掴んだ。
真冬だというのに、梨央の手はジットリと汗ばんでいる。
「うん。1人分のアラーム音ならきっとどうにかなる。でもみんなで集まって大音量になったら、きっと逃げることはできない」
梨央もあたしと同じ考え方なのだ。
スマホの薄明りの中で見えた梨央の顔には涙の跡が残っている。
しかし、今はもう泣いてはいなかった。
決意を固めた表情をしている。
「絶対に、無事でいてね」
あたしがそう言うと、梨央はほほ笑んだ。
「もちろん。若菜もね」
梨央はそう言うと、家庭科室を出て行ったのだった。
和馬が出て行ってすぐ梨央がそう言って立ち上がった。
「梨央、本当に?」
あたしは慌てて立ち上がり、梨央の手を掴んだ。
真冬だというのに、梨央の手はジットリと汗ばんでいる。
「うん。1人分のアラーム音ならきっとどうにかなる。でもみんなで集まって大音量になったら、きっと逃げることはできない」
梨央もあたしと同じ考え方なのだ。
スマホの薄明りの中で見えた梨央の顔には涙の跡が残っている。
しかし、今はもう泣いてはいなかった。
決意を固めた表情をしている。
「絶対に、無事でいてね」
あたしがそう言うと、梨央はほほ笑んだ。
「もちろん。若菜もね」
梨央はそう言うと、家庭科室を出て行ったのだった。