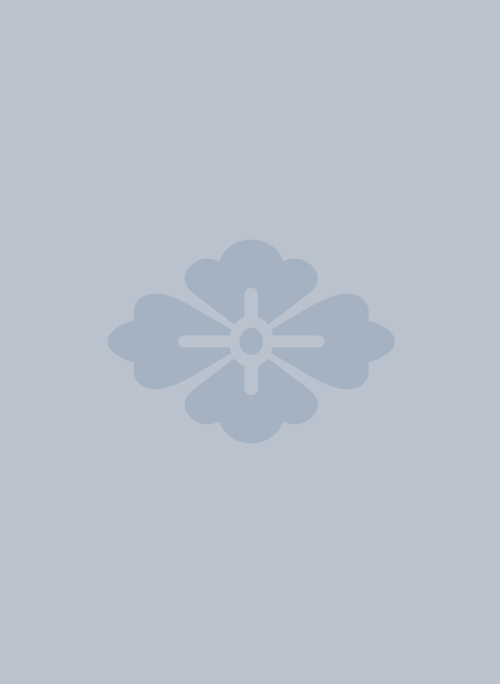昔の夢を見た。
10年も昔のこと。
もう、何年も忘れていた過去の話。
近所に住む、一人の小さな女の子との懐かしい記憶。
女の子は自分より4つ下だと親に聞いた時、とても信じられなかった。
その子が大人びていたからではない。
小さかったのだ。
服から覗く彼女の腕や足は、幼い子供独特の細白さではなく明らかな病弱、虚弱さを子供ながら不審に思っていた。
きっと、誰もがあの子を…
あの子の家庭の異常さに気付いていた。
初めてあの子とあったのは、雨の日だった。飼い猫が雷に怯え、偶然会いていた窓から逃げ出した。小学校から帰って来たとき、母親から聞いたとき、ひどく狼狽えたのを今でも覚えている。
母親の制止の声を振り切り、ランドセルを玄関に放り出し、小雨の中ひたすらに猫を探した。
あちこち探しても、猫はいない。
雨で濡れたシャツが身体に張り付き、体温を奪っていく。
雨が頬を伝う。
涙が、頬を伝う。
毎日同じ布団で寝ていた、大切な猫だった。まだ生まれて1年足らずだ。子供なんだ。自分が探してやらなければ、そう強く思った。
必死に探した。路地も、自動販売機の隙間も、溝も、泥だらけになることを厭わなかった。
それでもいない。
寂しさに、後悔に、押しつぶされそうだった。