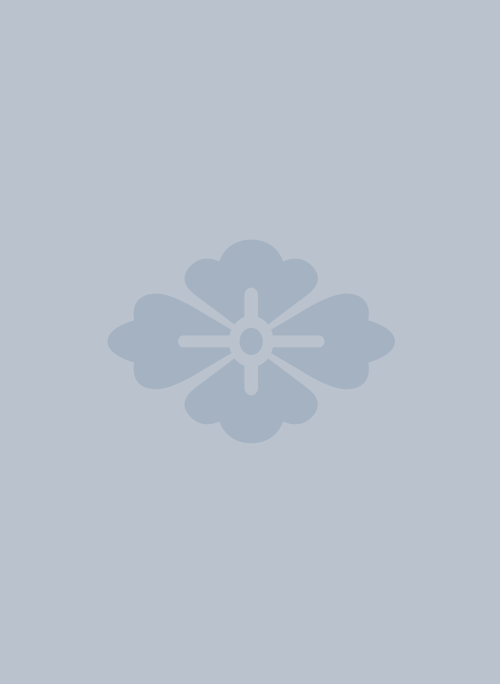ロンドンにある、イースト・エンドには、最近奇妙な噂があった。
深夜になると、酒屋の裏路地から霧に紛れて赤ん坊の泣き声が聞こえてくる。けれども、その声の方向に進んではいけない。
もし、進んでしまったら―。
「……勘弁してくれ」
「おや、ウィリアムはこういう話は苦手かい?探偵の助手なのに」
「ジルよ。探偵の助手が、その手の話を好むという偏見は、早めに捨ててくれ」
ホワイト・チャペル地区のとある通り。ウィルは買い出しのついでに本屋により、その帰りに最近知り合った友人と歩いていた。
「ま、君はともかく。君の恋人なら喜ぶんじゃないかい?」
「恋人じゃねぇよ。相棒だ」
「一つ屋根の下で一緒に暮らしていると言うのに、何のロマンスも生まれないとはね」
やれやれと、大袈裟に肩をすくめるジルを、ウィルは呆れたような目で見る。
ジルという男は、やれ誰と誰が恋仲だとか、誰が誰を好きだとか、女性が好みそうな話が好物らしく。ウィルがアマネの助手をしているということを知った途端、馴れ初めは何だと聞いてきた。
(大体、あいつは恋愛ってもんにあんまり興味無いみたいだしな)
アマネの恋愛事情が気にならない訳ではないが、恐らく興味は無いだろう。恋愛小説すら読もうとしないくらいだ。
「まぁ彼女はともかく、君はどうなんだい?」
「何が?」
ジルの意味深な笑みに、ウィルは訝しげな視線を返す。
「彼女のこと、好きなんじゃないのかなって」
「何言ってんだよ。あいつは俺にとっては、妹みたいなもんだ」
そう言って顔を反らしたウィルに、ジルはやれやれとまた肩をすくめる。
「しかし、彼女は美人だよな。変わってるし、ジャニーだけど」
ジャニーという言葉は、日本人を格下に見ているような言葉で、ウィルはその言葉があまり好きではない。
「ジャニーって呼ぶのは止めろよ」
「ははっ。すまない」
相当不機嫌な顔をしていたのだろう。ジルは困ったように眉を下げた。
「あ、俺こっちだから。じゃあ」
その後の別れ道で、そそくさと去っていったジルの背中を見ながら、ウィルはため息を吐いた。
「ただいま」
「………」
リビングの椅子に座り、前屈みになりながら、手の甲に顎をのせ、アマネは窓の外を眺めていた。
考え事をしている時のポーズだ。
(あの怪盗と何があったのか知らないが、あの時から考え事してるみたいだしな)
ウィルはアマネの前に座ると、机の上に乗っているコーヒーを見る。湯気がたっており、不自然に量も減っているので、こんな時でもコーヒー飲むことを忘れないアマネにホッとした。
そして、ジルの言葉が蘇る。
―彼女のこと、好きなんじゃないのかなって―
(俺にも良く分かんないんだよ。家族のように思ってるのか、そうじゃないのか)
けれども、ウィルはアマネを心から信頼している。それはアマネも同じだろう。
でなければ、家事なんて任せて貰えないだろうし、助手にもしなかった。
(それに、俺は今の関係も結構気に入ってるからな)
アマネに対して、唯一対等に接する相手はウィルだけだろう。彼女は日本人であり、女性でもある。警部から信頼されているだろうが、一部の人間からは疎まれる。
本人は気にしていないようだが、ウィルは気分が悪かった。だから、彼女の名を上げるためにも助手をしているのだ。
「……そう言えばさ、俺の友達からこんな話を聞いたんだけど」
聞いていないだろうと思いながらも、ウィルはジルから聞いた噂を話す。
「って話で、最後まで聞いてないから分からなかったが、何か嘘臭いよな」
「……なるほど」
「は?」
返事が返ってくるとは思わなかったので、随分と間抜けな声が出た。
「謎が解けました。お手柄ですね、ウィル」
「え?いや、何が?」
急に褒められて、何をどうすればいいのか分からない。
「警部から、怪盗を逃した代わりに、ある捜査を頼まれたんです。怪盗を逃したのは、私の責任ですから」
「……ってことはあれか?最近妙に静かに考え込んでたのは、怪盗とは関係ないってか?」
ウィルは口元がピクピクと痙攣するのを感じながら、アマネを見つめる。
「はい」
「んだよチキショー!!俺はてっきりあの怪盗のことで悩んでんのかと思ったんだぞ!気遣ってお前の好きな本買ってきた、俺の気遣い返せよ!!」
頭を抱えて嘆くウィルから視線を反らし、アマネは紙袋から本を取り出す。
「彼の件では不愉快な思いをしましたが、あの怪盗に構っていられるほど暇ではありませんから。ああ、この本はありがたく頂きますね」
「………お好きにどーぞ」
ウィルの疲れきったような声に、アマネは小さく笑みを漏らした。
(怪盗のことを考えていなかった訳でもないんですがね)
ただ、ウィルにわざわざ話す必要はないと思った。
ウィルはアマネとは正反対だ。一度懐に受け入れた相手は無条件に信じ、優しさを振り撒く。そのせいで、ウィル自身が傷付くだろうに。
(何でもすぐに顔に出ますから、君のことは推理しなくても分かります)
深夜になると、酒屋の裏路地から霧に紛れて赤ん坊の泣き声が聞こえてくる。けれども、その声の方向に進んではいけない。
もし、進んでしまったら―。
「……勘弁してくれ」
「おや、ウィリアムはこういう話は苦手かい?探偵の助手なのに」
「ジルよ。探偵の助手が、その手の話を好むという偏見は、早めに捨ててくれ」
ホワイト・チャペル地区のとある通り。ウィルは買い出しのついでに本屋により、その帰りに最近知り合った友人と歩いていた。
「ま、君はともかく。君の恋人なら喜ぶんじゃないかい?」
「恋人じゃねぇよ。相棒だ」
「一つ屋根の下で一緒に暮らしていると言うのに、何のロマンスも生まれないとはね」
やれやれと、大袈裟に肩をすくめるジルを、ウィルは呆れたような目で見る。
ジルという男は、やれ誰と誰が恋仲だとか、誰が誰を好きだとか、女性が好みそうな話が好物らしく。ウィルがアマネの助手をしているということを知った途端、馴れ初めは何だと聞いてきた。
(大体、あいつは恋愛ってもんにあんまり興味無いみたいだしな)
アマネの恋愛事情が気にならない訳ではないが、恐らく興味は無いだろう。恋愛小説すら読もうとしないくらいだ。
「まぁ彼女はともかく、君はどうなんだい?」
「何が?」
ジルの意味深な笑みに、ウィルは訝しげな視線を返す。
「彼女のこと、好きなんじゃないのかなって」
「何言ってんだよ。あいつは俺にとっては、妹みたいなもんだ」
そう言って顔を反らしたウィルに、ジルはやれやれとまた肩をすくめる。
「しかし、彼女は美人だよな。変わってるし、ジャニーだけど」
ジャニーという言葉は、日本人を格下に見ているような言葉で、ウィルはその言葉があまり好きではない。
「ジャニーって呼ぶのは止めろよ」
「ははっ。すまない」
相当不機嫌な顔をしていたのだろう。ジルは困ったように眉を下げた。
「あ、俺こっちだから。じゃあ」
その後の別れ道で、そそくさと去っていったジルの背中を見ながら、ウィルはため息を吐いた。
「ただいま」
「………」
リビングの椅子に座り、前屈みになりながら、手の甲に顎をのせ、アマネは窓の外を眺めていた。
考え事をしている時のポーズだ。
(あの怪盗と何があったのか知らないが、あの時から考え事してるみたいだしな)
ウィルはアマネの前に座ると、机の上に乗っているコーヒーを見る。湯気がたっており、不自然に量も減っているので、こんな時でもコーヒー飲むことを忘れないアマネにホッとした。
そして、ジルの言葉が蘇る。
―彼女のこと、好きなんじゃないのかなって―
(俺にも良く分かんないんだよ。家族のように思ってるのか、そうじゃないのか)
けれども、ウィルはアマネを心から信頼している。それはアマネも同じだろう。
でなければ、家事なんて任せて貰えないだろうし、助手にもしなかった。
(それに、俺は今の関係も結構気に入ってるからな)
アマネに対して、唯一対等に接する相手はウィルだけだろう。彼女は日本人であり、女性でもある。警部から信頼されているだろうが、一部の人間からは疎まれる。
本人は気にしていないようだが、ウィルは気分が悪かった。だから、彼女の名を上げるためにも助手をしているのだ。
「……そう言えばさ、俺の友達からこんな話を聞いたんだけど」
聞いていないだろうと思いながらも、ウィルはジルから聞いた噂を話す。
「って話で、最後まで聞いてないから分からなかったが、何か嘘臭いよな」
「……なるほど」
「は?」
返事が返ってくるとは思わなかったので、随分と間抜けな声が出た。
「謎が解けました。お手柄ですね、ウィル」
「え?いや、何が?」
急に褒められて、何をどうすればいいのか分からない。
「警部から、怪盗を逃した代わりに、ある捜査を頼まれたんです。怪盗を逃したのは、私の責任ですから」
「……ってことはあれか?最近妙に静かに考え込んでたのは、怪盗とは関係ないってか?」
ウィルは口元がピクピクと痙攣するのを感じながら、アマネを見つめる。
「はい」
「んだよチキショー!!俺はてっきりあの怪盗のことで悩んでんのかと思ったんだぞ!気遣ってお前の好きな本買ってきた、俺の気遣い返せよ!!」
頭を抱えて嘆くウィルから視線を反らし、アマネは紙袋から本を取り出す。
「彼の件では不愉快な思いをしましたが、あの怪盗に構っていられるほど暇ではありませんから。ああ、この本はありがたく頂きますね」
「………お好きにどーぞ」
ウィルの疲れきったような声に、アマネは小さく笑みを漏らした。
(怪盗のことを考えていなかった訳でもないんですがね)
ただ、ウィルにわざわざ話す必要はないと思った。
ウィルはアマネとは正反対だ。一度懐に受け入れた相手は無条件に信じ、優しさを振り撒く。そのせいで、ウィル自身が傷付くだろうに。
(何でもすぐに顔に出ますから、君のことは推理しなくても分かります)