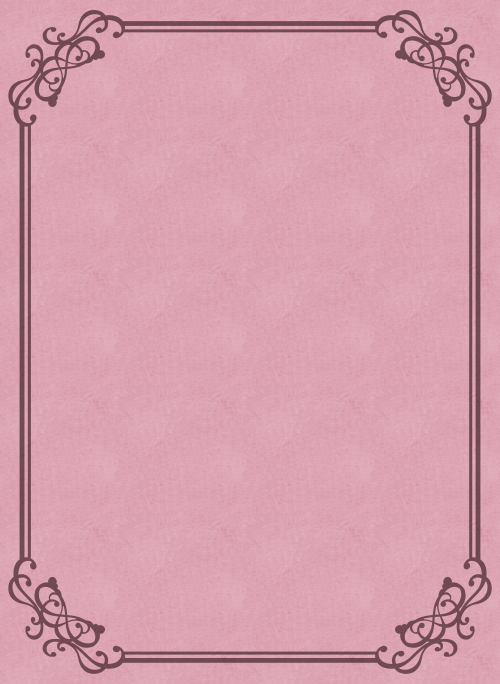懐かしい人が、城を訪れたのは、ジュールが蜂起したという知らせがあってふた月が過ぎようとしている頃だった。
謁見のための小さな部屋に呼び出されたディアヌは、久しぶりの再会に言葉を失った。
「クラーラ院長……なぜ……?」
「おばあ様……」
同行したジゼルも、何も言えないようだった。
まさか、院長がここに来るとは思ってもいなかった。だが、城を訪れたのは院長だけではなかった。ラマティーヌ修道院に所属する修道女全員が院長に従って城を訪れたのだ。
そして、彼女達の中には傷を負った者もいた。
ジゼルが先頭に立ち、修道女達を施療院の一角——使っていない部屋はたくさんある——収容する準備が行われる。
残ったディアヌは、院長の報告を聞くことになった。
「近隣の住民の避難も終えました、陛下。ジュールとその一行は、この城を目指してくるようです。我々は、王妃様の警護につきます」
「わかった。頼むぞ」
「近隣の住民って……?」
「ラマティーヌ修道院が襲撃されたのです。踏みとどまって、戦うことも考えましたが、ジュールの軍に抵抗するにはあまりにも人数が少ない。近隣の住民の避難を終えた後、我々も撤退してきたというわけです」
だから、怪我を負っていたというのか。まさか、ジュールが修道院を襲撃するとは思ってもみなかった。
「なぜ、修道院が襲撃されなければならないのです?」
震える声で問う。修道院を襲撃するなんて、食うに困ったならず者ならともかく、きちんと統制の取れた軍隊ならしない。少なくともディアヌの常識ではそうだった。
謁見のための小さな部屋に呼び出されたディアヌは、久しぶりの再会に言葉を失った。
「クラーラ院長……なぜ……?」
「おばあ様……」
同行したジゼルも、何も言えないようだった。
まさか、院長がここに来るとは思ってもいなかった。だが、城を訪れたのは院長だけではなかった。ラマティーヌ修道院に所属する修道女全員が院長に従って城を訪れたのだ。
そして、彼女達の中には傷を負った者もいた。
ジゼルが先頭に立ち、修道女達を施療院の一角——使っていない部屋はたくさんある——収容する準備が行われる。
残ったディアヌは、院長の報告を聞くことになった。
「近隣の住民の避難も終えました、陛下。ジュールとその一行は、この城を目指してくるようです。我々は、王妃様の警護につきます」
「わかった。頼むぞ」
「近隣の住民って……?」
「ラマティーヌ修道院が襲撃されたのです。踏みとどまって、戦うことも考えましたが、ジュールの軍に抵抗するにはあまりにも人数が少ない。近隣の住民の避難を終えた後、我々も撤退してきたというわけです」
だから、怪我を負っていたというのか。まさか、ジュールが修道院を襲撃するとは思ってもみなかった。
「なぜ、修道院が襲撃されなければならないのです?」
震える声で問う。修道院を襲撃するなんて、食うに困ったならず者ならともかく、きちんと統制の取れた軍隊ならしない。少なくともディアヌの常識ではそうだった。