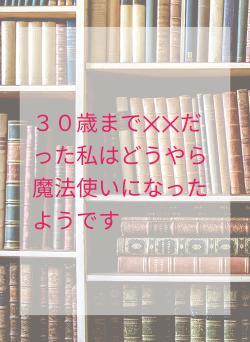先輩と別れて教室へ向かっていると、時々知らない男子生徒たちから声をかけられた。
みんな古家先輩のファンだった人たちだ。
俺に敵意を向けているのではなく、むしろ尊敬のまなざしを向ける生徒が多かった。
彼らは口をそろえて「古家こはるをどうやって落としたんだ」と、聞いてきた。
その質問に俺は決まって「向こうから告白をしてきたんだ」と、答えた。
するとみんなは目を見開き、古家こはるは冴えない年下男子が好みのタイプなんだと思い込んでいた。
実際に告白をしてきたのは古家先輩からだった。
ただ、普通の告白ではない。
『1人でいることが耐えられない。まだ幻覚を見るの』
という内容のものだった。
俺自身も死んでいった人たちの夢をずっと見続けていて、終わりのない闇へと引きずり込まれるような気持ちでいた。
そんな時に同じ心境の古家先輩がいたら、自然とそんな流れにもなるものだ。
お互いに成長し、傷が癒えた時、俺たちはそれでも一緒にいるかどうかはわからなかったのだった。
みんな古家先輩のファンだった人たちだ。
俺に敵意を向けているのではなく、むしろ尊敬のまなざしを向ける生徒が多かった。
彼らは口をそろえて「古家こはるをどうやって落としたんだ」と、聞いてきた。
その質問に俺は決まって「向こうから告白をしてきたんだ」と、答えた。
するとみんなは目を見開き、古家こはるは冴えない年下男子が好みのタイプなんだと思い込んでいた。
実際に告白をしてきたのは古家先輩からだった。
ただ、普通の告白ではない。
『1人でいることが耐えられない。まだ幻覚を見るの』
という内容のものだった。
俺自身も死んでいった人たちの夢をずっと見続けていて、終わりのない闇へと引きずり込まれるような気持ちでいた。
そんな時に同じ心境の古家先輩がいたら、自然とそんな流れにもなるものだ。
お互いに成長し、傷が癒えた時、俺たちはそれでも一緒にいるかどうかはわからなかったのだった。