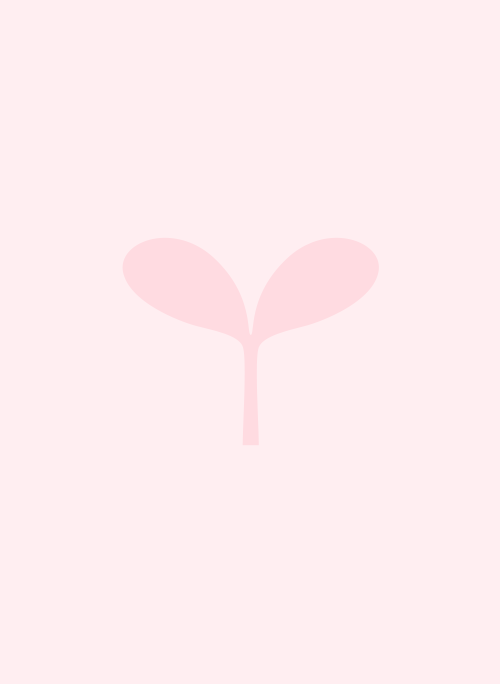薄すぎる自分の伸びきった影を見ると、何だか無性に気が滅入ってしまう。
そのまま消えて行きそうで、それでいてバチンと限界を越えたゴム紐のように、難無く今にも千切れてしまわないか、見ているだけでも、僕を不安で堪らなくさせる。
今の自分なら、専ら、そんなことを考えることすらも、正直、嫌になっていた。
僕は歩きながら、ひょろ長い影を動かして、何度も掘り返されたことのある継ぎ剥ぎだらけのアスファルトの地面を這い、腕を伸ばし、曲げ、影を操る。
一見無意味な動作をすることで、僕は僕がそこにいることを確かめるのだ。
高校を卒業したばかりの未熟な僕には、まだこの世の中の濁った甘い空気を、勢いよく飲み込めるほど、鈍感にはなれない。
そう単純に馴染めるものではないことは、解りきったことであり、もし何かが起きたところで、そのまま受け入れることが出来るほど、自分がそんな心の強い人間だとも到底思えなかった。
結局、僕は自問してばかりで、ただ傲慢に、頑固に取り繕う自分を、一途に頼るしかなかったのだ。
ガソリンスタンドの明かりだけが頼りの、深夜の町の一角。
電柱に沿って湾曲に貼られたポスターの若い女性が、その僅かな明かりの恩恵を受けて、僕の方を向いて微笑んでいる。
それは、化粧品のポスター。白いスーツを着た上半身だけの彼女。切り取られた体は、何故か生き生きとしていて、まざまざと思いを含んだ僕に見せ付ける。
胸元からも覗える、透き通るような白い肌の彼女は、キリリとした睫毛で、この僕から視線を反らそうともしない。
「ねぇ、この町を出るの?」
うっとりとした、艶っぽい大人の女性の声が、僕を感電させる。
擽(くすぐ)ったいようで、落ち着かない。胸焼けのような苦しさが、意味もなく愛しい。
実際のところは、そんな風にポスターが言っている様でも、聞こえている訳でもないのだ。
僕の頭の中だけをめぐる、単なる言葉の羅列、妄想に過ぎない。
「そうだよ。僕は自由になるんだ」
僕はそれでも独り言のように、ポスターに向かって、大真面目に話し掛ける。
誰も見ていないことを良いことに、やりたい放題だった。後日その事を誰かに罵られても、何ら過言ではないと僕は思う。
そのまま消えて行きそうで、それでいてバチンと限界を越えたゴム紐のように、難無く今にも千切れてしまわないか、見ているだけでも、僕を不安で堪らなくさせる。
今の自分なら、専ら、そんなことを考えることすらも、正直、嫌になっていた。
僕は歩きながら、ひょろ長い影を動かして、何度も掘り返されたことのある継ぎ剥ぎだらけのアスファルトの地面を這い、腕を伸ばし、曲げ、影を操る。
一見無意味な動作をすることで、僕は僕がそこにいることを確かめるのだ。
高校を卒業したばかりの未熟な僕には、まだこの世の中の濁った甘い空気を、勢いよく飲み込めるほど、鈍感にはなれない。
そう単純に馴染めるものではないことは、解りきったことであり、もし何かが起きたところで、そのまま受け入れることが出来るほど、自分がそんな心の強い人間だとも到底思えなかった。
結局、僕は自問してばかりで、ただ傲慢に、頑固に取り繕う自分を、一途に頼るしかなかったのだ。
ガソリンスタンドの明かりだけが頼りの、深夜の町の一角。
電柱に沿って湾曲に貼られたポスターの若い女性が、その僅かな明かりの恩恵を受けて、僕の方を向いて微笑んでいる。
それは、化粧品のポスター。白いスーツを着た上半身だけの彼女。切り取られた体は、何故か生き生きとしていて、まざまざと思いを含んだ僕に見せ付ける。
胸元からも覗える、透き通るような白い肌の彼女は、キリリとした睫毛で、この僕から視線を反らそうともしない。
「ねぇ、この町を出るの?」
うっとりとした、艶っぽい大人の女性の声が、僕を感電させる。
擽(くすぐ)ったいようで、落ち着かない。胸焼けのような苦しさが、意味もなく愛しい。
実際のところは、そんな風にポスターが言っている様でも、聞こえている訳でもないのだ。
僕の頭の中だけをめぐる、単なる言葉の羅列、妄想に過ぎない。
「そうだよ。僕は自由になるんだ」
僕はそれでも独り言のように、ポスターに向かって、大真面目に話し掛ける。
誰も見ていないことを良いことに、やりたい放題だった。後日その事を誰かに罵られても、何ら過言ではないと僕は思う。