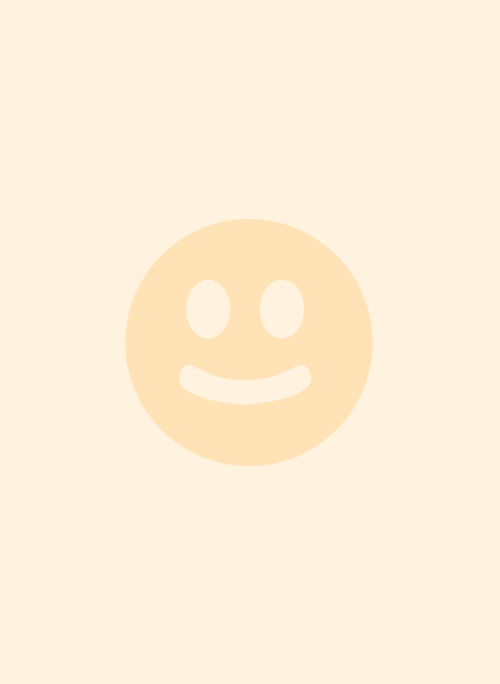母が泣いている。
仕方なくリュートは皇都にある離宮に戻ってきた。
「おかえりなさいませ、リュート様」
侍女達が勢揃いで恭しく首を垂れるのを、リュートは不服そうに鼻息で返す。
嫌いなのだ、こういうのは。
もうちょっとさあ、なんかこう、『あらおかえり、もう、どこ行ってたの、ほっつき歩いてさ』みたいなフランクな感じがいいのだ。
なのに、これじゃあ堅苦しくていけない。
だって、そうだろう?
俺は勇者の子息とか、いいとこのボンボンみたいな自覚は全くないんだから。
仕方なくリュートは皇都にある離宮に戻ってきた。
「おかえりなさいませ、リュート様」
侍女達が勢揃いで恭しく首を垂れるのを、リュートは不服そうに鼻息で返す。
嫌いなのだ、こういうのは。
もうちょっとさあ、なんかこう、『あらおかえり、もう、どこ行ってたの、ほっつき歩いてさ』みたいなフランクな感じがいいのだ。
なのに、これじゃあ堅苦しくていけない。
だって、そうだろう?
俺は勇者の子息とか、いいとこのボンボンみたいな自覚は全くないんだから。