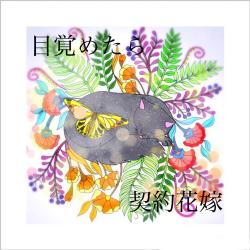夏も終わり、朝晩が冷え込むようになってきた。
隣の温もりに擦り寄っていけば、抱き寄せられる腕に安堵する。
髪を優しく撫でられ、また眠りに落ちそうになる。
「朱里、起きたか?」
掠れたセクシーな声も聞き慣れてきた。唇に落ちてくるキスも随分と慣れてきた。
「朱里?」
「ん?」
「シャワー浴びるか?」
「うん、尚輝が先に………。」
「一緒にだ。」
尚輝がベッドから出ていくのを感じ、お湯を張る音が聞こえてくる。
戻ってきた尚輝がベッドに潜り込んで私を抱き寄せる。
「朱里、一緒に暮らさないか?」
「………。」
「そろそろ一緒に暮らしたい。」
尚輝の囁きが耳元でする。
「週末だけじゃなく、一緒にいたい。」
最近、週末だけは尚輝の部屋に泊まる。一緒にいれば、離れたくない気持ちはわかる。
ずっと一緒にいたくなる。
「朱里、一緒に暮らさないか?」
囁かれる甘い声に尚輝を抱き締めた。
隣の温もりに擦り寄っていけば、抱き寄せられる腕に安堵する。
髪を優しく撫でられ、また眠りに落ちそうになる。
「朱里、起きたか?」
掠れたセクシーな声も聞き慣れてきた。唇に落ちてくるキスも随分と慣れてきた。
「朱里?」
「ん?」
「シャワー浴びるか?」
「うん、尚輝が先に………。」
「一緒にだ。」
尚輝がベッドから出ていくのを感じ、お湯を張る音が聞こえてくる。
戻ってきた尚輝がベッドに潜り込んで私を抱き寄せる。
「朱里、一緒に暮らさないか?」
「………。」
「そろそろ一緒に暮らしたい。」
尚輝の囁きが耳元でする。
「週末だけじゃなく、一緒にいたい。」
最近、週末だけは尚輝の部屋に泊まる。一緒にいれば、離れたくない気持ちはわかる。
ずっと一緒にいたくなる。
「朱里、一緒に暮らさないか?」
囁かれる甘い声に尚輝を抱き締めた。