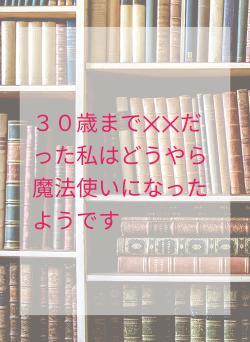あたしが早い段階で助けを呼んだ事がよかったようで、庭から逃げようとしていた犯人は旅館の人の手によって捕まっていた。
事情を聞くためにとらえられた相手の顔をチラリと見た時、あたしは息を飲んだ。
それはあたしが夢で見たあの男と同じだったのだ。
恐怖心からか、夢の中の顔はハッキリと覚えていたので、間違いない。
「すごいね千里」
そんな出来事があったのだと玲子に話すと、玲子は感心したようにそう言った。
「怖かったよ」
思い出して身震いをする。
ついさっきみんなでお風呂に入ったばかりなのに、背筋がゾクリとするのを感じた。
あの不思議な夢を見なければあたしはあの犯人と対峙していたことになるのだ。
その後どうなっていたのかもわからない。
「予知夢ってやつだね」
玲子がそう言うので、あたしは首を傾げた。
予知夢というのは聞いたことがあったけれど、実際それを経験した事なんて1度もない。
「もしかしたらご先祖様が守ってくれたのかもね。特別な能力のない千里に夢を見させて逃げさせてくれたんだよ」
そう言う玲子にあたしは「そうなのかなぁ」と、呟くように言った。
事情を聞くためにとらえられた相手の顔をチラリと見た時、あたしは息を飲んだ。
それはあたしが夢で見たあの男と同じだったのだ。
恐怖心からか、夢の中の顔はハッキリと覚えていたので、間違いない。
「すごいね千里」
そんな出来事があったのだと玲子に話すと、玲子は感心したようにそう言った。
「怖かったよ」
思い出して身震いをする。
ついさっきみんなでお風呂に入ったばかりなのに、背筋がゾクリとするのを感じた。
あの不思議な夢を見なければあたしはあの犯人と対峙していたことになるのだ。
その後どうなっていたのかもわからない。
「予知夢ってやつだね」
玲子がそう言うので、あたしは首を傾げた。
予知夢というのは聞いたことがあったけれど、実際それを経験した事なんて1度もない。
「もしかしたらご先祖様が守ってくれたのかもね。特別な能力のない千里に夢を見させて逃げさせてくれたんだよ」
そう言う玲子にあたしは「そうなのかなぁ」と、呟くように言った。