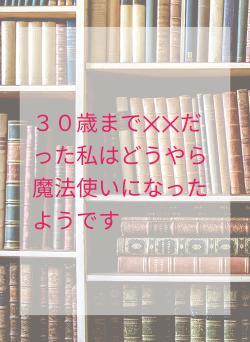翌日、太陽の光が部屋に差し込んできて目を覚ました。
なんだか心がすごくスッキリしている。
あの女が死んだと言うのに、全然悲しくなんてなかった。
ベッドから下りて大きく伸びをする。
長年足にくくりつけられていた鎖が取れたように体が軽く感じられる。
今日のあたしならなんだってできる!
そんな清々しい朝だった。
テキパキと制服に着替えてリビングへ下りて行く。
今日の朝ご飯は何にしようか。
お金は沢山あるんだ、朝から少し豪華なものを食べてしまおうか。
そんな事考えながら一階へたどり着いた途端、懐かしい、朝の食卓の香りが鼻孔をくすぐった。
それは何年も嗅いでこなかった香り。
だけど決して忘れない、お母さんの朝ご飯の香りだ。
「なんで……?」
そう呟き、早足でキッチンへ向かった。
大きくドアを開けて……エプロンをつけてキッチンに立っているお母さんがいた。
なんだか心がすごくスッキリしている。
あの女が死んだと言うのに、全然悲しくなんてなかった。
ベッドから下りて大きく伸びをする。
長年足にくくりつけられていた鎖が取れたように体が軽く感じられる。
今日のあたしならなんだってできる!
そんな清々しい朝だった。
テキパキと制服に着替えてリビングへ下りて行く。
今日の朝ご飯は何にしようか。
お金は沢山あるんだ、朝から少し豪華なものを食べてしまおうか。
そんな事考えながら一階へたどり着いた途端、懐かしい、朝の食卓の香りが鼻孔をくすぐった。
それは何年も嗅いでこなかった香り。
だけど決して忘れない、お母さんの朝ご飯の香りだ。
「なんで……?」
そう呟き、早足でキッチンへ向かった。
大きくドアを開けて……エプロンをつけてキッチンに立っているお母さんがいた。