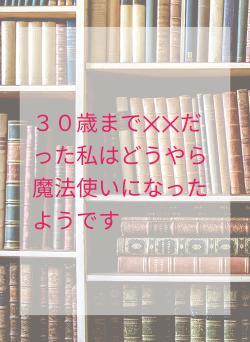『自殺タカログ』のハガキは、朝起きてポストを覗くとすでになくなっていた。
何者かがこっそり回収しに来たらしい。
あたしは『自殺カタログ』を鞄に忍ばせて家を出た。
誰もあたしの部屋に入る事はないと思うが、念のためだ。
お父さんが偶然見つけてしまったら、いらぬ心配をかけてしまうかもしれない。
下駄箱で靴を履きかえていると、後方から数人の女子生徒の話し声が聞えて来た。
あたしは邪魔にならないように手早く履き替えて廊下を歩く。
「やっほぉ芽衣」
後ろからアンミの声が聞こえてきて、背筋が震えた。
後方から聞こえて来た話声はアンミたちのグループのものだったようだ。
あたしはぎこちない笑顔を浮かべて振り向いた。
「お、おはよう……」
こんなイジメっ子たちへ向けて無理やり笑顔を浮かべている自分が情けない。
どうにかアンミたちの機嫌を損ねないように必死になっている自分が悲しい。
「今日はなにして遊ぼっかぁ?」
アンミがそう言いながらあたしの肩に手を回して来た。
香水の甘い香りにむせ返りそうになる。
「昨日の続きする? 今度は下着姿じゃなくて、全裸にして写真でも撮る?」
そう聞いてくるアンミに体中が凍り付くのを感じる。
アンミは明らかに昨日の事を根に持っているようだ。
何者かがこっそり回収しに来たらしい。
あたしは『自殺カタログ』を鞄に忍ばせて家を出た。
誰もあたしの部屋に入る事はないと思うが、念のためだ。
お父さんが偶然見つけてしまったら、いらぬ心配をかけてしまうかもしれない。
下駄箱で靴を履きかえていると、後方から数人の女子生徒の話し声が聞えて来た。
あたしは邪魔にならないように手早く履き替えて廊下を歩く。
「やっほぉ芽衣」
後ろからアンミの声が聞こえてきて、背筋が震えた。
後方から聞こえて来た話声はアンミたちのグループのものだったようだ。
あたしはぎこちない笑顔を浮かべて振り向いた。
「お、おはよう……」
こんなイジメっ子たちへ向けて無理やり笑顔を浮かべている自分が情けない。
どうにかアンミたちの機嫌を損ねないように必死になっている自分が悲しい。
「今日はなにして遊ぼっかぁ?」
アンミがそう言いながらあたしの肩に手を回して来た。
香水の甘い香りにむせ返りそうになる。
「昨日の続きする? 今度は下着姿じゃなくて、全裸にして写真でも撮る?」
そう聞いてくるアンミに体中が凍り付くのを感じる。
アンミは明らかに昨日の事を根に持っているようだ。