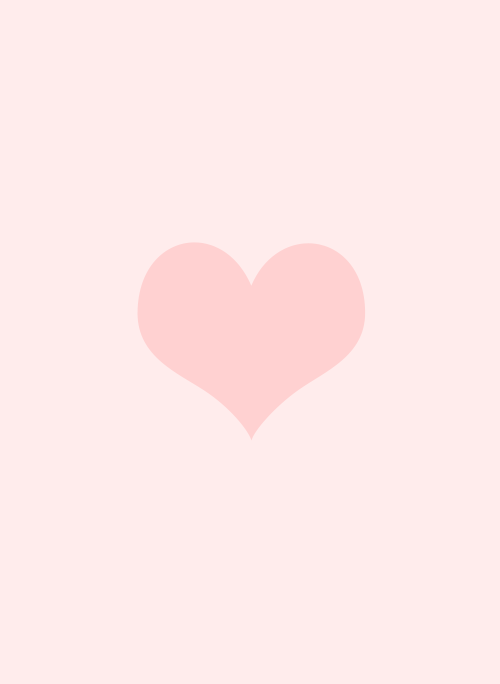「ごめっ…大丈夫だから」
そう言って彼を突き離そうとしたら、ぎゅっと手首を掴まれた。
「あの夜と同じだな…」
小さく呟き、笑みを浮かべる。
肝試しの夜のことを言ってるんだと思い出し、カッと顔が熱くなった。
「今は別に怖くて泣いてる訳じゃないから…」
やっと来た幸せを手離さないといけないから辛い。
それを打ち明ける訳にもいかないし、気持ちを話すのですらタブーだ。
もう一度手を振り解こうとしたのに繋がれる。
こんなイジワルを繰り返して、何が一体面白い?
恨みがましく思いながら見つめれば、彼は不思議と喜んでるようにも見える。
その様子にムッとした表情を浮かべると口を開いた。
「肝試しの夜にさ、大田をこうして抱きしめたくて仕方なかった。中学生なのにそれをしたら駄目だよな…と思って、必死で唄いながら誤魔化した」
見つめてる目が本気そうだった。
顎が落ちそうなくらいポカン…と、顔を眺めてしまった。
「大田、俺は……」
真面目な表情をしている一ノ瀬圭太に寄り添いたい。
この温もりに包まれて、いつまでも触れていたい。
あの頃と同じように、隣を歩いてみたいーー。
(だけど、もう…遅すぎる……)
私達はもう…子供じゃないんだーーー。
「もう子供じゃないよ。私達」
掴まれてた手首を無理矢理に振り解いた。
その手首を見つめた視線が、私の方に向けられる。