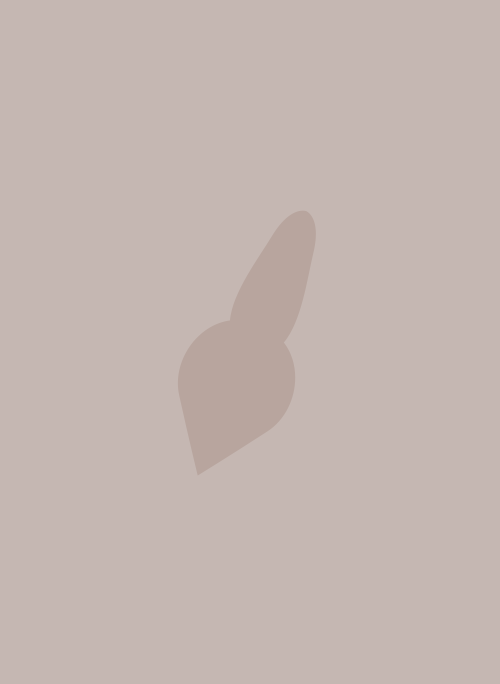「逢えたかな」
そう、彼女は静かに呟いた。
「え?」
何のことだか解らなくて、彼女の方を見れば、彼女はそっと空を見上げていた。
「織姫さまと彦星さま」
そんな彼女の言葉に、デジタル時計の日付を見て、なるほどとひとり納得した。
「...でも、可哀想だよね」
そう言って、彼女は俺の方を見て"ね?"と首を傾ける。そんな可愛い彼女は、いつも言葉足りなくて。その度、俺は彼女の言葉の意味を知ろうと頭をフル回転させる。
「1年に1度だけだから?」
「うん」
「確かに、もう少し逢わせてあげてもいいのにね」
「そうかな?1年に1度だけしか逢えないなら、いっそ、二度と逢えない方がいいと思うなぁ」
そう言って、コトンと彼女が俺の肩に寄り掛かる。心地好い温もりに自然と頬が緩む。
「どうして?」
「...だって、もしさ、離れてる間にどっちかに好きな人ができちゃったら、どうする?」
「好きな人って」
「だって、わからないよ、人の心なんて」
「そんな、夢のないこと言わないの」
そう言って、今度は俺が彼女の頭に額をあてた。
「私だったら、天帝の目を盗んで、電車でもバスでも、タクシーでも自転車でも、なんでも使って、こっそり彦星に逢いに行っちゃうかもしれないなぁ」
「...それは彦星も驚く、天真爛漫な織姫だな」
「そしたら、彦星喜ぶかな?」
「...そりゃ、嬉しいんじゃない?でも、俺が彦星だったら、自分の方から逢いに行くけどね、全速力で走って。」
そう言ってみせれば、彼女は驚いたように少しだけ眉を上げて、それから、"素敵な彦星だね"とクスクスと笑った。
「ねぇ、」
「ん?」
「逢えたといいね」
「逢えたよ、きっと」
「そうだね」
そんな彼女との他愛ない会話に、
"幸せだな"と思わず呟いていた。
*end*