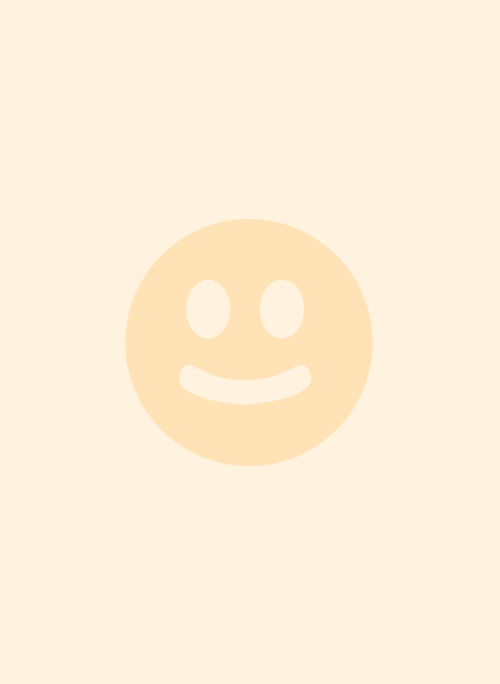翌朝、私達は二人とも不機嫌な顔のままで出勤した。
今日は息子の雅坊は私が朝、彼の実家へ迎えにいって保育園に送って行く手はずだったのが、桑谷さんが言ったのだ、俺がする、と。
彼は私と同じデパート3階のスポーツ用品店の売り場責任者であるにもかかわらず、シフトを強引に変更して自分を遅番に設定し、保育園への送りを実行した。
「どうしてよ?」
朝、台所で立ったままモーニングコーヒーを飲んでいた私は呆れて振り返る。
シフトかえた、俺が送っていくから、とその直前に聞いたのだ。
「大丈夫なの、売り場?人いたの?ってかいつの間にシフト変更の連絡したわけ?」
私の矢継ぎ早の質問に、彼は洗ったばかりの頭をタオルで拭きながら簡単に答えた。
「起きてからだ。新入社員の張り切りボーイが売り場にいるんだ。ヤツに頼んだら喜んで引き受けてくれた」
「・・・」
喜んで、のところは信用しないでおきましょ、私は心の中でこっそりそう思ってあからさまなため息をつく。
「で、どうしてあなたが雅坊の送りを?今までそんなこと言い出さなかったじゃないの」
これまでだってあったのだ。実家に迎えにいって保育園に送って行くことは。それは、例え彼が昼出勤だったとしても私がやっていた。まだ幼い息子はやはり母の顔を見るほうが喜ぶからな、と彼本人が言ったのだ。なのに、なぜ。
昨日は遅くて結局お風呂に入らなかったためにさっきシャワーを浴びたばかりの上半身裸の格好で、彼は私をじっと見た。
その一重の黒目には愛嬌のカケラもなかった。やたらと真剣な目で、彼は私をしばらく見てから呟くように言う。