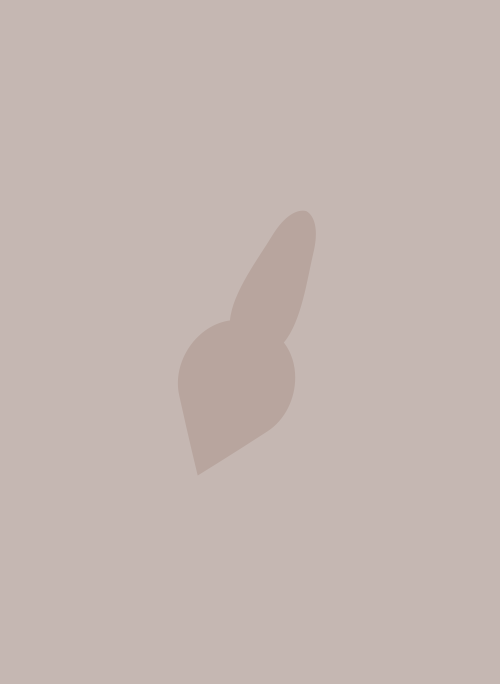日曜日の夕陽の射し込む部屋は、静かで、言いようのない切ない気持ちになる。
ソファに座る私の膝の上に、頭を乗せた彼はスヤスヤと寝息をたてている。
その寝顔は、とてもきれいで。
愛しい彼の頬にそっと触れてみる。
「すき」
そんな言葉を投げ掛けても、彼は起きない
「すきだよ」
起きない彼の寝顔を見ては、ふと思う
このまま、目覚めることなく、ずっとずっと私の側にいればいいのに、と。
「すき」
「...じゃあ、どうして泣くの?」
そう言って、彼は起き上がった。
「起きてたの?」
思わず聞けば、彼は困ったように笑う
「起きたんだよ、顔に雫が落ちてきたから」
「...ごめんなさい」
ただ、謝ることしかできなくて
そうすれば、彼は静かに首を横に振ると、"それより"と言葉を紡ぐ。
「どうして、泣いてるの?」
そう落ち着いた声で問い掛けてくる彼に、やっぱり涙はとまらなくて。そんな私を見つめる彼の手が、そっと私の頬に伸びる。
「やめて…」
そんな私の言葉に、彼は少しだけ驚いたようにして、それから、優しく目を細めて微笑む。
そして、そのまま彼の手は私の頬に触れた。
「......泣かしてるのは、俺か」
温かい彼の掌の体温に混じる、冷たいもの
私はそれが、いつも、嫌だった
どうしようもなく、泣きたくなって
"それでもいいから"と手を伸ばしたのは、私
"やめて"と耐えきれず手を振り払ったのも、私
「...もう、おわりにしようか」
そんな彼の言葉に、私は静かに頷いた。
「さよなら」
と握った彼の左手の薬指には、
嫌に輝いて見える綺麗な指環がある。
傷だらけになって、すすんだ
棘の道の先にあったのは
ほんの刹那の幸せと
耐えることのできない傷みだった
*end*