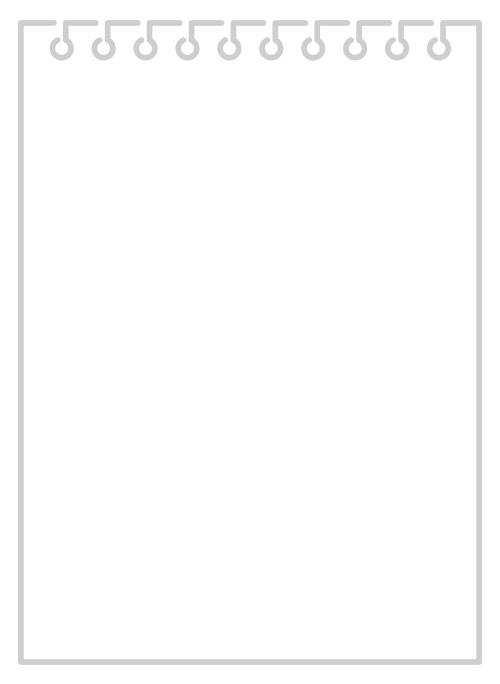* * *
「それじゃ、行ってきます。」
「帰りは何時になる?」
「んー…今日こそノー残業デー!」
「今年最後の出勤だもんね。あんまり無理しないでね。」
「うん。健人は今日バイトだっけ?夜はご飯食べに行こうか。」
「作るよ!バイトそんなに遅くまでじゃないし。」
「あ、ほんと?その方が嬉しいけど、じゃあそっちも無理のない範囲で。」
こういう些細な優しさ(本人は無自覚)がどれだけ健人にとって嬉しいことなのか、綾乃はきっと知らないだろうと思う。でも、それでいい。だからいい。
「綾乃ちゃん。」
「ん?」
軽く腕を掴んで引くと、すぽっと収まる小さな身体。自分の身体で覆うみたいにぎゅっと抱きしめるのが健人は好きだ。
「あのー…突然何?どうしたの?」
「綾乃ちゃんが可愛くて、行かせたくないなぁって。」
「…何バカなこと言ってるの?おバカさんなの?」
「綾乃ちゃんのカバンの中とかに入れたら連れて行ってもらえるのになぁ。」
「…ケージにでも入れてあげましょうか?」
「そんなに犬っぽいかなぁ、俺。」
「抱きしめた時に鼻でスンスンってするでしょ。そういうとこも犬っぽい。」
特に匂いフェチというわけではないけれど、綾乃の匂いは好きだった。安心して、ずっと抱きしめたくなる匂い。洗濯物が乾いた後に、綾乃と同じ香りが自分の衣服からもしたときにとても嬉しくなったことを思い出すと、笑みが零れた。
「おーい、何笑ってんの?」
「綾乃ちゃんの匂いが好きなんだよなぁって。」
「え、なんか臭う?」
「…多分自分じゃ気付かない匂いってやつだと思うよ。ってごめんね、もう時間だ。」
名残惜しいけれど、ゆっくりと腕から綾乃を解放した。抱きしめることは、帰ってきてからまたしようと心に決める。コートの襟をいつものように直すと、綾乃が優しく微笑んだ。
「ありがと。行ってくるね。」
「うん。」
いつもはしないけれど、今日は唐突にしたくなったから、という理由で綾乃の頬に手を伸ばした。そっと唇をその頬にのせた。
「それじゃ、行ってきます。」
「帰りは何時になる?」
「んー…今日こそノー残業デー!」
「今年最後の出勤だもんね。あんまり無理しないでね。」
「うん。健人は今日バイトだっけ?夜はご飯食べに行こうか。」
「作るよ!バイトそんなに遅くまでじゃないし。」
「あ、ほんと?その方が嬉しいけど、じゃあそっちも無理のない範囲で。」
こういう些細な優しさ(本人は無自覚)がどれだけ健人にとって嬉しいことなのか、綾乃はきっと知らないだろうと思う。でも、それでいい。だからいい。
「綾乃ちゃん。」
「ん?」
軽く腕を掴んで引くと、すぽっと収まる小さな身体。自分の身体で覆うみたいにぎゅっと抱きしめるのが健人は好きだ。
「あのー…突然何?どうしたの?」
「綾乃ちゃんが可愛くて、行かせたくないなぁって。」
「…何バカなこと言ってるの?おバカさんなの?」
「綾乃ちゃんのカバンの中とかに入れたら連れて行ってもらえるのになぁ。」
「…ケージにでも入れてあげましょうか?」
「そんなに犬っぽいかなぁ、俺。」
「抱きしめた時に鼻でスンスンってするでしょ。そういうとこも犬っぽい。」
特に匂いフェチというわけではないけれど、綾乃の匂いは好きだった。安心して、ずっと抱きしめたくなる匂い。洗濯物が乾いた後に、綾乃と同じ香りが自分の衣服からもしたときにとても嬉しくなったことを思い出すと、笑みが零れた。
「おーい、何笑ってんの?」
「綾乃ちゃんの匂いが好きなんだよなぁって。」
「え、なんか臭う?」
「…多分自分じゃ気付かない匂いってやつだと思うよ。ってごめんね、もう時間だ。」
名残惜しいけれど、ゆっくりと腕から綾乃を解放した。抱きしめることは、帰ってきてからまたしようと心に決める。コートの襟をいつものように直すと、綾乃が優しく微笑んだ。
「ありがと。行ってくるね。」
「うん。」
いつもはしないけれど、今日は唐突にしたくなったから、という理由で綾乃の頬に手を伸ばした。そっと唇をその頬にのせた。