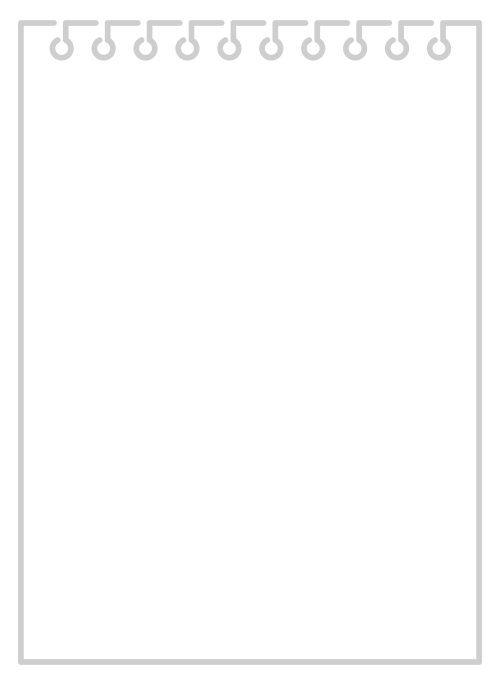* * *
ガチャリ、と鍵の開く音がした。耳が主人の帰りをいつも敏感にキャッチしてくれる。
「ただいまぁー。」
「おかえり!」
いつもなら『ごはん?お風呂?どっちが先?』と尋ねるところだが、今日はどうしても抱きしめたくて仕方がなかった。そんな気持ちを込めて、冷えたコートごとぎゅっと抱きしめた。
「…あのー…本当に今日、何かあったの?」
「何にもないよ。でもこうしたいの。」
「…ちょっと意味がわからないんですが。」
「綾乃ちゃんも嫌じゃないならぎゅってして。」
「…別に嫌じゃないけどさ。」
そう言いながら綾乃はぎゅっと大きな背中に腕を回した。本当に犬みたいに温かいから、抱きしめられるのも抱きしめるのも嫌いじゃない。むしろ冬の間はその体温に甘えたくなることがたくさんある。それでも、今日のべたつきは一体何だろうか。
「…健人?」
「なに?」
「もしかして、疲れてる?」
「え?」
綾乃は回した腕をゆっくりほどき、自分よりも15センチほど高い位置にある健人の頬に手を伸ばした。顔に疲労の色は見えない。それでもこの男は自分の疲れ、不安、色んな負の感情をぎりぎりまで見せようとはしないから。
「自覚していないところで何かあったんじゃない?」
「どうして、そう思うの?」
「やけに甘えたがるから。」
「…本当に何もないんだよ。でも何か、綾乃ちゃんが愛しくて可愛くて仕方がないんだ。朝から…無性に。」
ほんの少しだけ赤く染まる頬。綾乃が触れた部分が熱い。そんなことを思っているうちにまたしてもぎゅっと抱きしめられた。
「しいて言えば、…掃除しながら思い出しちゃった。綾乃ちゃんへの告白とか、家族のこととか。」
「…なるほど。あの告白は面白かった。」
「うわーひどい!こっちは必死だったのに!」
「そんな姿も可愛くてさ。自分にはない初々しさだーって。」
綾乃の肩口に額を乗せると、綾乃の香りが鼻をくすぐった。
ガチャリ、と鍵の開く音がした。耳が主人の帰りをいつも敏感にキャッチしてくれる。
「ただいまぁー。」
「おかえり!」
いつもなら『ごはん?お風呂?どっちが先?』と尋ねるところだが、今日はどうしても抱きしめたくて仕方がなかった。そんな気持ちを込めて、冷えたコートごとぎゅっと抱きしめた。
「…あのー…本当に今日、何かあったの?」
「何にもないよ。でもこうしたいの。」
「…ちょっと意味がわからないんですが。」
「綾乃ちゃんも嫌じゃないならぎゅってして。」
「…別に嫌じゃないけどさ。」
そう言いながら綾乃はぎゅっと大きな背中に腕を回した。本当に犬みたいに温かいから、抱きしめられるのも抱きしめるのも嫌いじゃない。むしろ冬の間はその体温に甘えたくなることがたくさんある。それでも、今日のべたつきは一体何だろうか。
「…健人?」
「なに?」
「もしかして、疲れてる?」
「え?」
綾乃は回した腕をゆっくりほどき、自分よりも15センチほど高い位置にある健人の頬に手を伸ばした。顔に疲労の色は見えない。それでもこの男は自分の疲れ、不安、色んな負の感情をぎりぎりまで見せようとはしないから。
「自覚していないところで何かあったんじゃない?」
「どうして、そう思うの?」
「やけに甘えたがるから。」
「…本当に何もないんだよ。でも何か、綾乃ちゃんが愛しくて可愛くて仕方がないんだ。朝から…無性に。」
ほんの少しだけ赤く染まる頬。綾乃が触れた部分が熱い。そんなことを思っているうちにまたしてもぎゅっと抱きしめられた。
「しいて言えば、…掃除しながら思い出しちゃった。綾乃ちゃんへの告白とか、家族のこととか。」
「…なるほど。あの告白は面白かった。」
「うわーひどい!こっちは必死だったのに!」
「そんな姿も可愛くてさ。自分にはない初々しさだーって。」
綾乃の肩口に額を乗せると、綾乃の香りが鼻をくすぐった。