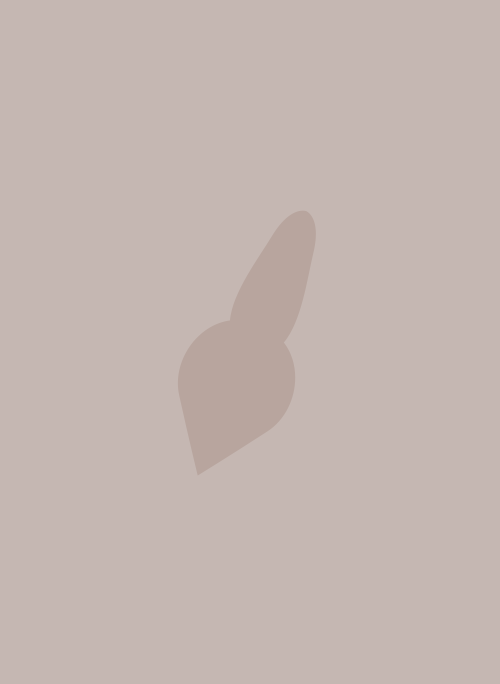「海はバカだね。」
そう言った彼は静かに笑った。
授業中の屋上。そこは私と彼以外いなく、ただ淋しいほどに碧い、空と海があった。
「なんで、ついてきたの?」
そう言って横にいる彼を睨んだ。
「何でって、それを海が言うかな?」
彼は呆れたように溜息混じりに言った。
「それは・・・・」
彼が言いたいことはわかっている。
つい数分前、私たちは科学室にいた。
隣同士でペアを組むなんて、そんなことを言いだした教師が悪い。私の斜め前の席の彼は、私の前の席の女とペアだった。前の女は、吐き気がするほどの甘ったるい声に、必要以上に彼へと触れる。実験なんて頭から消えていた。
私はどこかきっと壊れているんだろう。洗っていた筈のビーカーをいつの間にか叩き割っていたのだから。集まる視線を見ることなく私は科学室をでたのだ。何か言っている教師を背に。