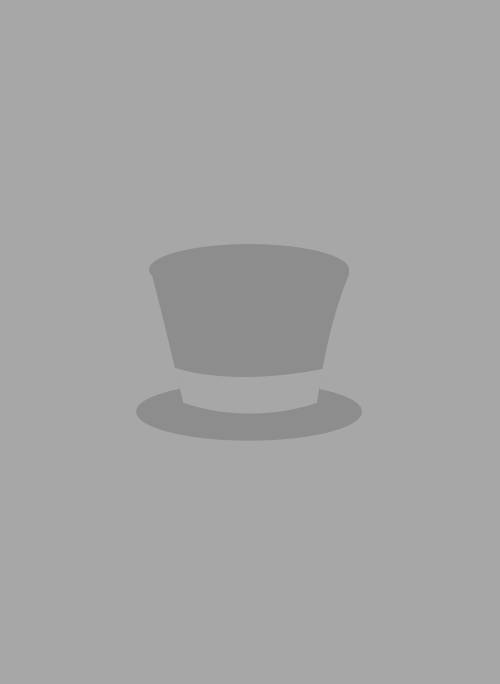「はぁ…。」
私は、机の上に肘を立てながら
深くため息をつき、
「…どうかしたの? ティアナちゃん」
彼女は私を心底、心配するように
話しかけてきた。
彼女というのは、勿論、
山吹陽彩のことであり、
私と彼女は今、この〝小さな世界〟の
中で話をしていた。
「大丈夫…。ただ少しね…。」
「…何かあったの?
私で良ければ相談に乗ろうか?」
ー彼女は本当に優しい人だと思う。
私から見ても理想的な女性だ。
しかし、今回の件について彼女に
相談するか否か、私は迷っていた。
相談をしたら、もしかしたら彼女は
私たちの関係に
疑いを持つかもしれない。
当然、私は私のことを隠し通すつもり
だけど、一番怖いのは
全てばれてしまい、彼女の曇りのない
穏やかな眼差しが、疑念と嫌悪に
満ちる、凍てついた眼差しに
変わってしまうことだった。
彼女のそんな姿を見るのは
少しどころか、かなり嫌である。
私は、机の上に肘を立てながら
深くため息をつき、
「…どうかしたの? ティアナちゃん」
彼女は私を心底、心配するように
話しかけてきた。
彼女というのは、勿論、
山吹陽彩のことであり、
私と彼女は今、この〝小さな世界〟の
中で話をしていた。
「大丈夫…。ただ少しね…。」
「…何かあったの?
私で良ければ相談に乗ろうか?」
ー彼女は本当に優しい人だと思う。
私から見ても理想的な女性だ。
しかし、今回の件について彼女に
相談するか否か、私は迷っていた。
相談をしたら、もしかしたら彼女は
私たちの関係に
疑いを持つかもしれない。
当然、私は私のことを隠し通すつもり
だけど、一番怖いのは
全てばれてしまい、彼女の曇りのない
穏やかな眼差しが、疑念と嫌悪に
満ちる、凍てついた眼差しに
変わってしまうことだった。
彼女のそんな姿を見るのは
少しどころか、かなり嫌である。