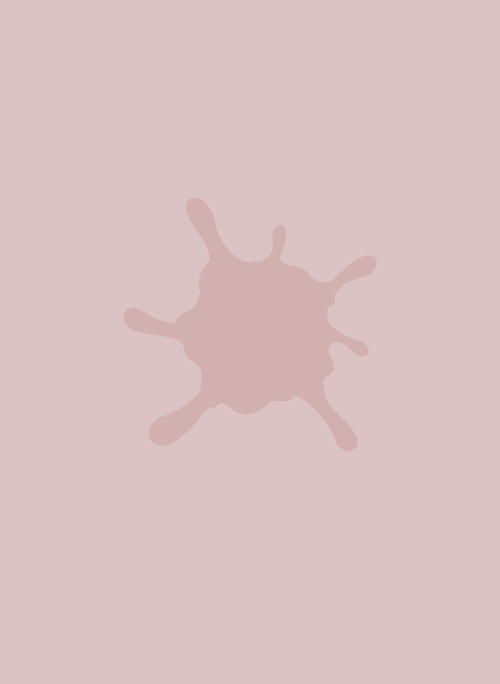「ひっ! こっちを見るな!! 呪われてしまうだろう!? 消えろ!!」
「あんな右眼、焼いてしまえばいいのに!」
「しかし、アイツの右目を傷つけた奴が死んだって聞いたことがあるぞっ!」
「まさか、ルースが帰って来ないのは……」
私が『呪われた子』となり、誰もがこの右眼を見ると呪われると信じてしまった頃。
私が6歳の頃でした。
「お前のその目のせいで母さんが死んだ! お前のせいで!! 返せ! 母さんを返せ!」
そう言って、ある男の子がナイフを持って私の前に現れました。
その男の子は、母はお前のせいで病気になったのだと、石を投げつけてきた男の子でした。
「あ……ごめんなさい。私は」
「うるさい、うるさい! お前の右眼のせいで死んだんだ! そんな目なんてくり抜いてやる!」
「……っ!」
男の子は私を押し倒して、右眼を覆っていた黒い布をバッと取り去ります。
随分久しぶりにみる光に眼が眩み、前が良く見えません。
それでも頬に感じるヒヤリとした感覚に、男の子がナイフを右眼に当てたと分かりました。
恐怖で身体が固まり、ただ男の子の眼を見つめることしかできません。
ーーその眼は暗く濁っていて……けれど、深い悲しみを抱えているように見えました。
ごめんなさい。
私の右眼のせいで、泣いているんですね。
あなたの言う通りに……もし、右眼をくり抜いたら、貴方は許してくれますか?
お父さんとお母さんは私を受け入れてくれますか?
ーーだったらくり抜いてもいいかなぁ?
もう、独りぼっちは嫌なの。
「あんな右眼、焼いてしまえばいいのに!」
「しかし、アイツの右目を傷つけた奴が死んだって聞いたことがあるぞっ!」
「まさか、ルースが帰って来ないのは……」
私が『呪われた子』となり、誰もがこの右眼を見ると呪われると信じてしまった頃。
私が6歳の頃でした。
「お前のその目のせいで母さんが死んだ! お前のせいで!! 返せ! 母さんを返せ!」
そう言って、ある男の子がナイフを持って私の前に現れました。
その男の子は、母はお前のせいで病気になったのだと、石を投げつけてきた男の子でした。
「あ……ごめんなさい。私は」
「うるさい、うるさい! お前の右眼のせいで死んだんだ! そんな目なんてくり抜いてやる!」
「……っ!」
男の子は私を押し倒して、右眼を覆っていた黒い布をバッと取り去ります。
随分久しぶりにみる光に眼が眩み、前が良く見えません。
それでも頬に感じるヒヤリとした感覚に、男の子がナイフを右眼に当てたと分かりました。
恐怖で身体が固まり、ただ男の子の眼を見つめることしかできません。
ーーその眼は暗く濁っていて……けれど、深い悲しみを抱えているように見えました。
ごめんなさい。
私の右眼のせいで、泣いているんですね。
あなたの言う通りに……もし、右眼をくり抜いたら、貴方は許してくれますか?
お父さんとお母さんは私を受け入れてくれますか?
ーーだったらくり抜いてもいいかなぁ?
もう、独りぼっちは嫌なの。