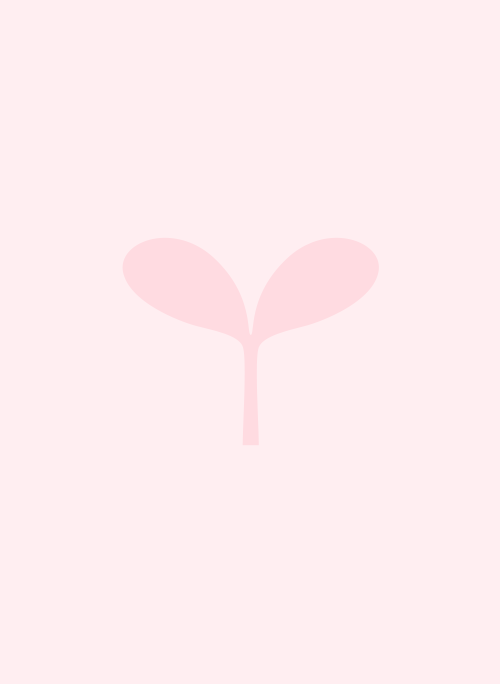街灯の、今にも消えてしまいそうな頼りない明かりに、蛾や虫たちが集まっている。
その下を、酒に酔った男がふらふらと歩いていた。
その表情は、酔っているのか僅かに赤い。足取りも少し危ういようだ。
「ったく、やってられるかってんだ!」
悪態をつきながら、夜道を歩いている。
どうやら仕事がうまくいかず、やけ酒したようだった。
「―――?」
何か違和感を感じて足を止める。
どこからか、鼻を突くような腐敗臭。
目を凝らしてあたりに視線を彷徨わせる。
もしや……?
街灯の明かりの届かない闇の中から、べちゃ、べちゃ、と規則正しい音が近づいてくる。
見えない恐怖に背筋が凍り、やみくもに走り出す。
その先には―――。
「う、うわ!」
人であって人でない、腐った体から悪臭を放つ死人(ゾンビ)の姿。
足がすくみ、腰が砕け、その場に座り込み、恐怖で呼吸は早くなる。
ずるずると足を引きづりながら、ゆっくりと近づいてくるそれは、顔の半分が白骨化していて、口からは錆びたような茶色の液体を滴らせている。
腐敗臭がきつくなる。
大きく見開かれた目が、それから視線を外せないでいた。
「ひっ……!」
迫り繰るそれに、体の震えが止まらず、立ち上がって逃げることもままならない。
恐怖におののきながらも、手に持っていたカバンを投げた。
びちゃっ
水っぽい音と共に、腐った肉片が目の前に飛び散る。
痛くも痒くもないのか、それとも今更体の一部を失おうとどうでもいいのか、そのまま男を狙って手を伸ばす。
「やめろ、来るなぁ!」
ぬるっとしたゾンビの手が男の首にかかる。それは体温などまったく感じない、ウジ虫の蠢めく腕。
その腕を離そうと反射的に伸ばした手がゾンビの腕を掴んだ。
ズルッ。
掴んだ先から溶けたような肉がこぼれ落ち、それを掴んでいた手も滑るように宙へ投げ出される。
「ぐ、はぁ……!」
掴まれた首に力がかかる。苦痛に顔が歪められた。この腕のどこにそのような力があるというのだろう。
ブツン! という鈍い音と共に苦しげに歪む顔も、一瞬で吹き飛ぶ。
胴と頭が二つに離された。力を失った胴はそのまま地に倒れ、首はゴロゴロと転がり落ちる。
そして、後には流れ出す血を旨そうにぴちゃぴちゃと舐めるゾンビの姿。
血の匂いを嗅ぎつけ、どこからともなく集まってくるゾンビたち。
彼らの食事が始まる―――。
世界は日一日と破滅へ近づいていく。
人々はこのまま絶望の日々を過ごすことしかできないのか―――?
胴と切り離された首が恨めしげに闇を睨んでいた……。
その下を、酒に酔った男がふらふらと歩いていた。
その表情は、酔っているのか僅かに赤い。足取りも少し危ういようだ。
「ったく、やってられるかってんだ!」
悪態をつきながら、夜道を歩いている。
どうやら仕事がうまくいかず、やけ酒したようだった。
「―――?」
何か違和感を感じて足を止める。
どこからか、鼻を突くような腐敗臭。
目を凝らしてあたりに視線を彷徨わせる。
もしや……?
街灯の明かりの届かない闇の中から、べちゃ、べちゃ、と規則正しい音が近づいてくる。
見えない恐怖に背筋が凍り、やみくもに走り出す。
その先には―――。
「う、うわ!」
人であって人でない、腐った体から悪臭を放つ死人(ゾンビ)の姿。
足がすくみ、腰が砕け、その場に座り込み、恐怖で呼吸は早くなる。
ずるずると足を引きづりながら、ゆっくりと近づいてくるそれは、顔の半分が白骨化していて、口からは錆びたような茶色の液体を滴らせている。
腐敗臭がきつくなる。
大きく見開かれた目が、それから視線を外せないでいた。
「ひっ……!」
迫り繰るそれに、体の震えが止まらず、立ち上がって逃げることもままならない。
恐怖におののきながらも、手に持っていたカバンを投げた。
びちゃっ
水っぽい音と共に、腐った肉片が目の前に飛び散る。
痛くも痒くもないのか、それとも今更体の一部を失おうとどうでもいいのか、そのまま男を狙って手を伸ばす。
「やめろ、来るなぁ!」
ぬるっとしたゾンビの手が男の首にかかる。それは体温などまったく感じない、ウジ虫の蠢めく腕。
その腕を離そうと反射的に伸ばした手がゾンビの腕を掴んだ。
ズルッ。
掴んだ先から溶けたような肉がこぼれ落ち、それを掴んでいた手も滑るように宙へ投げ出される。
「ぐ、はぁ……!」
掴まれた首に力がかかる。苦痛に顔が歪められた。この腕のどこにそのような力があるというのだろう。
ブツン! という鈍い音と共に苦しげに歪む顔も、一瞬で吹き飛ぶ。
胴と頭が二つに離された。力を失った胴はそのまま地に倒れ、首はゴロゴロと転がり落ちる。
そして、後には流れ出す血を旨そうにぴちゃぴちゃと舐めるゾンビの姿。
血の匂いを嗅ぎつけ、どこからともなく集まってくるゾンビたち。
彼らの食事が始まる―――。
世界は日一日と破滅へ近づいていく。
人々はこのまま絶望の日々を過ごすことしかできないのか―――?
胴と切り離された首が恨めしげに闇を睨んでいた……。