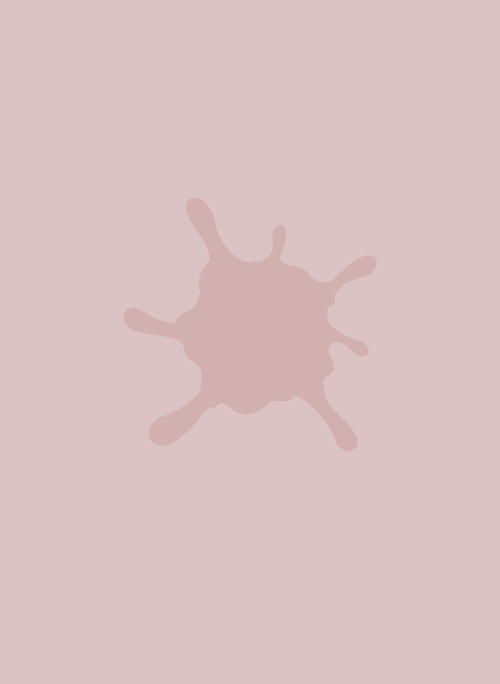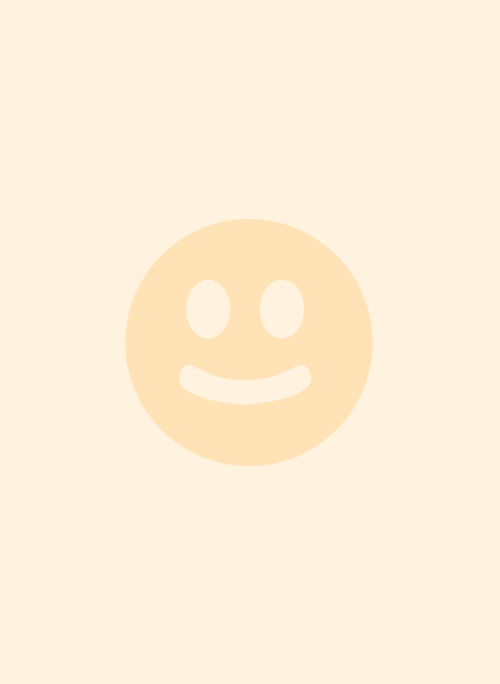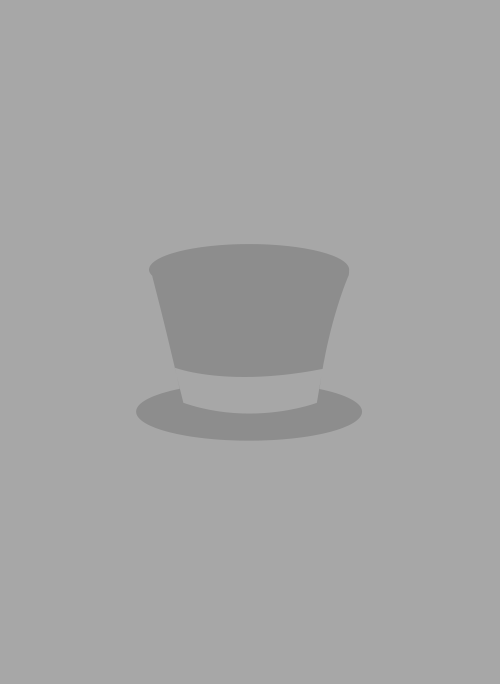ジャンル:ホラー
テーマ:親子の絆
制限:三人称視点・固有名詞の使用禁止
文字数1500~3000
というお題で書かせていただいた作品です。
◆ ◆ ◆ ◆
人は異質のものを無意識に拒む。しかし、異質のものへの興味は絶えない。そんな、相反する感情が存在した時、異質のものを見てみたいと思う者がいる。
あの踏切には親子の霊がいる。遮断機が降りた時に向かい側に誰もいないと見えるという。その霊は不気味な笑みを浮かべると、電車の通過とともに消えるというのだ。
そんな噂を男子生徒がはじめた途端、ある女子が眉をひそめた。
女子はすぐに帰宅の準備をして、逃げるように教室を出た。彼女がそこまで親子の霊の話を嫌悪するのは何故か。それは、彼女にとって嫌なことを想起させるものだったからだ。
彼女には二歳年上の姉がいた。当然、姉相手に駆けっこはいつも負け。絵を書いても自分のほうが下手。母には「妹なんだから負けるのは当たり前よ」と言われ続けていた。
それでも姉は得意とならずに優しかった。その姉が、あの日だけは違ったのだ。
「まだ自転車乗れないでしょ。だから今日はお母さんと私だけで行くの。すぐに帰ってくるから待ってて」
その時、姉は小学一年生。補助輪なしで自転車が乗れるようになったばかりであった。
「自転車に乗れるようになったら三人で行きましょう。だから今日は、あなたはお留守番」
母についていっては駄目なのかと訊くと、姉と同じように待っていろという。答えを聞いて、彼女は仲間はずれにされたと思った。
たった二年遅く生まれてきただけなのに、何でお母さんは、お姉ちゃんばかり見ているのと。そのため、言ってしまったのだ。
「お母さんも、お姉ちゃんも大嫌い。いなくなっちゃえ」と。
結果、本当にいなくなってしまった。しかも二人一緒に。
踏切を渡っている最中に、姉が体勢を崩して脱輪したらしい。先を走っていた母は姉の異常に気づくのが遅れた。母が気づいて姉のもとへ向かった時には遮断機は完全に降りていて、電車も迫っていたという。母は周りの人の制止を聞くことなく遮断機を潜り、姉の手を取り、そこで轢かれた。
彼女が母と姉に対面したのは、霊安室だった。奇しくも二人の命日と彼女の誕生日が重なってしまったのだった。
「すぐに帰ってくるから待ってて」という、姉との約束は破られ、二人は自力で帰ってくることはなかった。
母は離婚していたため、彼女は母方のほうに引き取られた。祖母は親以上とも思えるような愛情を注いでくれた。しかし、それでも彼女には空虚感が存在した。
もう一度、母に優しい言葉をかけてほしいと思っていた。そして、伝えたかった。大嫌いといったのは嘘で、大好きだったということを。
しかし、彼女は踏切に行こうと思う度に母の言葉を思い出すのだ。
「三人でいきましょう」それが、今では違う意味になってはいないだろうかと。
ふと、彼女は顔をあげる。いつもとは違う帰り道。いつの間にか、踏切に向かっていたことに彼女は気づいた。あまり暑くもないのに、緊張で汗が噴き出てくる。
誰もが思うだろう。何故、行かないと決めていた踏切に、彼女はきてしまったのであろうかと。それは、空虚感を埋めたいと思う願望なのか、あるいは――
どこからか吹いた風が彼女の長い黒髪を揺らす。小さい頃は姉と同じようにショートカットだったが、二人が他界したのを切っ掛けに髪を切るのをやめていた。
線路の向こう側には誰もいない。電車がくるという警告音とともに遮断機が降りてくる。
まさに男子生徒が教室で語っていた、親子の霊が現れるそのままの状況だ。
彼女の心臓の鼓動は、警告音に合わせるかのように鳴り響いていた。同時に金縛りにあったように一歩も動けない。
そのため、現場を直視することになっていた。
途端に彼女の腕に鳥肌が立つ。急激に周囲の気温が下降したのだ。キイという耳障りな金属音が響き渡る。それが自転車を引き摺る音と知るのに、時間は要さなかった。
季節はずれの霧が踏切内だけ発生している。その霧の中にふたつの影を確認できた。それが異質のものであるというのは一目瞭然だった。何故なら、向こうの景色が透き通って見えたからだ。
異質のものの姿を確認して彼女の鼓動は更に高まった。見間違えるわけがない。彼女の母と姉だった。
「いや、お願い。帰らせて……」
震えた声は遠くまで通ることはなく虚しく消えた。彼女の願いとは逆に母と姉の影が少しずつ近づいてくる。
そして、遮断機越しで生前とはまるで違う、蒼白の母の手が差し出された。
「さあ、三人でいきましょう」
くぐもった声のはずなのに、彼女は母の言葉をはっきりと聞いていた。その隣では、彼女が大きくなったのとは対照的に成長していない姉が笑っている。
手を出すつもりは彼女にはなかった。しかし、意思を反して手が差し出されてしまう。
姉の手も差し出され、三人の手が重なった。半透明の冷たい手。電車が接近してくる車輪の音が聞こえてくる。
彼女の目の前には懐かしい母の顔。優しかった姉の笑顔がある。たとえ、この世のものではなくても母と姉なのだ。
「いなくなっちゃえなんて言って、ごめんなさい!」
ようやく、そこで彼女は二人に本心を告げることができた。その答えを聞いて、母と姉が微笑んだ。電車はすぐそこだ。彼女は二人に連れて行かれると思い、覚悟して目を閉じた。その時だ。
「お誕生日おめでとう。うちであなたを驚かせるつもりだったのだけど、ケーキ見つかっちゃたわね。さあ、三人で帰りましょうか」
「えっ?」
母の答えに彼女は驚きの声をあげた。母と姉だけで出て行った理由。留守番と言われた理由を何となくわかってしまったからだ。
「じゃあ、私はずっと誤解して……お母さんとお姉ちゃんが私をおいて出ていったのは」
「今日、誕生日のお祝いと一緒に言うつもりだったのよ。あなたの名前――の由来はね」
電車が迫る音で母の声がかき消される。彼女が母の声を聞き取ろうと、身をのり出そうとした瞬間、ほぼ同時に電車が通過していた。
吹き抜ける風の勢いで、彼女は数歩後退する。彼女が顔をあげた時には、もうそこに母と姉の姿はなかった。彼女の胸の中にあった空虚感が消えた代わりに、涙があふれ出る。
「お母さん、私を生んでくれてありがとう。お姉ちゃん大好き……」
流れ出る涙を手のひらで拭き、彼女はゆっくりと歩き出す。
彼女は気づいただろうか。ふたつの影が、うちに帰るまでついてきていたことを。
自分の影が母の身長を越していたということを。
踏切にいる親子の霊を見たという話は、その日を境に語られなくなっていたのだった。
テーマ:親子の絆
制限:三人称視点・固有名詞の使用禁止
文字数1500~3000
というお題で書かせていただいた作品です。
◆ ◆ ◆ ◆
人は異質のものを無意識に拒む。しかし、異質のものへの興味は絶えない。そんな、相反する感情が存在した時、異質のものを見てみたいと思う者がいる。
あの踏切には親子の霊がいる。遮断機が降りた時に向かい側に誰もいないと見えるという。その霊は不気味な笑みを浮かべると、電車の通過とともに消えるというのだ。
そんな噂を男子生徒がはじめた途端、ある女子が眉をひそめた。
女子はすぐに帰宅の準備をして、逃げるように教室を出た。彼女がそこまで親子の霊の話を嫌悪するのは何故か。それは、彼女にとって嫌なことを想起させるものだったからだ。
彼女には二歳年上の姉がいた。当然、姉相手に駆けっこはいつも負け。絵を書いても自分のほうが下手。母には「妹なんだから負けるのは当たり前よ」と言われ続けていた。
それでも姉は得意とならずに優しかった。その姉が、あの日だけは違ったのだ。
「まだ自転車乗れないでしょ。だから今日はお母さんと私だけで行くの。すぐに帰ってくるから待ってて」
その時、姉は小学一年生。補助輪なしで自転車が乗れるようになったばかりであった。
「自転車に乗れるようになったら三人で行きましょう。だから今日は、あなたはお留守番」
母についていっては駄目なのかと訊くと、姉と同じように待っていろという。答えを聞いて、彼女は仲間はずれにされたと思った。
たった二年遅く生まれてきただけなのに、何でお母さんは、お姉ちゃんばかり見ているのと。そのため、言ってしまったのだ。
「お母さんも、お姉ちゃんも大嫌い。いなくなっちゃえ」と。
結果、本当にいなくなってしまった。しかも二人一緒に。
踏切を渡っている最中に、姉が体勢を崩して脱輪したらしい。先を走っていた母は姉の異常に気づくのが遅れた。母が気づいて姉のもとへ向かった時には遮断機は完全に降りていて、電車も迫っていたという。母は周りの人の制止を聞くことなく遮断機を潜り、姉の手を取り、そこで轢かれた。
彼女が母と姉に対面したのは、霊安室だった。奇しくも二人の命日と彼女の誕生日が重なってしまったのだった。
「すぐに帰ってくるから待ってて」という、姉との約束は破られ、二人は自力で帰ってくることはなかった。
母は離婚していたため、彼女は母方のほうに引き取られた。祖母は親以上とも思えるような愛情を注いでくれた。しかし、それでも彼女には空虚感が存在した。
もう一度、母に優しい言葉をかけてほしいと思っていた。そして、伝えたかった。大嫌いといったのは嘘で、大好きだったということを。
しかし、彼女は踏切に行こうと思う度に母の言葉を思い出すのだ。
「三人でいきましょう」それが、今では違う意味になってはいないだろうかと。
ふと、彼女は顔をあげる。いつもとは違う帰り道。いつの間にか、踏切に向かっていたことに彼女は気づいた。あまり暑くもないのに、緊張で汗が噴き出てくる。
誰もが思うだろう。何故、行かないと決めていた踏切に、彼女はきてしまったのであろうかと。それは、空虚感を埋めたいと思う願望なのか、あるいは――
どこからか吹いた風が彼女の長い黒髪を揺らす。小さい頃は姉と同じようにショートカットだったが、二人が他界したのを切っ掛けに髪を切るのをやめていた。
線路の向こう側には誰もいない。電車がくるという警告音とともに遮断機が降りてくる。
まさに男子生徒が教室で語っていた、親子の霊が現れるそのままの状況だ。
彼女の心臓の鼓動は、警告音に合わせるかのように鳴り響いていた。同時に金縛りにあったように一歩も動けない。
そのため、現場を直視することになっていた。
途端に彼女の腕に鳥肌が立つ。急激に周囲の気温が下降したのだ。キイという耳障りな金属音が響き渡る。それが自転車を引き摺る音と知るのに、時間は要さなかった。
季節はずれの霧が踏切内だけ発生している。その霧の中にふたつの影を確認できた。それが異質のものであるというのは一目瞭然だった。何故なら、向こうの景色が透き通って見えたからだ。
異質のものの姿を確認して彼女の鼓動は更に高まった。見間違えるわけがない。彼女の母と姉だった。
「いや、お願い。帰らせて……」
震えた声は遠くまで通ることはなく虚しく消えた。彼女の願いとは逆に母と姉の影が少しずつ近づいてくる。
そして、遮断機越しで生前とはまるで違う、蒼白の母の手が差し出された。
「さあ、三人でいきましょう」
くぐもった声のはずなのに、彼女は母の言葉をはっきりと聞いていた。その隣では、彼女が大きくなったのとは対照的に成長していない姉が笑っている。
手を出すつもりは彼女にはなかった。しかし、意思を反して手が差し出されてしまう。
姉の手も差し出され、三人の手が重なった。半透明の冷たい手。電車が接近してくる車輪の音が聞こえてくる。
彼女の目の前には懐かしい母の顔。優しかった姉の笑顔がある。たとえ、この世のものではなくても母と姉なのだ。
「いなくなっちゃえなんて言って、ごめんなさい!」
ようやく、そこで彼女は二人に本心を告げることができた。その答えを聞いて、母と姉が微笑んだ。電車はすぐそこだ。彼女は二人に連れて行かれると思い、覚悟して目を閉じた。その時だ。
「お誕生日おめでとう。うちであなたを驚かせるつもりだったのだけど、ケーキ見つかっちゃたわね。さあ、三人で帰りましょうか」
「えっ?」
母の答えに彼女は驚きの声をあげた。母と姉だけで出て行った理由。留守番と言われた理由を何となくわかってしまったからだ。
「じゃあ、私はずっと誤解して……お母さんとお姉ちゃんが私をおいて出ていったのは」
「今日、誕生日のお祝いと一緒に言うつもりだったのよ。あなたの名前――の由来はね」
電車が迫る音で母の声がかき消される。彼女が母の声を聞き取ろうと、身をのり出そうとした瞬間、ほぼ同時に電車が通過していた。
吹き抜ける風の勢いで、彼女は数歩後退する。彼女が顔をあげた時には、もうそこに母と姉の姿はなかった。彼女の胸の中にあった空虚感が消えた代わりに、涙があふれ出る。
「お母さん、私を生んでくれてありがとう。お姉ちゃん大好き……」
流れ出る涙を手のひらで拭き、彼女はゆっくりと歩き出す。
彼女は気づいただろうか。ふたつの影が、うちに帰るまでついてきていたことを。
自分の影が母の身長を越していたということを。
踏切にいる親子の霊を見たという話は、その日を境に語られなくなっていたのだった。