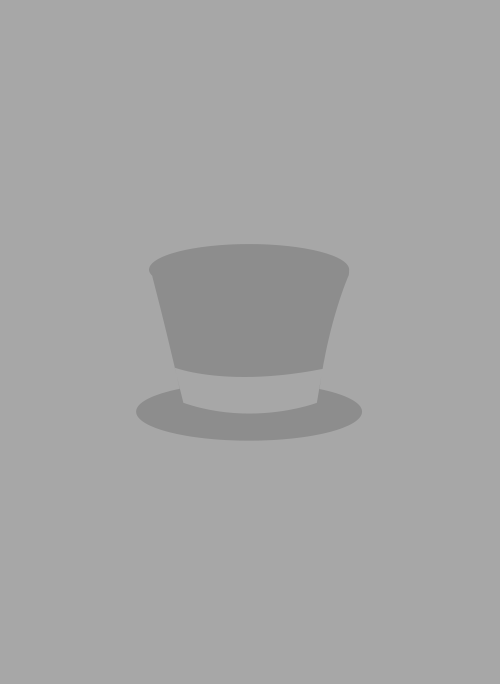依頼人の女性と男の子が帰ってから、約2時間が経つ。その間、私はずっとゼストの部屋にいた。
私が座っている目の前には、ゼストがいる。
頭にも腕にも足にも、どこを見ても包帯が巻かれているゼスト。顔にはたくさんの絆創膏。そして、彼はまだ目を開けない。
「…………ごめん」
私の口から出てくるのはその言葉だけ。私を守ってくれた幼馴染への罪悪感と後悔しか残っていない。
……とくん、とくん。
こういうときになってもなお、その音は鳴り止んでくれない。
私がなんとかしなきゃいけない。こんな怪我をさせたのは私なんだ。私があのままじっとしていれば、もしかするともっと軽傷で済んだかもしれないのだから。
「ゼスト入るよ」
扉の外からそんな声が聞こえ、その後すぐに男の人が言葉通り入って来た。
深い黒色の髪。その前髪は長く、分け方の関係により右目が隠れている。その人自身の目はいつも瞼が重そうな雰囲気で、性格も口調も穏やかだ。その人の名前は、ナイトさん。ゼストより一つ年上の20歳。
私がこの前ちらっと説明した、アスタさんとソウヤさんを除く20歳を迎えた三人のうちの一人である。
ナイトさん、と私の呟く声に反応する彼。
「お、ルナもいたの」
「……はい」
ゼストがこんな状態なのだ、入ってきてすぐ気づいてくださいなんて言っている場合ではない。
「私が怪我させちゃったので」
なんとか明るく振る舞おうとするけれどもうまく笑えない。このままゼストが目を開けれくれなかったら。このまま遠くへ行ってしまったら。
そんなことばかりが頭に浮かぶ。
「俺が今から言うことは全部俺の独り言だから」
別に聞き流してくれたんでいい、とゼストを見つめながら少し真剣な表情で突然そう言うナイトさん。そんな顔で言われたら、聞き流そうにも流せない。でもきっとこれは、ナイトさんなりの気遣いなのだろう。
「こいつは不器用な奴だよ。たぶん、俺やルナたちが思ってるよりもずっと不器用だ。こいつといるとめんどくさいことばっかりだよ」
「……はい」
私はただ、頷きながら聞いていた。聞き流す理由が見つからなかった。ナイトさんは続ける。
「こいつも結構なバカだから、そう簡単には死なないさ。ケロッと目を覚まして、何事もなかったみたいな態度で図々しく笑うと思うよ。まあ……」
そこで少し間を空けて、ナイトさんはまた口を開いた。
「ルナを置いて遠くへは行かないだろうから、こいつが起きたら愚痴の一つや二つ、言ってやればいいよ」
……とくん、とくん。
たぶんナイトさんの言っていることは、茶化しでも何でもない。真実だと思う。今考えれば確かにそうだった。
私がどこに行こうとゼストは必ずそばにいた。それはもうしつこいくらい。頼んでもないのに。
でも、それがなんだか嬉しかったり心地よかったりしている自分がいたことも事実。
……とくん、とくん。
「……そうですね」ほんの少しだけ、自然に笑えた気がした。