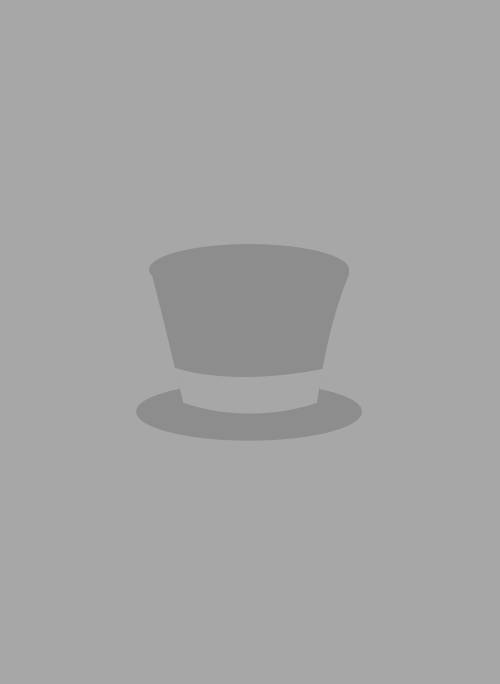あれから一ヶ月が経つ。ゆっくりだけど私はいつもの自分へとようやく戻り始め、そして今、現在進行中でゼストの部屋の前にいるのだった。
ゼストとはまだ気まずい空気のままである。この状態をどうにかして早く直したいところなのだけれど、なかなかうまくいかないのが現実。
まぁあんなこと言っちゃったら、そりゃ嫌われるのも当然だよね……――。
――何が“幼馴染なめんな”よ! あんたもみんなと同じじゃん! 私のことなんか全然見てくれてない!
そうじゃないってことは、私が一番よく知っているはずだった。いつもいつも、声をかけてくれるのは決まってゼストだった。だから私のことを気にしているとか気にしていないとか、そういうことはどうだってよくて、どちらにせよ私に声をかけるのは必ずゼストだった。
ゼストには私が見えているのだ。冷静に考えればその結論に簡単にたどり着く。でもあのときの私は普通じゃなかったから、その答えを自分の中で認めるだけでも怖かった。
そのうち忘れられてしまうかもしれない、という恐怖感があったのだ。
ちゃんと話せばわかってもらえるだろうか。……いやあんなこと言っておいてそんな都合のいい話があるわけがない。
ゼストの部屋の前に立ち、自分の中でそのような葛藤を繰り広げていると――。
「人の部屋の前で何やってんだお前」
この中にいるはずだと思っていた部屋の主――ゼストがやってきた。あっちから来るなんて想定外。
言葉を声に出そうとするけれども、喉の奥で引っかかって出てこない。
やっぱり何でもない。心の中でそう呟いてその場を離れようとした。しかしその足はゼストが私の腕をがしっと掴んだことにより止められてしまった。その手に力を込めているのか、掴まれている腕が痛みを訴えている。こりゃ逃げられないな。
「俺に用があんだろ」
低いトーンでそう言うゼスト。どうしてこういうときだけ鋭くなるんだこいつは。
だけどまぁ、あっちから声をかけてもらえたからまだよかった。あのままだったらきっと私から言い出す機会を逃していたと思う。たぶん、ちゃんと言える。
私はゼストの部屋に入り、向かい合って座った。
……とくん、とくん。
この音の正体は、依然としてわからないままである。