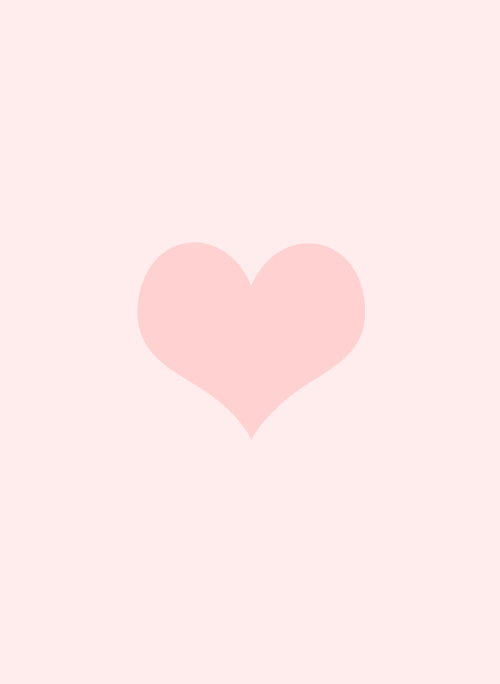さらに数か月後、先生は新しい女の子を連れてきた。見るからに昔の私。
だっさい髪型で、変な服のとりあわせ。でも笑顔がステキな女の子だ。
「あの子が次のターゲットっていうわけですかね」
私は少しあきれたように松原さんに言った。
「そうね。また先生のお気に召すように、つくりかえられるんじゃない?」
「またあのイケメンボイスでね」
「イケメンボイス?何言ってるの?先生の声、そんな風に聞こえるの?笑える」
あれ?松原さんは先生のイケメンボイス聞いたことないのだろうか。
今でも耳もとに残ってる先生の男の声。
……思い出しただけで、心臓がぎゅってなるのに。
新しい女の子は美容室に連れていかれ、髪を切られたと泣いて帰ってきた。
すっごくステキになったのに、こんなところやってられないと、その日のうちに辞表を書いてやめてしまった。
「よくあることよ」と笑う先輩たち。その日、先生は一度も部屋から出てこなかった。
閉店後、戸締り当番が私だったので、先生に部屋から出てもらおうと、声をかけた。
「すいません。そろそろ戸締りしたいのですが……」
返事がない。
「すいません」
「……山川か……入れ」
久しぶりに聞いた先生のイケメンボイスだった。
「し、失礼します」
薄暗い部屋に書きかけのデザインが散らばっていた。
「あいつのためにこんなに書いたのに、やめやがった」
先生は向こうを向いたままだった。
「あの……」
「こっちこいよ」
振り向いた先生は、いつもオネエなのが信じられないくらい、男の顔だった。
私は少し警戒した。
この人、本当はオネエじゃない。いつもオネエのふりをしているだけだと確信したからだ。
「山川」
その反則のイケメンボイスに、体が勝手に反応する。
「この人は別に私じゃなくてもいいんだ」頭では分かっているのに心臓が締め付けられる。
先生のそばに行きたい。あの眼でもう一度じっと私の顔を見て。
そばに行くと、先生は私の頬に手を伸ばした。ドキドキが止まらない。
先生が私に近づいてくる。私の頬に先生の掌が優しく触れる。
心臓が口から飛び出しそうで、私はぎゅっと目をつぶった。
「……お前のほっぺ、ホントやわらけーな」
雰囲気ぶち壊しのその声に驚いて、パッと目を開けると先生はにやっと笑った。
「なに?キスでもされるかと思った?」
私は恥ずかしくなって下を向いて、首をふった。
「このほっぺが癒されるんだよな」
私のほっぺをふにっとつまむと、先生は私から少し離れ、後ろを向いた。
私は恥ずかしくて、恥ずかしくて、その思いを怒りに変えた。
「誰にでもこんなことするんですか?それに、どうしてオネエのフリなんてしてるんですか?あなたが何を考えているのか全然わからないです!」
「何言ってるの~、私はオネエよ~」
腹が立って、先生を突き飛ばし、店の鍵を置いて帰った。
だっさい髪型で、変な服のとりあわせ。でも笑顔がステキな女の子だ。
「あの子が次のターゲットっていうわけですかね」
私は少しあきれたように松原さんに言った。
「そうね。また先生のお気に召すように、つくりかえられるんじゃない?」
「またあのイケメンボイスでね」
「イケメンボイス?何言ってるの?先生の声、そんな風に聞こえるの?笑える」
あれ?松原さんは先生のイケメンボイス聞いたことないのだろうか。
今でも耳もとに残ってる先生の男の声。
……思い出しただけで、心臓がぎゅってなるのに。
新しい女の子は美容室に連れていかれ、髪を切られたと泣いて帰ってきた。
すっごくステキになったのに、こんなところやってられないと、その日のうちに辞表を書いてやめてしまった。
「よくあることよ」と笑う先輩たち。その日、先生は一度も部屋から出てこなかった。
閉店後、戸締り当番が私だったので、先生に部屋から出てもらおうと、声をかけた。
「すいません。そろそろ戸締りしたいのですが……」
返事がない。
「すいません」
「……山川か……入れ」
久しぶりに聞いた先生のイケメンボイスだった。
「し、失礼します」
薄暗い部屋に書きかけのデザインが散らばっていた。
「あいつのためにこんなに書いたのに、やめやがった」
先生は向こうを向いたままだった。
「あの……」
「こっちこいよ」
振り向いた先生は、いつもオネエなのが信じられないくらい、男の顔だった。
私は少し警戒した。
この人、本当はオネエじゃない。いつもオネエのふりをしているだけだと確信したからだ。
「山川」
その反則のイケメンボイスに、体が勝手に反応する。
「この人は別に私じゃなくてもいいんだ」頭では分かっているのに心臓が締め付けられる。
先生のそばに行きたい。あの眼でもう一度じっと私の顔を見て。
そばに行くと、先生は私の頬に手を伸ばした。ドキドキが止まらない。
先生が私に近づいてくる。私の頬に先生の掌が優しく触れる。
心臓が口から飛び出しそうで、私はぎゅっと目をつぶった。
「……お前のほっぺ、ホントやわらけーな」
雰囲気ぶち壊しのその声に驚いて、パッと目を開けると先生はにやっと笑った。
「なに?キスでもされるかと思った?」
私は恥ずかしくなって下を向いて、首をふった。
「このほっぺが癒されるんだよな」
私のほっぺをふにっとつまむと、先生は私から少し離れ、後ろを向いた。
私は恥ずかしくて、恥ずかしくて、その思いを怒りに変えた。
「誰にでもこんなことするんですか?それに、どうしてオネエのフリなんてしてるんですか?あなたが何を考えているのか全然わからないです!」
「何言ってるの~、私はオネエよ~」
腹が立って、先生を突き飛ばし、店の鍵を置いて帰った。