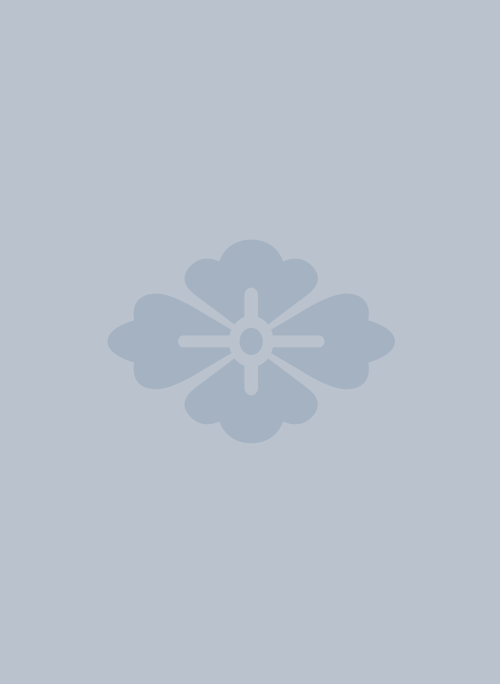「イギリス人じゃありませんよ、私は。フランス人です」
そんな彼の心の声が聞こえたのか、彼女ははっきりそう言った。
「だよな」
ジョルジュがそう言うと、シモーヌは少し首を傾げながら尋ねた。
「ジョルジュさんは、フランスの味方なのですか?」
「まぁ、手当がよければイギリスにつくこともあるが、基本的にはフランスだな。ここで生まれ育ったから、ここを守りたいって気持ちもあるし」
「そうですか」
「お前は?」
「私もですよ」
そう答えると、シモーヌは微笑んだ。
「気が合いそうですね」
「そ、そうか?」
そう聞き返すジョルジュの顔は、少し赤かった。
「じゃあ、奥で少し打ち合わせします?」
「まぁ、そこまで言うなら、してやってもいいが……」
そう言って、少しわざとらしい咳払いをするジョルジュの顔は真っ赤だった。
「では……」
そう言って彼女が奥の席を手で示した時だった。
「みんなでよってたかって、何の騒ぎだい?」
そう言いながら、女性にしては少し筋肉質の赤毛の女性が声をかけてきたのは。
「カレン姐(ねぇ)さん!」
集まっていた男達の一人が思わずその名を呼ぶと、シモーヌの後ろからついていこうとしていたジョルジュもそちらを振り返った。
「姐さん……。そいつも一緒なんだ」
ジョルジュが彼女の傍に寄りそうように立っている、東洋人にしては背の高い男をチラリと見た。
「あれ? 新入りかい?」
そんな彼をチラリと見ると、カレンは彼よりもその傍にいる背の高い黒髪の少女が気になったらしく、そう声をかけた。
「はい、シモーヌと申します。バートさんやジョルジュさん達にお世話になってます」
彼女がそう言って軽く膝を曲げて挨拶すると、カレンは頷いた。
「ああ、バートとマルクは、面倒見がよくて、優しいからね。分からないことがあったら、色々教えてもらうんだよ」
「はい」
ニコリとしながらそう答えるシモーヌに、カレンは頷いた。
が、ジョルジュは何故か不機嫌そうだった。
「おや、機嫌悪そうだね? 又、モメてるのかい?」
そんな彼に近付き、ニヤリとしながらカレンがそう尋ねると、むっとした表情のまま、彼は言った。顔を見ずに。
「だって、その言い方じゃ、兄貴やバートは頼りになっても、俺は頼りにならないみたいじゃないですか」
「まぁ、今みたいに他の傭兵仲間に囲まれるようじゃね」
「それは、もう解決しましたよ!」
ムッとした表情のまま、ジョルジュがそう叫ぶと、カレンは溜息をついた。
「やっぱり、そうだったのかい! あたしがちょっと留守してる間に、又、モメたんだね!」
「いや、だからその、それはもう解決したって……」
「お黙り!」
カレンの大声に、ジョルジュだけでなく、そこにいた者全員がビクリとし、彼女を見た。
そんな彼の心の声が聞こえたのか、彼女ははっきりそう言った。
「だよな」
ジョルジュがそう言うと、シモーヌは少し首を傾げながら尋ねた。
「ジョルジュさんは、フランスの味方なのですか?」
「まぁ、手当がよければイギリスにつくこともあるが、基本的にはフランスだな。ここで生まれ育ったから、ここを守りたいって気持ちもあるし」
「そうですか」
「お前は?」
「私もですよ」
そう答えると、シモーヌは微笑んだ。
「気が合いそうですね」
「そ、そうか?」
そう聞き返すジョルジュの顔は、少し赤かった。
「じゃあ、奥で少し打ち合わせします?」
「まぁ、そこまで言うなら、してやってもいいが……」
そう言って、少しわざとらしい咳払いをするジョルジュの顔は真っ赤だった。
「では……」
そう言って彼女が奥の席を手で示した時だった。
「みんなでよってたかって、何の騒ぎだい?」
そう言いながら、女性にしては少し筋肉質の赤毛の女性が声をかけてきたのは。
「カレン姐(ねぇ)さん!」
集まっていた男達の一人が思わずその名を呼ぶと、シモーヌの後ろからついていこうとしていたジョルジュもそちらを振り返った。
「姐さん……。そいつも一緒なんだ」
ジョルジュが彼女の傍に寄りそうように立っている、東洋人にしては背の高い男をチラリと見た。
「あれ? 新入りかい?」
そんな彼をチラリと見ると、カレンは彼よりもその傍にいる背の高い黒髪の少女が気になったらしく、そう声をかけた。
「はい、シモーヌと申します。バートさんやジョルジュさん達にお世話になってます」
彼女がそう言って軽く膝を曲げて挨拶すると、カレンは頷いた。
「ああ、バートとマルクは、面倒見がよくて、優しいからね。分からないことがあったら、色々教えてもらうんだよ」
「はい」
ニコリとしながらそう答えるシモーヌに、カレンは頷いた。
が、ジョルジュは何故か不機嫌そうだった。
「おや、機嫌悪そうだね? 又、モメてるのかい?」
そんな彼に近付き、ニヤリとしながらカレンがそう尋ねると、むっとした表情のまま、彼は言った。顔を見ずに。
「だって、その言い方じゃ、兄貴やバートは頼りになっても、俺は頼りにならないみたいじゃないですか」
「まぁ、今みたいに他の傭兵仲間に囲まれるようじゃね」
「それは、もう解決しましたよ!」
ムッとした表情のまま、ジョルジュがそう叫ぶと、カレンは溜息をついた。
「やっぱり、そうだったのかい! あたしがちょっと留守してる間に、又、モメたんだね!」
「いや、だからその、それはもう解決したって……」
「お黙り!」
カレンの大声に、ジョルジュだけでなく、そこにいた者全員がビクリとし、彼女を見た。