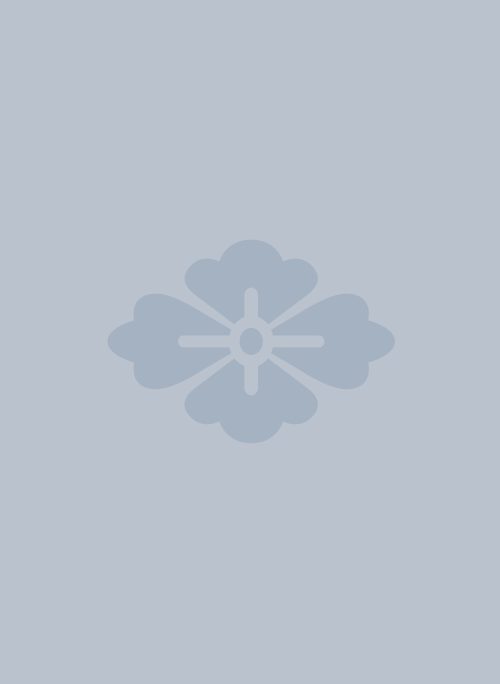──その少女は、ある日、突然、やってきた。
イングランド軍がフランスに攻めてきて、小競り合いがいつも起こっている町の酒場に。
「あの……仕事を紹介して頂ける酒場というのは、ここでしょうか?」
黒いフードをとって現れたのは、長い黒髪の巻き毛に薄い緑色の綺麗な瞳の美少女だった。
「ああ、ここで間違いねぇが……まさか、お嬢ちゃんが登録するのかい?」
「いけませんか?」
そう言いながら、少女は黒いマントをするりと脱いだ。
身長は一七〇センチ位で、女性にしては高い方だった。
その上、上等な乗馬服のようないでたちが、すっきりして見える為に、より一層すらりと背が高く見えた。
「そりゃま、やりたいって言うのを無理に止める気は無ぇが……危ないぜ?」
左側の目に眼帯をつけた酒場の主人が、少女を足の先から頭のてっぺんまで見回してそう言うと、少女はにこりと微笑んだ。
「気をつけますわ。御忠告、ありがとうございます」
酒場に来る傭兵にしては丁寧なその言葉遣いに、酒場の主人は彼女に何か複雑な事情があるのだろうと分かった。
「しょうがねぇな……。最初は、誰かと一緒に行くんだぞ。そうだな……バート」
その名に近くで仲間と酒を飲んでいた男が立ちあがり、カウンターまでやって来た。
「何だい、マスター?」
短く切り揃えた黒髪に人の良さそうな顔。そして、服の上からでも何となく分かる、筋肉質っぽい体つき。
だが、一番印象に残るのは、その屈託の無い笑顔だった。
「この子が新しく仕事をしたいと言ってるんだが、次の仕事、一緒に行ってやれないか?」
そのマスターの言葉に、少女はバートに軽く頭を下げた。
「ほう……。その若さと可愛さで、傭兵か? 苦労してるみたいだな」
少女はバートのその言葉に苦笑すると、彼は少女に手を差し出した。
「俺は、バート。よろしくな」
「私は、シモーヌと申します。どうぞ、宜しくご教授下さいませ」
少女のその丁寧な言葉遣いと少し足を後ろに引いてのお辞儀に、バートは苦笑した。
「ここでは、そんな丁寧な言葉遣いは無用だぜ、お嬢ちゃん。気楽にいこうぜ!」
「分かりました。では、『お嬢ちゃん』もよして下さいね」
「それは、お前の働き次第だなぁ」
そう言ってワイングラス片手に近付いて来たのは、既に赤い顔の少年だった。
イングランド軍がフランスに攻めてきて、小競り合いがいつも起こっている町の酒場に。
「あの……仕事を紹介して頂ける酒場というのは、ここでしょうか?」
黒いフードをとって現れたのは、長い黒髪の巻き毛に薄い緑色の綺麗な瞳の美少女だった。
「ああ、ここで間違いねぇが……まさか、お嬢ちゃんが登録するのかい?」
「いけませんか?」
そう言いながら、少女は黒いマントをするりと脱いだ。
身長は一七〇センチ位で、女性にしては高い方だった。
その上、上等な乗馬服のようないでたちが、すっきりして見える為に、より一層すらりと背が高く見えた。
「そりゃま、やりたいって言うのを無理に止める気は無ぇが……危ないぜ?」
左側の目に眼帯をつけた酒場の主人が、少女を足の先から頭のてっぺんまで見回してそう言うと、少女はにこりと微笑んだ。
「気をつけますわ。御忠告、ありがとうございます」
酒場に来る傭兵にしては丁寧なその言葉遣いに、酒場の主人は彼女に何か複雑な事情があるのだろうと分かった。
「しょうがねぇな……。最初は、誰かと一緒に行くんだぞ。そうだな……バート」
その名に近くで仲間と酒を飲んでいた男が立ちあがり、カウンターまでやって来た。
「何だい、マスター?」
短く切り揃えた黒髪に人の良さそうな顔。そして、服の上からでも何となく分かる、筋肉質っぽい体つき。
だが、一番印象に残るのは、その屈託の無い笑顔だった。
「この子が新しく仕事をしたいと言ってるんだが、次の仕事、一緒に行ってやれないか?」
そのマスターの言葉に、少女はバートに軽く頭を下げた。
「ほう……。その若さと可愛さで、傭兵か? 苦労してるみたいだな」
少女はバートのその言葉に苦笑すると、彼は少女に手を差し出した。
「俺は、バート。よろしくな」
「私は、シモーヌと申します。どうぞ、宜しくご教授下さいませ」
少女のその丁寧な言葉遣いと少し足を後ろに引いてのお辞儀に、バートは苦笑した。
「ここでは、そんな丁寧な言葉遣いは無用だぜ、お嬢ちゃん。気楽にいこうぜ!」
「分かりました。では、『お嬢ちゃん』もよして下さいね」
「それは、お前の働き次第だなぁ」
そう言ってワイングラス片手に近付いて来たのは、既に赤い顔の少年だった。