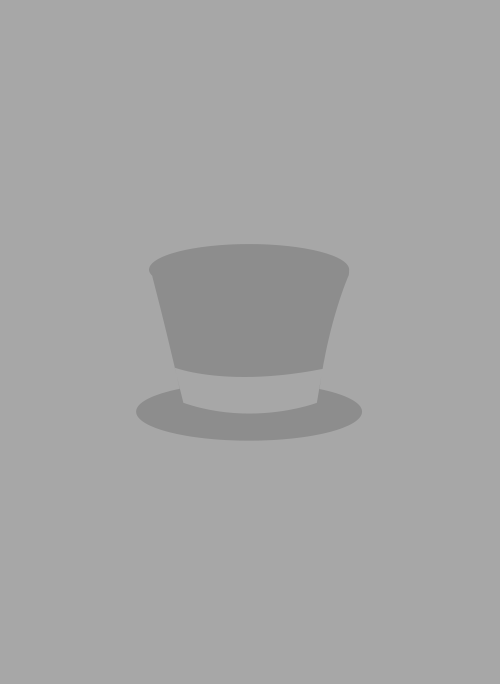「―――僕だって、本当は大好きだった……いや、愛していたさ」
息絶えた少女を見下ろし、僕は煙草を一服する。
墨色の空に紫煙が上る。
いつからだったかな。
本当に、最初はレウはあの人の代わりのつもりだった。
でも、レウの中に僕から彼女を奪った男の血が流れてると思うと、どうにも怒りと嫉妬が勝ってしまい、最後にはこの有様だ。
あー……
達成感と、酷い終わり方の失恋とでごちゃごちゃしてる。
今更考えたって、全部終わった事なのに。
「……」
腰を下ろし、冷たくなっていくレウの頬に触れる。
好きだったんだよな、レウは、こんな僕の事。
死ぬ間際に、告白する程。
そして、僕はそれを裏切るような形で、全部壊した。
いや、もう十年以上前、僕があの女を好きになった時点で、壊れてたのか。
こんな、汚れきった心を持つ殺人犯の事を、何も知らないとはいえ好きになってくれたんだ。
だから、これはせめてものお礼……かな。
レウの細い顎をつまみ、口付けをする。
おとぎ話じゃないから、もちろん目を覚ますことは無い。