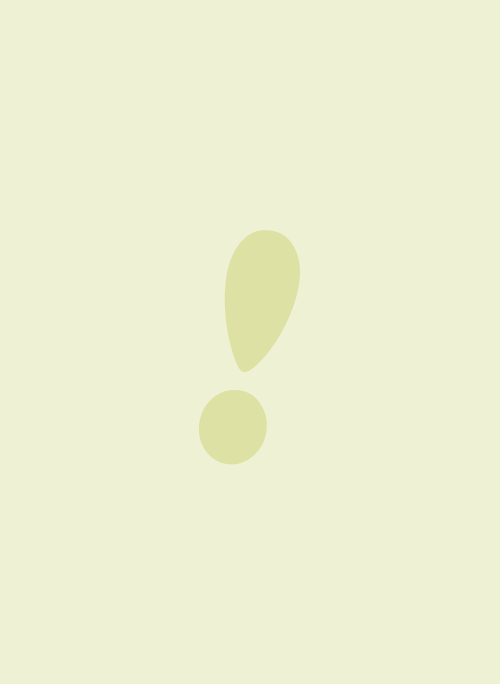退屈で溜め息で窒息しそうな毎日を送っていた。
このまま退屈な毎日に私は埋もれてしまうことが怖くなったそんな日々に変化が訪れたのは16歳の冬の始まりのある日だった。
2才年上の先輩に偶然街中で会って声をかけられた。
私は人の顔なんて覚えていない、だから街中で声をかけられることはあっても、自分からは声などかけたことが無かった。
『久しぶり!』
私は気付かず街中を歩いていた。
いきなり肩を叩かれ、私は睨みながら振り返ると、相手は一瞬怯んだ。
顔を見て知った顔だったので、目付きが何時もの目付きに戻った。
相手はその顔の変化に安心したのか、話始めた。
『伊崎 文華さんだよね?!私中学の時の加藤 梨花だよ。覚えてる?』
私は元々あまり人付き合いが得意では無かったが、覚えていた。
確か二年先輩の人だ。
『はい。覚えてますよ。お久しぶりです。
元気そうですね。』
すると、加藤先輩はやたら嬉しそうに話始めた。
『うわー!覚えててくれて嬉しい!
今何してるの?』
私は淡々と答えた。
『学校の帰りですけど…。先輩はどしたんですか?』
加藤先輩は少し照れ臭そうに言った。
『私、今からバイトなんだけど、来ない?』
私は頭に【?】が浮かんだ。
するとそれを察したのか先輩は話始めた。
『私今軽食屋のバイトしてて良かったらそこで奢るから食べて待っててくれるかな?
バイト終わったらもう少し話したいし。ダメかな?』
私は特に用事もなかったので、二つ返事で了解した。
デパートまでは広くなくて、高級感は無いけれど、ファミリー向けの大きな店の一角に軽食が出来るコーナーがあって、店の前にはブースがあってそこで、食べれるようになっていた。
先輩は一足先に社員通用口から入っていった。
私は表から店内に入り、フードコートに座っていた。
ほど無くして、先輩はその店の制服を着て店内に入って、バイトを始めた。
何も食べないのも悪いと思った私はレジに行き、ジュースを注文すると、先輩はジュースとたこ焼きをトレーに乗せて、会計をするふりをして、私にトレーを渡した。
私は初めてそんなことをされたのでキョトンとしていると、片目を瞑り『ありがとうございました~。』と言ったので、私はそれを受け取りテーブルについた。
時刻は夕方で、店は結構混んでいた。
私は先輩が働いている動作をぼんやりたこ焼きを食べながら見ていた。
楽しそうに仕事をしている先輩が、私には羨ましかった。
キラキラしながら働いていた。
時間を気にもしなかったので、閉店の店内放送が流れて気付くと私は立ち上がり、トレーを返却口の所に持っていくと、先輩が向こう側から声をかけた。
このまま退屈な毎日に私は埋もれてしまうことが怖くなったそんな日々に変化が訪れたのは16歳の冬の始まりのある日だった。
2才年上の先輩に偶然街中で会って声をかけられた。
私は人の顔なんて覚えていない、だから街中で声をかけられることはあっても、自分からは声などかけたことが無かった。
『久しぶり!』
私は気付かず街中を歩いていた。
いきなり肩を叩かれ、私は睨みながら振り返ると、相手は一瞬怯んだ。
顔を見て知った顔だったので、目付きが何時もの目付きに戻った。
相手はその顔の変化に安心したのか、話始めた。
『伊崎 文華さんだよね?!私中学の時の加藤 梨花だよ。覚えてる?』
私は元々あまり人付き合いが得意では無かったが、覚えていた。
確か二年先輩の人だ。
『はい。覚えてますよ。お久しぶりです。
元気そうですね。』
すると、加藤先輩はやたら嬉しそうに話始めた。
『うわー!覚えててくれて嬉しい!
今何してるの?』
私は淡々と答えた。
『学校の帰りですけど…。先輩はどしたんですか?』
加藤先輩は少し照れ臭そうに言った。
『私、今からバイトなんだけど、来ない?』
私は頭に【?】が浮かんだ。
するとそれを察したのか先輩は話始めた。
『私今軽食屋のバイトしてて良かったらそこで奢るから食べて待っててくれるかな?
バイト終わったらもう少し話したいし。ダメかな?』
私は特に用事もなかったので、二つ返事で了解した。
デパートまでは広くなくて、高級感は無いけれど、ファミリー向けの大きな店の一角に軽食が出来るコーナーがあって、店の前にはブースがあってそこで、食べれるようになっていた。
先輩は一足先に社員通用口から入っていった。
私は表から店内に入り、フードコートに座っていた。
ほど無くして、先輩はその店の制服を着て店内に入って、バイトを始めた。
何も食べないのも悪いと思った私はレジに行き、ジュースを注文すると、先輩はジュースとたこ焼きをトレーに乗せて、会計をするふりをして、私にトレーを渡した。
私は初めてそんなことをされたのでキョトンとしていると、片目を瞑り『ありがとうございました~。』と言ったので、私はそれを受け取りテーブルについた。
時刻は夕方で、店は結構混んでいた。
私は先輩が働いている動作をぼんやりたこ焼きを食べながら見ていた。
楽しそうに仕事をしている先輩が、私には羨ましかった。
キラキラしながら働いていた。
時間を気にもしなかったので、閉店の店内放送が流れて気付くと私は立ち上がり、トレーを返却口の所に持っていくと、先輩が向こう側から声をかけた。