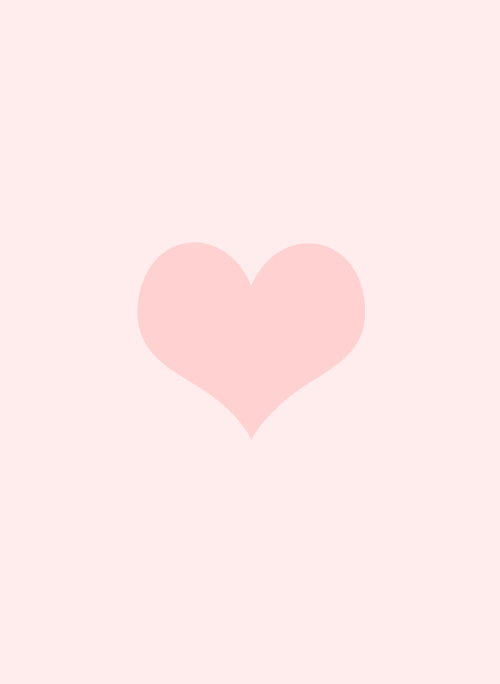「チクショー、ふざけんなぁ!」
友人の結婚式の日。
誘われていた夜の宴席にも行かずに、エーレンフリート・フィッツェンハーゲンは軍のロングコート姿のまま、ベンチで泣きながらクダをまく女の左に座っていた。
女は獣のように声を荒らげ吠えている。そんな彼女に慰めの言葉を吐くでもなく、エーレンフリートも生来の愛想のよくない表情で隣にいるだけ。通りすがりの人が二人を見ても、とても色気のある関係には思えないだろう。
冴え冴えとした寒い夜。月はエーレンフリートの髪と同じ銀の色で、夜空に輝き始めていた。息を吐けば、近くに立っている街灯の明かりに、白い煙のように浮かび上がる。そんな光を、彼は冴え冴えとした青い目で見るともなしに見ていた。
魚尾灯の、文字通り魚の尻尾のように閃く炎は、首都の夜の街を象徴している。上下水道とガス管の埋まる石畳の下。蒸気機関車が大量輸送を可能にし、港では大きな船が人々を新大陸へと運び始めていた時代。
バッツマルトの首都ウォーデンの夜の公園では、そんな革新的な時代とはまったく関係の無い、いかにも人間らしい悲劇が繰り広げられていた。主に、エーレンフリートの右隣で。
「何で世界はこんなに不公平なんだぁ!」
寒風の吹きさらす公園のベンチに座って、泣きながらクダをまく女の名は、マーヤ・クレマー。同じく軍のロングコート姿の彼女は、さきほどから自分の帽子を両手でぐちゃぐちゃにつぶしたり引っ張ったりして、己の中の衝動を表している真っ最中だった。
士官学校時代、彼女は「炎の女」の異名を持っていた。男のように短く髪を切っていてもなお、他の男たちにとっては彼女の赤毛は、怒りに頭を燃え上がらせているように見えたからだ。士官学校の中で数少ない女性生徒の一人であった彼女は、その異名を持つことで他の男に舐められないようにしていたのだと、エーレンフリートは感じていた。
そんな炎の女が、楽しく笑っている姿をエーレンフリートは知っている。同期であり、なおかつ彼女の幼馴染である男女と一緒にいる時だ。
男女の名は、ダニエルとクララ──今日の結婚式の主賓の二人の名だった。
エーレンフリートの目から見て、三人は本当に仲が良かった。彼らと一緒にいる時のマーヤは、炎の女と呼ばれる様子はかけらもなく、屈託なく笑い馬鹿な話に興じていた。
エーレンフリートが何故それを知っているかというと、彼はダニエルと士官学校の寮の同室であり、そこから彼らは友人になったからだ。何かとダニエルに引っ張り出されて行ってみると、大抵そこにはマーヤとクララがいた。
クララは、後方支援部隊希望の亜麻色の長い髪を持つ美しい女性だった。何故軍の士官学校に入ったのかと首をひねるほどだったが、マーヤとダニエルを見つめるクララの目はいつもキラキラと輝いていて、元気のいい積極的な二人に憧れているのがよく分かった。マーヤもまたクララに対し、キラキラと憧れの目を向けていた。それは、ダニエルに対してもそうだった。
そんな三人の中で、エーレンフリートは何度となく距離を掴み損ねてきた。三人は彼を蚊帳の外にしたわけではない。何もかも分かり合っているような彼らだったからこそ、綺麗な三角形だったからこそ、エーレンフリートは自分が入る隙間を見出せなかったのだ。
けれど、三人の美しい三角を見ることを、エーレンフリートは同時に心地よくも思っていた。炎の女マーヤは、ダニエルの友人である彼に対して目を吊り上げるようなマネはしなかった。
『あんた、いい奴だね』
ダニエルがひどい風邪で長く寝込んだ時、見舞いにきたマーヤとクララを男子寮にこっそり入れてやった日。リンゴがたくさん入った紙袋を彼に押し付けながら、マーヤは幼馴染に向けるように屈託なく笑った。彼女の赤毛は、そのリンゴの皮の色とそっくりだった。
「ああ、ああ……クララは綺麗だった、ダニエルも幸せそうだった……でも祝えない、私は祝えない」
昼間から夕方まで続いた結婚式からパーティ。いくら軍人であったとしても女性なのだから、マーヤはどんなに着飾って参加しても許されただろう。しかし、彼女は軍服だった。いつもより濃い化粧だったことだけが違和感だったが、その理由は後で分かることになる。
「おめでとう」という言葉が溢れる幸せな空間で、マーヤは笑って同じように二人に祝福の言葉を口にしていた。しかしその表情は、エーレンフリートの知る、あの屈託のない笑顔ではなかった。慣れていない愛想笑いをする子供のように不器用なものだった。
新郎新婦も、マーヤがおかしいことは分かっていただろう。クララが、花嫁姿のまま大丈夫と彼女に問いかけていた。「昨日祝杯だとお酒を飲んで、実は二日酔いで」と具合の悪そうなフリをして、マーヤは新婦に笑って見せた。
「夜、新居でも仲間内の宴席を開くから是非来てね」
パーティの終わり際、クララがまるで念を押すようにマーヤに声をかける。一瞬、完全に固まった赤い髪の女の後ろから──エーレンフリートは近づいていた。
「クララ、今夜はマーヤを貸して欲しい……大事な話があるんだ」
マーヤの肩に後ろから手をかけて、彼は目の前に立つ新婦に意味ありげな、しかし逆に言えば曖昧な言葉で濁しながらそう告げた。一瞬触れているマーヤの肩が驚きに震えたが、「そ、そうなんだ。大切な話があるんだ」と、赤毛の女もまたそう答える。
新婦は一瞬、喜びの表情を浮かべかけたが、二人の様子がそれほど浮かれたものでないことに気づいたのか、美しい表情を「そう」と、やはり曖昧に濁した。
夕暮れの帰り道。その時はまだ、マーヤは泣いてはいなかった。ただ、黙ったままそう早くない足取りで歩道を歩く。馬車の通る大き目の道のため、エーレンフリートは車道側を歩いた。
「……どこに行くの?」
炎の女とは思えない、ひしゃげた声が一度橋の上で止まる。海までつながる大きな川だ。ゆるやかな流れを、今日最後だろう荷を載せた船が下って行く。
「さあ」
同じく足を止めて、エーレンフリートは船を見た。冬の川の上は寒い。雪が積もっていないのが救いではあるが、それでも肌を切るような冷たさだ。
「大事な話って何?」
その寒さも気にならないように、マーヤはぼんやりと橋の欄干へと近づく。エーレンフリートは、彼女が飛び込んだりしないか注意深く見つめながら、こう答えた。
「……さあ」
くるりとマーヤが彼の方を振り返る。両肘を欄干にもたれるようにして、ロングコート姿の女が、ふてくされた顔でエーレンフリートを見上げる。当然ながら、明るい茶の瞳に普段の輝きはない。
「あんたってさあ……いつもそうだよね?」
普通なら「どうしてあんなことを言ったのか」という追求から始まるべきである。しかし、そうではなかった。何故彼があんな話をクララにしたのか、マーヤは気づいているのだ。
「ダニエルが病気の時、クララと私が男子寮に入りたいって無茶言っても手伝ってくれるし、ダニエルが馬鹿やらかしたら一緒に罰くらってるし……」
最初は、ダニエルに弱味でも握られてるんじゃないかって思ってたわ、とマーヤは背中を欄干に預けて夕暮れの空を仰ぐ。
「帽子、落ちるぞ」
腐っても首都の大通り。橋の上を歩く人も多いため、このまま向かい合っていると通行人の邪魔になる。エーレンフリートもまた、欄干に近づき彼女の横に立った。違うのは向きだけだ。彼は川を見て、彼女は川に背を向けている。
「そうね」と、彼女は空を仰ぐのをやめて頭を戻した。しかし、すぐに横のエーレンフリートを見る。「それよ」という言葉と共に。
「あんた気を遣い過ぎなのよ。気がつきすぎ。ダニエルと私を見てよ。『馬鹿が軍服着るな』って何回教官に怒鳴られたことか……いつだってクララに迷惑をかけて……」
皮手袋の手を持ち上げて、マーヤは白い息を吐く。その手が途中で力を失って、ぱたりと下へと落ちた。
「ああ……どうしよう」
下ろされた手は拳を作ろうとして、再び力なく開かれた。今度は視線を自分の軍靴の先に落として、彼女はこう言うのだ。
「明日から……どうやって生きていこう」
ぽたりと一滴、彼女の靴にだけ雨が落ちた。
友人の結婚式の日。
誘われていた夜の宴席にも行かずに、エーレンフリート・フィッツェンハーゲンは軍のロングコート姿のまま、ベンチで泣きながらクダをまく女の左に座っていた。
女は獣のように声を荒らげ吠えている。そんな彼女に慰めの言葉を吐くでもなく、エーレンフリートも生来の愛想のよくない表情で隣にいるだけ。通りすがりの人が二人を見ても、とても色気のある関係には思えないだろう。
冴え冴えとした寒い夜。月はエーレンフリートの髪と同じ銀の色で、夜空に輝き始めていた。息を吐けば、近くに立っている街灯の明かりに、白い煙のように浮かび上がる。そんな光を、彼は冴え冴えとした青い目で見るともなしに見ていた。
魚尾灯の、文字通り魚の尻尾のように閃く炎は、首都の夜の街を象徴している。上下水道とガス管の埋まる石畳の下。蒸気機関車が大量輸送を可能にし、港では大きな船が人々を新大陸へと運び始めていた時代。
バッツマルトの首都ウォーデンの夜の公園では、そんな革新的な時代とはまったく関係の無い、いかにも人間らしい悲劇が繰り広げられていた。主に、エーレンフリートの右隣で。
「何で世界はこんなに不公平なんだぁ!」
寒風の吹きさらす公園のベンチに座って、泣きながらクダをまく女の名は、マーヤ・クレマー。同じく軍のロングコート姿の彼女は、さきほどから自分の帽子を両手でぐちゃぐちゃにつぶしたり引っ張ったりして、己の中の衝動を表している真っ最中だった。
士官学校時代、彼女は「炎の女」の異名を持っていた。男のように短く髪を切っていてもなお、他の男たちにとっては彼女の赤毛は、怒りに頭を燃え上がらせているように見えたからだ。士官学校の中で数少ない女性生徒の一人であった彼女は、その異名を持つことで他の男に舐められないようにしていたのだと、エーレンフリートは感じていた。
そんな炎の女が、楽しく笑っている姿をエーレンフリートは知っている。同期であり、なおかつ彼女の幼馴染である男女と一緒にいる時だ。
男女の名は、ダニエルとクララ──今日の結婚式の主賓の二人の名だった。
エーレンフリートの目から見て、三人は本当に仲が良かった。彼らと一緒にいる時のマーヤは、炎の女と呼ばれる様子はかけらもなく、屈託なく笑い馬鹿な話に興じていた。
エーレンフリートが何故それを知っているかというと、彼はダニエルと士官学校の寮の同室であり、そこから彼らは友人になったからだ。何かとダニエルに引っ張り出されて行ってみると、大抵そこにはマーヤとクララがいた。
クララは、後方支援部隊希望の亜麻色の長い髪を持つ美しい女性だった。何故軍の士官学校に入ったのかと首をひねるほどだったが、マーヤとダニエルを見つめるクララの目はいつもキラキラと輝いていて、元気のいい積極的な二人に憧れているのがよく分かった。マーヤもまたクララに対し、キラキラと憧れの目を向けていた。それは、ダニエルに対してもそうだった。
そんな三人の中で、エーレンフリートは何度となく距離を掴み損ねてきた。三人は彼を蚊帳の外にしたわけではない。何もかも分かり合っているような彼らだったからこそ、綺麗な三角形だったからこそ、エーレンフリートは自分が入る隙間を見出せなかったのだ。
けれど、三人の美しい三角を見ることを、エーレンフリートは同時に心地よくも思っていた。炎の女マーヤは、ダニエルの友人である彼に対して目を吊り上げるようなマネはしなかった。
『あんた、いい奴だね』
ダニエルがひどい風邪で長く寝込んだ時、見舞いにきたマーヤとクララを男子寮にこっそり入れてやった日。リンゴがたくさん入った紙袋を彼に押し付けながら、マーヤは幼馴染に向けるように屈託なく笑った。彼女の赤毛は、そのリンゴの皮の色とそっくりだった。
「ああ、ああ……クララは綺麗だった、ダニエルも幸せそうだった……でも祝えない、私は祝えない」
昼間から夕方まで続いた結婚式からパーティ。いくら軍人であったとしても女性なのだから、マーヤはどんなに着飾って参加しても許されただろう。しかし、彼女は軍服だった。いつもより濃い化粧だったことだけが違和感だったが、その理由は後で分かることになる。
「おめでとう」という言葉が溢れる幸せな空間で、マーヤは笑って同じように二人に祝福の言葉を口にしていた。しかしその表情は、エーレンフリートの知る、あの屈託のない笑顔ではなかった。慣れていない愛想笑いをする子供のように不器用なものだった。
新郎新婦も、マーヤがおかしいことは分かっていただろう。クララが、花嫁姿のまま大丈夫と彼女に問いかけていた。「昨日祝杯だとお酒を飲んで、実は二日酔いで」と具合の悪そうなフリをして、マーヤは新婦に笑って見せた。
「夜、新居でも仲間内の宴席を開くから是非来てね」
パーティの終わり際、クララがまるで念を押すようにマーヤに声をかける。一瞬、完全に固まった赤い髪の女の後ろから──エーレンフリートは近づいていた。
「クララ、今夜はマーヤを貸して欲しい……大事な話があるんだ」
マーヤの肩に後ろから手をかけて、彼は目の前に立つ新婦に意味ありげな、しかし逆に言えば曖昧な言葉で濁しながらそう告げた。一瞬触れているマーヤの肩が驚きに震えたが、「そ、そうなんだ。大切な話があるんだ」と、赤毛の女もまたそう答える。
新婦は一瞬、喜びの表情を浮かべかけたが、二人の様子がそれほど浮かれたものでないことに気づいたのか、美しい表情を「そう」と、やはり曖昧に濁した。
夕暮れの帰り道。その時はまだ、マーヤは泣いてはいなかった。ただ、黙ったままそう早くない足取りで歩道を歩く。馬車の通る大き目の道のため、エーレンフリートは車道側を歩いた。
「……どこに行くの?」
炎の女とは思えない、ひしゃげた声が一度橋の上で止まる。海までつながる大きな川だ。ゆるやかな流れを、今日最後だろう荷を載せた船が下って行く。
「さあ」
同じく足を止めて、エーレンフリートは船を見た。冬の川の上は寒い。雪が積もっていないのが救いではあるが、それでも肌を切るような冷たさだ。
「大事な話って何?」
その寒さも気にならないように、マーヤはぼんやりと橋の欄干へと近づく。エーレンフリートは、彼女が飛び込んだりしないか注意深く見つめながら、こう答えた。
「……さあ」
くるりとマーヤが彼の方を振り返る。両肘を欄干にもたれるようにして、ロングコート姿の女が、ふてくされた顔でエーレンフリートを見上げる。当然ながら、明るい茶の瞳に普段の輝きはない。
「あんたってさあ……いつもそうだよね?」
普通なら「どうしてあんなことを言ったのか」という追求から始まるべきである。しかし、そうではなかった。何故彼があんな話をクララにしたのか、マーヤは気づいているのだ。
「ダニエルが病気の時、クララと私が男子寮に入りたいって無茶言っても手伝ってくれるし、ダニエルが馬鹿やらかしたら一緒に罰くらってるし……」
最初は、ダニエルに弱味でも握られてるんじゃないかって思ってたわ、とマーヤは背中を欄干に預けて夕暮れの空を仰ぐ。
「帽子、落ちるぞ」
腐っても首都の大通り。橋の上を歩く人も多いため、このまま向かい合っていると通行人の邪魔になる。エーレンフリートもまた、欄干に近づき彼女の横に立った。違うのは向きだけだ。彼は川を見て、彼女は川に背を向けている。
「そうね」と、彼女は空を仰ぐのをやめて頭を戻した。しかし、すぐに横のエーレンフリートを見る。「それよ」という言葉と共に。
「あんた気を遣い過ぎなのよ。気がつきすぎ。ダニエルと私を見てよ。『馬鹿が軍服着るな』って何回教官に怒鳴られたことか……いつだってクララに迷惑をかけて……」
皮手袋の手を持ち上げて、マーヤは白い息を吐く。その手が途中で力を失って、ぱたりと下へと落ちた。
「ああ……どうしよう」
下ろされた手は拳を作ろうとして、再び力なく開かれた。今度は視線を自分の軍靴の先に落として、彼女はこう言うのだ。
「明日から……どうやって生きていこう」
ぽたりと一滴、彼女の靴にだけ雨が落ちた。