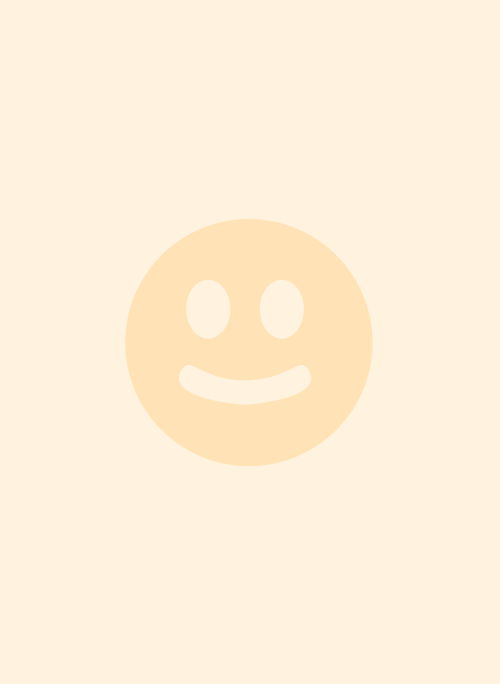【真実のおとぎ咄】
*
「鏡よ鏡。
この森のそばで、まだ死んで間もない子供はいるか?」
かつて悪魔が住み着いたとの曰くのある、暗く深い森。
そこは草木ぐ生い茂るあまりに林床に陽光が差さず、まさに悪魔の棲家にふさわしい暗黒の樹海と化していた。
そんな獣も寄り付かぬような森の中に、小さな一軒屋がある。
薪を割ったのであろう、斧が刺さった切り株が近くにあるだけの、なんの変哲もない家である。
煙突からは煙もあがっていない。
そんな普通の家の中で、なにやら鏡に向かって話しかけているのは、ひとりの魔法使いであった。
白いシャツの上に黒いマントを羽織った、男の魔法使いだ。
うねった蛇のような黒髪を無造作に伸ばしているが、その反面、顔は整っている。
街で売られている人形も色褪せる美貌であった。
「鏡よ鏡。
この森のそばで、まだ死んで間もない子供はいるか?」
魔法使いはもういちど、等身大の鏡に向かって問いかけた。
『二日前に捨てられた、白雪姫の死体が、この森の北側にございます』
普通は物言わぬはずの鏡が、そう答えた。
「白雪姫?」
魔法使いは思わず間の抜けた声を上げた。
白雪姫とは、この森を含めた領土を収める国の姫である。
なんでも肌が淡雪のように白いとかで、本名とは別にその名で呼ばれるようになった。
「白雪姫ねえ……。
できれば男の子がよかったんだが」
まあこの際、使えればなんでも良い。
使えなければ、心臓をとって喰うだけだ。
魔法使いは思う。
魔法使いは、雑用をさせるのにちょうど良い子供を探していた。
召し使いが欲しかったのだ。
自分で薪を割るのも面倒になって来たし、魔法で薪を割ろうとすると余計に労力を使う。
だから、生身の人間が欲しかった。
「また国のお姫さまが、なんで殺されたんだか……」
なんとなく、白雪姫がなぜ死んだのか、魔法使いには察しがついていた。
噂で耳にした限りでは、白雪姫の家族には、父以外は四人の義妹と義母しかいないという。
白雪姫は王の最初の妃の娘で、あとの妹たちは、その後妻の娘である。
どうせ白雪姫の存在を煙たく思った後妻が、白雪姫に毒を盛ったりでもしたのだろう。
魔法使いは呆れた様子でため息を着くと、マントのフードをかぶった。