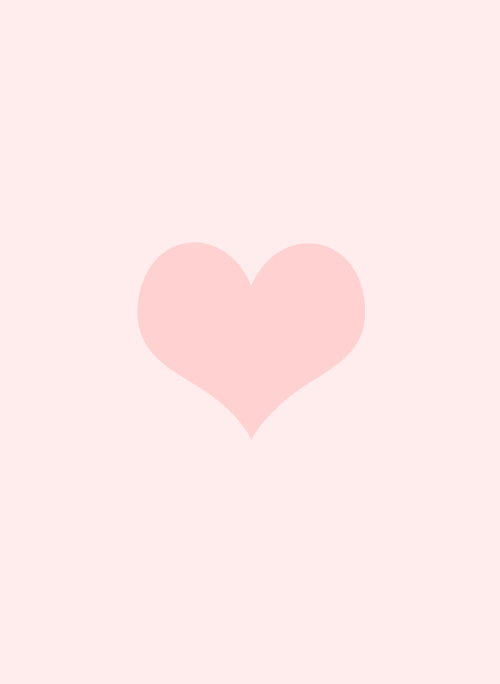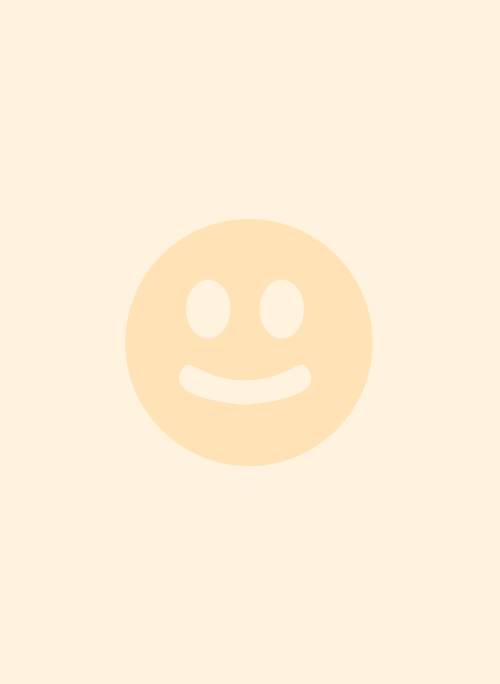朝の空気はどの季節にもひんやりとしている。
新しい日の始まり。
誰にも平等に配られる白紙。
何を書くかはそれぞれの自由。
俺は始発の列車に飛び乗った。
手には愛用のボストンバッグひとつ。
大きな荷物は行き先に送ってあった。
高校1年の末。
俺は春休みに入るとすぐ、両親にひとつの提案をした。
田舎のばあちゃんの家に滞在する。
いつまでも変わることのできない自分に別れを告げるために。
それは提案というより決心だった。
突然の申し出に、当然ながら両親は反対をした。
だけど俺の決心が揺らぐことはなかった。
5日経ち10日経ち、両親は徐々に説得を諦めつつあった。
最終的には、頑なに言い張る俺に両親は折れた。
列車の窓の向こうではその両親が笑顔を見せている。
幼い妹と弟も一緒にだ。
ガラス一枚隔てた向こうの世界。
訣別という言葉を強く意識した。
プラットホームにアナウンスがこだまする。
豪快な空気の音をたててドアは閉まる。
家族に向かって手を振る。
誰もが笑っていた。
訣別に相応しい瞬間だった。
列車は駅を離れ、順調に走り出す。
やがて左手をゆっくりと膝におろす。
いつしかこみ上げていたものがあった。
景色が一面、起き出した街の様子に変わる頃、それはついに溢れ出した。
新しい日の始まり。
誰にも平等に配られる白紙。
何を書くかはそれぞれの自由。
俺は始発の列車に飛び乗った。
手には愛用のボストンバッグひとつ。
大きな荷物は行き先に送ってあった。
高校1年の末。
俺は春休みに入るとすぐ、両親にひとつの提案をした。
田舎のばあちゃんの家に滞在する。
いつまでも変わることのできない自分に別れを告げるために。
それは提案というより決心だった。
突然の申し出に、当然ながら両親は反対をした。
だけど俺の決心が揺らぐことはなかった。
5日経ち10日経ち、両親は徐々に説得を諦めつつあった。
最終的には、頑なに言い張る俺に両親は折れた。
列車の窓の向こうではその両親が笑顔を見せている。
幼い妹と弟も一緒にだ。
ガラス一枚隔てた向こうの世界。
訣別という言葉を強く意識した。
プラットホームにアナウンスがこだまする。
豪快な空気の音をたててドアは閉まる。
家族に向かって手を振る。
誰もが笑っていた。
訣別に相応しい瞬間だった。
列車は駅を離れ、順調に走り出す。
やがて左手をゆっくりと膝におろす。
いつしかこみ上げていたものがあった。
景色が一面、起き出した街の様子に変わる頃、それはついに溢れ出した。