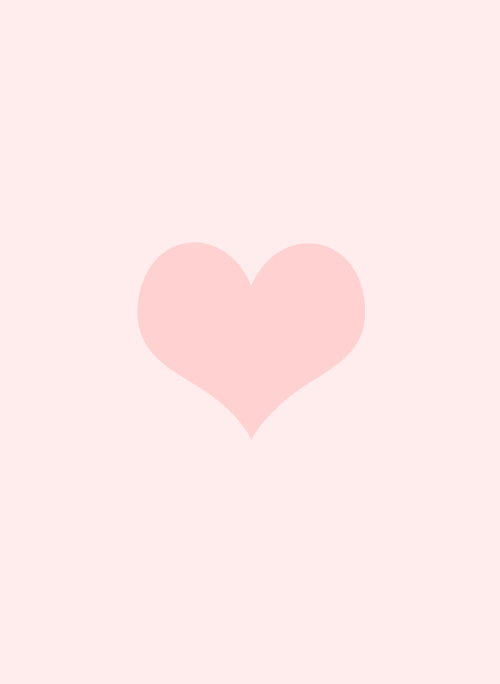それはあの未来から来たらしい女性が言った言葉だった。確か、一番若い使用人から貰ったチョコが……
「ん? なに、信之さん」
「慶次、家で一番若い使用人って誰だろうな?」
俺はあるメイドを思い浮かべながら聞いてみたのだが、
「そりゃあ小松ちゃんだろうね。なんせまだ二十歳だから」
慶次は事も無げに即答した。
俺が思い描いたのも、昨夜寝室で話を交わしたメイドの小松で、それはいいのだが、慶次のやつ、小松の年を知っているばかりか、馴れ馴れしく“小松ちゃん”と言った。遊び人の慶次らしいと言えばそうなのだが、俺は咄嗟にイラっとした。なぜかは分からないが……
「それがどうかした?」
「あ、ああ。その小松のチョコってあるのかな?」
「うん、あるよ。これだよ?」
またしても慶次は即答。しかも沢山ある中から、迷う事なく一つの真っ赤な紙でラッピングされた箱を取り上げた。
「おまえ、何ですぐそれだって分かるんだよ?」
「え? そりゃあ僕も貰ったし、小松ちゃんの手作りチョコは今年が初だからね。真っ先にチェックしたんだ」
「チェックって、もう食べたのか?」
「うん、食べた」
「食べたのか……。それで、ひょっとして変な味はしなかったか?」
そう。未来から来たらしい女性は言ったんだ。一番若い使用人から貰ったチョコは、しょっぱかったと。
俺はゴクっと唾を飲み、慶次の答えを待った。その答えによっては、あの女性が未来から来た事の証になると思うから。
「ん? なに、信之さん」
「慶次、家で一番若い使用人って誰だろうな?」
俺はあるメイドを思い浮かべながら聞いてみたのだが、
「そりゃあ小松ちゃんだろうね。なんせまだ二十歳だから」
慶次は事も無げに即答した。
俺が思い描いたのも、昨夜寝室で話を交わしたメイドの小松で、それはいいのだが、慶次のやつ、小松の年を知っているばかりか、馴れ馴れしく“小松ちゃん”と言った。遊び人の慶次らしいと言えばそうなのだが、俺は咄嗟にイラっとした。なぜかは分からないが……
「それがどうかした?」
「あ、ああ。その小松のチョコってあるのかな?」
「うん、あるよ。これだよ?」
またしても慶次は即答。しかも沢山ある中から、迷う事なく一つの真っ赤な紙でラッピングされた箱を取り上げた。
「おまえ、何ですぐそれだって分かるんだよ?」
「え? そりゃあ僕も貰ったし、小松ちゃんの手作りチョコは今年が初だからね。真っ先にチェックしたんだ」
「チェックって、もう食べたのか?」
「うん、食べた」
「食べたのか……。それで、ひょっとして変な味はしなかったか?」
そう。未来から来たらしい女性は言ったんだ。一番若い使用人から貰ったチョコは、しょっぱかったと。
俺はゴクっと唾を飲み、慶次の答えを待った。その答えによっては、あの女性が未来から来た事の証になると思うから。