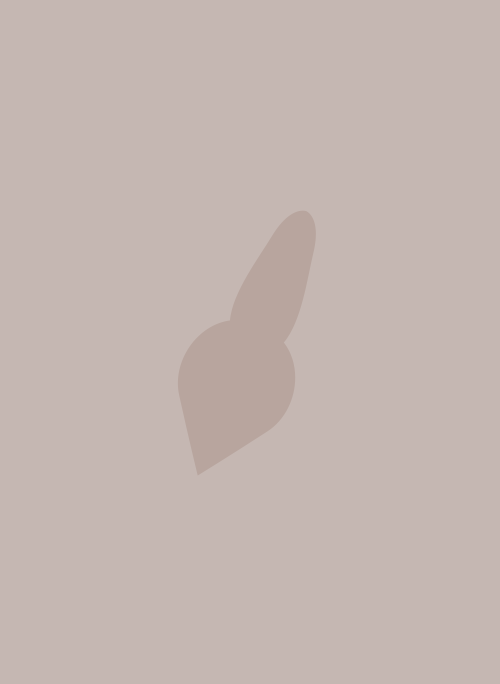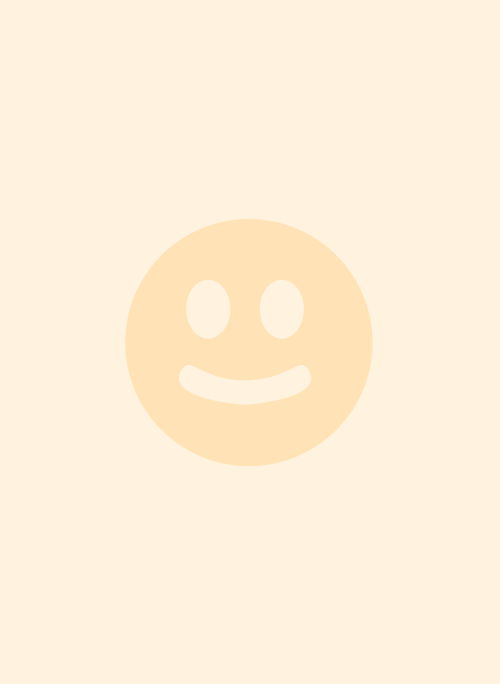その夜、右京を行く者があった。
元来右京はさびれており治安もよくない。深夜に右京を歩く人影というだけでも珍しい。
しかも、まだ若い。十代を半ば過ぎたほどに見えた。
髪を一つにまとめ、身につけているのはつぎのあたった墨染の狩衣に小袴。動きやすい格好だ。腰には刀まで差している。
一言で言ってしまえば怪しい。
どこか落ち着かない足どりもその怪しさに拍車をかけていた。
「だ、大丈夫。大丈夫だ…」
よくよく見れば、顔立ちは意外にもすっきりと凛々しい。ただし、その表情は不安に彩られていたが。
「夜盗なんかいない、いないんだ。いても戦えるし」
独り言は続く。
「だいたい道満様も道満様だ。金を持って消えるなんて何を考えてるんだ。供の身にもなってくれ」
その懐に入れた札―いわゆる式神のよりしろだが―がもの言いたげに動くのを感じて、少し表情が緩んだ。
「ああ、藤影(ふじかげ)。大丈夫、慣れてるさ。空き家を一晩借りればいいだけだが…」
はあ、とため息を吐いた。
「なかなか適当なものがないな…治安が悪いから野宿もしたくないし…」
とぼとぼと行くその背中に――声がかかった。
「もし」
「――ッ!!?」
夜盗を気にしていたばかりである。振り向いた時には懐から一枚の符を引き抜いていた。
小さな雷を招来するものだ。並の夜盗くらいならば―
そう思って相手を見据え、…息を呑んだ。
こんなさびれた場所には場違いな、仕立ての良い狩衣。
それを着こなすのは、こちらと年のころも変わらぬ少年だった。元服も迎えていそうな年頃だが、何故か髪は結わずに散らされている。
その容姿は信じられないくらい美しい。こんな夜に見ると不気味なほどだ。本能的な恐怖を感じた。
ひっ、と喉が鳴った。早く、早くこの符を飛ばさなくては。しかし身体が思うように動かない。
「そこで―何をしてる」
少年の冴え冴えとした声が響いた。
元来右京はさびれており治安もよくない。深夜に右京を歩く人影というだけでも珍しい。
しかも、まだ若い。十代を半ば過ぎたほどに見えた。
髪を一つにまとめ、身につけているのはつぎのあたった墨染の狩衣に小袴。動きやすい格好だ。腰には刀まで差している。
一言で言ってしまえば怪しい。
どこか落ち着かない足どりもその怪しさに拍車をかけていた。
「だ、大丈夫。大丈夫だ…」
よくよく見れば、顔立ちは意外にもすっきりと凛々しい。ただし、その表情は不安に彩られていたが。
「夜盗なんかいない、いないんだ。いても戦えるし」
独り言は続く。
「だいたい道満様も道満様だ。金を持って消えるなんて何を考えてるんだ。供の身にもなってくれ」
その懐に入れた札―いわゆる式神のよりしろだが―がもの言いたげに動くのを感じて、少し表情が緩んだ。
「ああ、藤影(ふじかげ)。大丈夫、慣れてるさ。空き家を一晩借りればいいだけだが…」
はあ、とため息を吐いた。
「なかなか適当なものがないな…治安が悪いから野宿もしたくないし…」
とぼとぼと行くその背中に――声がかかった。
「もし」
「――ッ!!?」
夜盗を気にしていたばかりである。振り向いた時には懐から一枚の符を引き抜いていた。
小さな雷を招来するものだ。並の夜盗くらいならば―
そう思って相手を見据え、…息を呑んだ。
こんなさびれた場所には場違いな、仕立ての良い狩衣。
それを着こなすのは、こちらと年のころも変わらぬ少年だった。元服も迎えていそうな年頃だが、何故か髪は結わずに散らされている。
その容姿は信じられないくらい美しい。こんな夜に見ると不気味なほどだ。本能的な恐怖を感じた。
ひっ、と喉が鳴った。早く、早くこの符を飛ばさなくては。しかし身体が思うように動かない。
「そこで―何をしてる」
少年の冴え冴えとした声が響いた。